進行別 がん標準治療 放射線と抗がん剤の同時併用療法と外科手術を適材適所に
化学放射線治療を行い、問題が出れば手術
化学放射線治療のもうひとつの問題点は、放射線による晩期毒性です。
これまで日本では放射線は計60グレイ照射されてきました。これは正常細胞が耐えうる限界に近い照射量です。
その結果、心臓の周囲や胸に水が溜まったり、時には放射性肺臓炎を起こすこともあります。
「肉眼的にがんが消えた人では、約10パーセントが心臓や肺の病気で死亡しており、治療の影響が否定できない」と大津さんは語っています。
ところが、最近アメリカで放射線の量が64グレイでも50グレイでも治療成績に差はないという比較試験の結果が報告されました。
そこから、今は「副作用と次の救済治療を見越して化学放射線治療が行われるようになってきた」(大津さん)のです。
具体的には放射線の照射量を50グレイ程度にして、救済治療として行われる手術の負担を軽くするというものです。
こうした変化から、化学放射線治療を行って、がんが残ったり再発すれば手術というのが最近の流れの一つといいます。そういう意味では、手術か化学放射線治療かというより、手術と化学放射線治療を組み合わせてより高い治療成績が目指されるようになっているのです。とくにT3ではこうした傾向が強くなっています。
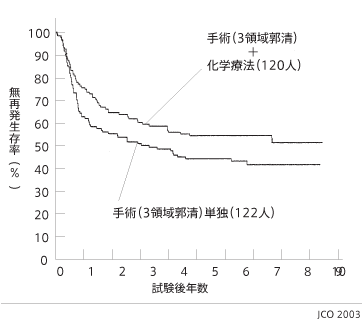
- 手術死亡 3~10パーセント
- 術後肺炎 20パーセント前後
- 縫合不全 15~20パーセント
- 肝・胃・心障害 3~5パーセント
- 吻合部狭窄 14~25パーセント
- 食べられる量が少なくなる
- 頸部食道がんでは、声を失うことも
- 飲みこむ際の違和感(治療中)
- 皮膚炎(治療中)
- 心障害(治療後、まれ)
- 抗がん剤の副作用(吐き気、口内炎、食道炎、白���球・血小板減少、食欲不振、脱毛、腎障害等)
3期後半から4A期
化学放射線治療と化学療法が中心
がんが食道の壁を突き抜けて周囲の臓器に食い込んだ状態が3期後半(T4)、離れたリンパ節などに遠隔転移を起こした状態が4A期です。この段階は、化学放射線治療が中心です。
以前はT4でも手術をする施設もありましたが、5年生存率は5パーセント以下で、現在では手術はまず行われなくなっています。化学放射線治療では5年生存率は15~20パーセントほどです。このステージでは救済治療として手術を追加することに意味があるかどうかはまだわかっていないと、大津さんは語っています。
4B期
がんがさらに遠くの臓器に転移した場合です。この場合は、抗がん剤による化学療法が標準治療です。がんによって食道が詰まった場合には、ステントという金属製の筒を食道に留置したり、放射線を局所的に照射してがんを縮小させる治療も行われています。
食道がんの部位による手術の違い
食道がんは、できる部位によって四つに分けられています。日本人の食道がんの半数を占めるのが食道の中央にできる胸部中部食道がんです。ついで、食道の下部にできる腹部下部食道がん、そして一番少ないのが食道上部、および頸部食道がんです。
いずれの場合も、がんのできた部位の食道を切除し、がんが広がった臓器を切除、食道を再建するという点では変わりありません。しかし、安藤さんによると「頸部のリンパ節郭清は、場合によって行わないこともある」と言います。胸部食道がんの手術では、頸部、胸、腹と3領域のリンパ節郭清が基本です。しかし、下部腹部食道がんの場合は、頸部のリンパ節転移が起こる率が低いので、頸部をあけてリンパ節郭清を行わないところも多いそうです。
一方、頸部食道がんは進行するとすぐ前に位置する喉頭を一緒に摘出することが少なくありません。「無理に残しても、間にある反回神経が麻痺してしまうと、逆に誤嚥から肺炎を起こす危険があります」と安藤さん。反回神経は声帯を動かす神経で、呑み込み(嚥下)にも重要な働きをしています。ところが、極めてデリケートで麻痺しやすい神経です。
声帯を残しても反回神経が両方麻痺してしまうと、食べ物が気管から肺に入って、誤嚥性肺炎を起こす危険も高くなります。これは高齢者にとっては命とりにもなる病気です。
そのため、進行がんでは喉頭を同時に摘出することが多いのです。
「化学放射線治療は機能を残せるのが大きな長所。機能を残してがんを治すという意味では、頸部食道がんは胸部食道がんなどより化学放射線治療のニーズが高いといえます」と安藤さんは語っています。
化学放射線治療
欧米では、40~50グレイの放射線を照射するのが一般的ですが、日本では50グレイが現在は一般的です。
具体的には治療1週目と5週目に抗がん剤を投与し、放射線は1日1.8グレイずつ、週に5日毎日連続して照射します。計50グレイになるまで、5週間ほど照射することになります。
大津さんによると放射線も「現在は3次元照射で食道がんに集中して当てているので、心臓など周囲の臓器に与える影響を少なくなった」といいます。抗がん剤は、いずれの時期でもブリプラチンやランダ(一般名シスプラチン)と5-FU(一般名フルオロウラシル)の2剤併用療法が中心です。より効果の高い抗がん剤の導入も課題のひとつで、現在はアクプラというシスプラチンの誘導体の臨床試験が行われています。これは、シスプラチンより腎臓に対する毒性が低いのが長所です。「日本ではタキソテールも認可されたところで、海外ではタキサン系抗がん剤(タキソールやタキソテール)を組み入れた化学放射線治療の臨床試験も行われているところ」といいます。
化学放射線治療で根治を目指す場合は、十分量の化学療法と放射線照射を行う必要があり、副作用も比較的高度であるため、今後は副作用の軽減も大きな課題とされています。
手術による食事摂取への影響
手術の直後は、食事量も制限されますが、それ以降もなかなか食べられないという人が多くなります。大津さんが以前行った調査によると、化学放射線治療によってふつうに食事をしていた人が治療後食べられなくなることはほとんどないそうです。
がんで食道がつかえてモノが飲み込みにくくなっていた人でも、化学放射線治療後は88パーセントが改善。おかゆから固形食などに移行できるそうです。これが手術となると、改善率は59パーセント。その結果、手術では平均して4.4パーセント体重が減少しますが、化学放射線治療では逆に1.5パーセントほど体重が増えていました。「見た目も体力も全く違います」と大津さんは語っています。ただし、安藤さんは「化学放射線治療により瘢痕性狭窄を来し通過障害がより高度になる場合も少なくありません」とつけ加えています。
同じカテゴリーの最新記事
- グラス1杯のビールで赤くなる人はとくに注意を! アルコールはがんの強力なリスクファクター
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 食道がんの薬物療法が大きく動いた! 『食道癌診療ガイドライン2022』の注目ポイント
- 放置せずに検査し、適切な治療を! 食道腺がんの要因になる逆流性食道炎
- 免疫チェックポイント阻害薬が薬物療法に変革をもたらした! 食道がん、キイトルーダが1次治療に加わる見込み
- 5年生存率を約2倍に改善! 食道がんの術後ペプチドワクチン療法
- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状
- ステージⅡとⅢの食道がんに放射線減量の化学放射線治療 食道がん治療に切らずに食道温存への期待
- 進行・再発食道がんに対する化学治療の最新知見 免疫チェックポイント阻害薬登場により前途が拓けてきた食道がんの化学療法


