難しい食道発声はもういらない。訓練なしで、自然に声が出せる 失われた声を回復する簡単「気管食道シャント法」
新しい空気の通り道を作る
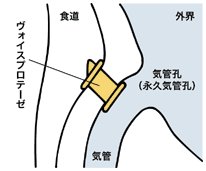
[気管食道シャント法で声が出る仕組み]
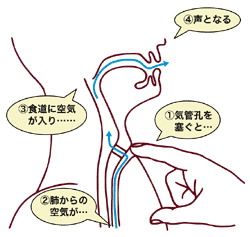
気管食道シャント法は、簡単にいえば、新しい空気の通り道を作る方法です。福島さんが、採用しているのは「プロヴォックス」(商品名)というヨーロッパで開発されたシステムです。
その方法は、非常に合理的といえます。喉頭摘出後には首にあけた孔と気管をつないで永久気管孔を作り、ここから空気が出入りするようになります。シャント法では右下図のように気管と食道の間に孔をあけ、ヴォイスプロテーゼというシリコン製のチューブを留置します。チューブで、食道と気管をつなぎ、新しい空気の通り道を作るわけです。シャントとは、「つなぐ」という意味だそうです。
この状態で、永久気管孔を指でふさぐと、肺の空気は気管からヴォイスプロテーゼを通って食道に入り、口から出ていきます。このとき、移植した空腸(人によっては自分の食道)の粘膜同士が空気で震えて振動し、声になるのです。ヴォイスプロテーゼには一方通行の弁がついているので、気管から食道には空気が流れますが、食道のほうから飲食物や唾液が気管に入る心配はありません。
つまり、原理的にはふつうに話すのと同じように、肺の空気を利用して口から息をはきながら声が出るわけです。したがって、発声に特別な訓練も必要ないのです。
「気管孔をうまくふさぐ要領さえ覚えれば、ふつうに声が出ます」と福島さん。これが、第1の利点です。
訓練なしで自然に声が出る
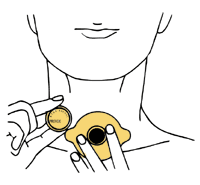
実際には、直接指で気管孔を塞ぐことは少なく、特殊なシールを永久気管孔の周囲に貼り、ここにカセットボタン(温度・湿度交換管=HME)をとりつけます。このボタンを押すと、気管孔が閉じるしくみです。このカセットは、外気に湿度や温度を与え、塵を取り除くフィルターの働きもします。ふつうは、外気は鼻でゴミをとりのぞかれ、温度36度、湿度98パーセントぐらいに加温・加湿されて肺に送り込まれます。ところが、永久気管孔を設置すると鼻の機能が失われるので、乾燥した冷たい空気がそのまま肺に入り、セキやタンが増えるのです��このカセットを利用すると、そうした面でも楽になるのです。
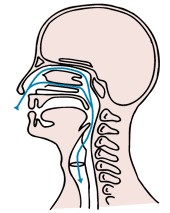
温度36℃/湿度98%
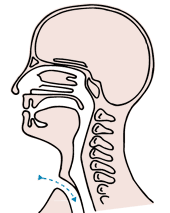
温度20℃/湿度42%
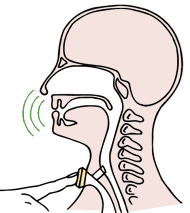
温度28.8℃/湿度65%
そして、患者さんにとってうれしいのは、より自然に近い会話ができることです。もちろん、声帯がピンポイントで振動して声を発生させるのに対し、こちらは空腸の壁面で発生させる音。元通りの声が出るわけではありません。けれども、「障害があるとはわからない程度になる人が多いですね」と福島さんは話しています。
食道発声法は空気を飲み込んでゲップを声にするので、飲み込める空気の量にも限りがあります。一息に話せる言葉は、せいぜい5~7語。「ありがとう」というのがやっとで、一息では自己紹介もできなかったといいます。ところが、シャント法では4000~5000ccもある肺の空気を利用するので長く言葉を続けることができるのです。吐き出す空気の量を調整することで、音量を変えたり、言葉に抑揚を付けることも自在にできるのです。
ヴォイスプロテーゼを留置する手術も、そう大変なものではないようです。
福島さんによると、「留置にかかる時間は5分ほどで、体の負担は少ない手術」だそうです。実際には、点滴で静脈麻酔をして、内視鏡でモニターを見ながら、食道と気管の間にヴォイスプロテーゼを留置します。漏れなどの確認のために、2~3日から1週間ほど入院しますが、手術当日から食事もできるそうです。
たいていは、がんの手術をして永久気管孔も落ちついたころ、平均すると術後1カ月ぐらいで留置できるそうです。
欧米では気管食道シャント法が一般的
日本では、気管食道シャント法といっても、聞いたことがないという人が多いと思います。しかし、実は欧米ではこの方法が一般的なのです。福島さんによると「食道発声はもちろん、電気式人工喉頭を使っている人もほとんどいません。9割以上の患者さんがシャント法を利用している」というのです。
1つには、歴史の違いもあるようです。日本のような食道発声法の習得システムがない欧米では、古くから気管食道シャント法が研究されてきました。日本にも1980年代にはいくつかのヴォイスプロテーゼが導入されたといいます。しかし、当時のものはまだ未熟で、食道から飲食物や唾液がもれて気管に入り、肺炎を起こすことがありました。そのため、癌研有明病院でも使用を断念したそうです。
しかし、その後も改良が続けられ、90年代後半には現在使われているプロヴォックスなど新世代のヴォイスプロテーゼが出てきました。これを契機に、癌研有明病院でも3年ほど前からプロヴォックスを積極的に使いはじめたのです。
これまで、癌研有明病院でプロヴォックスを装着した患者さんは30人以上。国内では1番実施数の多い病院の1つです。
「肺活量が少なかったり、永久気管孔の孔の形の問題でうまく声が出なかった人も2人いますが、95パーセントの人はよく声が出ています」と福島さん。感染や肺炎を起こした人はこれまで皆無。プロヴォックスは、合わなければ取りはずすことも可能ですが、はずして欲しいという人は1人もいないそうです。
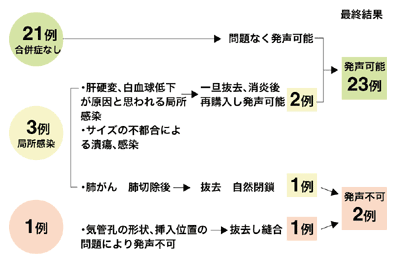
同じカテゴリーの最新記事
- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR
- 光免疫療法が踏み出した第一歩、膨らむ期待値 世界初、頭頸部がんにアキャルックス承認!
- 世界で初めての画期的なBNCT治療が間近に! 頭頸部がんに対する適応承認は今後の大きな発展契機に
- 前がん病変の白板症に注意を! 自分で気づくことができる舌がんは早期発見を
- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!
- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 咽喉頭がんに ダヴィンチの特徴が発揮される微細な作業による治療法
- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策


