進行別 がん標準治療 流れは手術から、機能や形状を温存する化学放射線治療へ
術後補助療法
世界的な標準治療の普及が遅れている
田原さんによると「欧米では進行がんに対しては、術後放射線治療を行うのがふつうで、手術単独より放射線で補助療法を行ったほうが生存率が高いという報告もされている」といいます。
そこで、放射線がいいのならば、抗がん剤を加えればもっと再発を抑えられるのではないかと、術後、あるいは術後放射線治療後に抗がん剤を加えるか加えないかという比較試験が多く行われました。しかし「生存率も再発率も差がなく、抗がん剤を上乗せするメリットはないという結果だったのです」。
しかし、田原さんは「再発リスクの高い人に絞って検討すれば、抗がん剤を上乗せするメリットがあるのではないか」と指摘しています。
実は、これまでの手術経験から、手術断端にがん細胞が認められる、多数のリンパ節に転移がある、リンパ節の外に浸潤している(節外浸潤)といった場合には、再発のリスクが高いことがわかっています。これまでの試験は、こうした再発リスクの高い人も低い人も一緒にして術後補助療法の効果を見ていたために、抗がん剤の効果が弱められたのではないかというのです。
実際に、最近は補助療法を行うのは再発リスクの高い人に限られているそうです。そこで、再発リスクの高い人だけを対象に、ランダもしくはブリプラチン併用の化学放射線治療と放射線単独での補助療法の比較試験が行われました。その結果、再発率、無病生存率ともに化学放射線治療が勝ることが判明。生存期間の上乗せ効果も期待されています。そこで、ランダもしくはブリプラチンを使った化学放射線治療が、術後補助療法の標準になっています。
日本では、まだ科学的根拠が明らかでないUFT(一般名テガフール・ウラシル)やTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)などの抗がん剤を補助療法として術後に使っているところも多いのが現状です。ランダもしくはブリプラチンによる化学放射線治療は、まだ量が日本人に適当かどうかの判断がされていませんが、これが術後補助療法の世界的標準治療であること、また再発のリスクが低い人には補助療法は必要ないことは覚えておきたいものです。
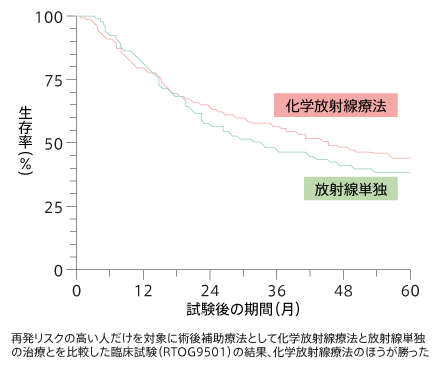
局所進行がん
治療法によって治療後の生活の質に差が出る
日本では、まだ頭頸部がんは外科を中心に治療が行われています。しかし、機能や美容的な面から、最近は手術によるがんの切除が可能でも、放射線や抗がん剤など非外科的治療を求める��が増えています。
手術でも、根治が望めないにも関わらず手術をする(根治切除不能)、つまり再発がわかっていながら手術をするのは、止めるべきと田原さんは語っています。
「これまでの経験から、局所進行がんで再発のリスクを規定する一番大きな因子は頸のリンパ節転移であることがわかっています。頸のリンパ節が4個以上腫れている、4センチ6センチと大きくなったり、両側のリンパ節が腫れていれば、手術をしても再発しやすいことがわかっています。当病院ではもう、両側のリンパ節が腫れていれば手術しない方針です」
こうした根治切除ができない局所進行がんには、化学放射線治療がいいことが明らかにされています。
それならば、切除できる局所進行がんでも、機能の温存という意味で化学放射線治療で治療ができないのか、と思う人も多いと思います。そこで、臨床試験が行われたのですが「切除可能ということは、化学放射線治療がうまくいかなくても手術することで救済できるので、結局放射線治療単独との生存率にはあまり差がなかった」そうです。生存率を上乗せするほどの効果はなかったのです。
しかし、欧米では今、喉頭がんは生存より喉頭が残るかどうか、つまり治療後も話せて食べられることを一番の目標に治療法の評価が行われています。そこで、ランダもしくはブリプラチンと放射線の同時併用療法、FP療法(ランダもしくはブリプラチンと5-FU)を行ったのちに放射線治療、放射線単独という3つの方法を比較する臨床試験が行われました。患者はほとんど3期、4期の患者です。その結果、喉頭が残るという意味では、ランダもしくはブリプラチンと放射線による化学放射線治療が一番いいという結果だったのです。生存率は差がありませんでした。そのため、欧米では現在、喉頭がんで喉頭温存する人はほとんどが化学放射線治療で行われ、再発した場合に手術を行うのが標準的だそうです。日本の場合、まだ手術か化学放射線治療かは、施設によって異なるのが現状です。
「化学放射線治療でのどを残すためには、再発した場合あとで手術ができるだけの力量が必要とされるのです」と田原さん。放射線をあてると手術が技術的に難しくなるので、それができるだけの力をもった外科医がいることも必要だそうです。
治療の方法によって、治療後の生活に大きな差が出ることを覚えておきましょう。また、化学放射線治療後の救済手術による合併症は手術単独より高頻度であることは知っておきましょう。
放射線治療の副作用
機能の温存という意味で、放射線治療は優れた治療法です。
しかし、その副作用も決して少ないものではありません。頭頸部がんの場合、肺や腸など放射線に弱い臓器に放射線がかかる心配がないので、かなり多くの放射線を照射することができます。
それが、たとえば顎下腺や耳下腺にかかると、唾液が分泌できなくなります。その結果、しゃべりにくい、味がわからない、声が嗄れるといった後遺症が出てきます。
「ペットボトルをいつも手にしていて、それを飲みながらでないと話ができない、のどがカラカラに乾いてそれで目が覚めるという人もいます」と田原さん。
同じような症状が出るシェーグレン症候群の薬が多少効果があるとされていますが、放射線のこうした後遺症は今のところ止むを得ないものとされています。
局所進行がんに対する導入化学療法
局所進行がんに対して、外科手術や放射線治療の前に、化学療法を行うという考え方があります。「1985年頃、ランダもしくはブリプラチンと5-FUによる術前化学療法を行ったところ、85パーセントに奏効し、4割で肉眼的にがんが消滅するという非常に高い成績が出てからは、この導入化学療法が世界中で汎用されました」
導入化学療法でがんを小さくできれば、手術もしやすくなり、生存率も上がるのではないかと期待され、外科手術や放射線治療などの局所治療のみと導入化学療法を加える治療との比較試験が数多く行われました。しかし、ほとんどの結果は「生存率に差はない」という結論で、導入化学療法の効果は否定されました。
しかし、最近導入化学療法が、局所進行がんに、外科手術や放射線治療単独を実施する前ではなく、化学放射線治療を実施する前に行うと良好な効果が期待できることが、数多く報告されるようになりました。「2003年にアメリカの臨床腫瘍学会で、一方はFP療法(ランダもしくはブリプラチン+5-FU)にタキソール(一般名パクリタキセル)を加えた3剤、もう一方はFP療法を行い、その後同じように化学放射線治療を行うという比較試験の結果が発表されました。これをみると、病理学的にがんが消滅する率が、FP療法では13パーセント、3剤併用だと32パーセントと報告されています」。
化学放射線治療後のがん消滅率は、どちらの治療法も変わらなかったのですが、生存率で3剤併用の導入化学療法のほうが効果が高かったのです。「タキソールを加えることの生存の上乗せ効果が立証された」と田原さんは考えています。また、FP療法にタキソテールを加えた3剤併用療法でも生存期間に4カ月以上の差が出たと報告されています(ただし、タキソテールは日本で承認された薬ですが、タキソールはまだ未承認薬で、現在臨床試験中です)。
こうしたことから、田原さんは「まだ導入化学療法→化学放射線治療と化学放射線治療単独との比較試験が行われていないので、どちらの治療がよいとの結論を出すことはできませんが、導入化学療法→化学放射線治療を行うのならば、導入化学療法に3剤併用療法を用いることがよさそうです」と語っています。
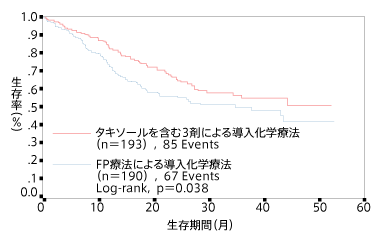
同じカテゴリーの最新記事
- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR
- 光免疫療法が踏み出した第一歩、膨らむ期待値 世界初、頭頸部がんにアキャルックス承認!
- 世界で初めての画期的なBNCT治療が間近に! 頭頸部がんに対する適応承認は今後の大きな発展契機に
- 前がん病変の白板症に注意を! 自分で気づくことができる舌がんは早期発見を
- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!
- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 咽喉頭がんに ダヴィンチの特徴が発揮される微細な作業による治療法
- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策


