本来の機能・形態を回復する頭頸部がんの再建手術 術後の形態や機能障害を改善し、生活の質を向上する必要不可欠な治療
顕微鏡を使った血管吻合で酸素と栄養を補給
頭頸部がんの再建が飛躍的に進歩したのは、先述したように遊離組織移植術の確立と普及に負っている。皮膚だけでなく、その下の皮下脂肪や筋肉、骨、血管などを一体のものとして採取した組織を皮弁というが、先の川島さんが肩胛骨から下顎へ移植したのは肩胛骨皮弁で、肩胛骨皮弁を一旦切除し、下顎へ移し血管吻合によって移植を成功させたのも遊離組織移植術である。
遊離組織移植術は皮弁とそれを養う栄養血管を生きたまま切除し、欠損箇所にマイクロサージェリーで再び血管を繋ぎ直して移植する方法である。
「がんの原発巣から離れたところでも、血行のきわめて良好な組織を、一度に必要とされる量だけを採取し移植することが可能です。加えて、血管吻合が終了すれば、皮弁へただちに酸素と栄養が補給されるため、細菌感染や外からの圧力に対する抵抗力が強く、欠損箇所に*生着しやすいところが大きな利点です」(中塚さん)
形成外科における再建手術の発展を簡単に振り返ってみると、まず皮膚を一旦生体から切り離して移植する遊離植皮術から始まった。遊離植皮術は皮膚の表皮と真皮を含む薄片を採取し、欠損箇所への静置によって移植する方法だ。皮膚の薄片=植皮片は移植したところの創傷面(移植床)からの組織液の浸透により栄養を補給され、やがて移植床からの血液補給を受けるようになって生着する。しかし、遊離植皮術は皮膚だけしか移植できないことや、骨や腱などの血行が不良なところへ生着できない等の限界があり、それを克服するために開発されたのが有茎弁植皮術である。
有茎弁植皮術は皮弁の一端を採取したところに付けたまま、欠損箇所へ移植する方法だ。皮弁の採取箇所と移植箇所の繋がりを茎と呼び、皮弁は移植したところに生着するまで、茎の中の血管(動脈と静脈)を流れる血液によって酸素と栄養が補給される。そのため血行の悪いところにも移植が可能となり、皮膚だけでなく皮下脂肪や筋肉、軟骨、骨なども移植できるようになったところに大きな特長がある。もちろん皮弁が欠損箇所に生着したら、茎は切断し切り離される。
有茎弁植皮術は身体各部の血行などの解明が進むに従い、さまざまな有茎皮弁の移植方法が開発された。頭頸部の再建では胸三角弁(DP皮弁)や僧帽筋や大胸筋を含む筋皮弁を用いて舌や粘膜などの再建が行われた。しかし、有茎弁植皮術は茎を有した皮弁を用いるため、皮弁の採取箇所と移植箇所が遠く離れている場合(遠隔皮弁)は、大がかりな複数回の煩雑な手術が必要となる。遠隔皮弁でも最小限の容易な手術で移植する方法が長いこと模索されてきたが、それを実現したのが遊離組織移植術なのである。
遊離組織移植術が可能になったのは1970年代のマイクロサージェリーの発展に負っている。マイクロサージェリーで皮弁の血管と移植床の血管をすみやかに繋ぎ直せるようになったことが、皮弁の採取箇所からの切除を可能にし、一度の手術で移植=再建の道を切り拓いたのである。遊離組織移植術は皮弁を採取する際、血管を付けた状態で切り離す。あたかも血管が皮弁の柄のように見えることから血管柄付き移植とも呼ばれる。
現在、マイクロサージェリーを用いた遊離組織移植術は、形成外科の再建手術の基本だ。頭頸部がんの再建も同様で、手術による切除で欠損した形や機能を再建するテコとなっている。
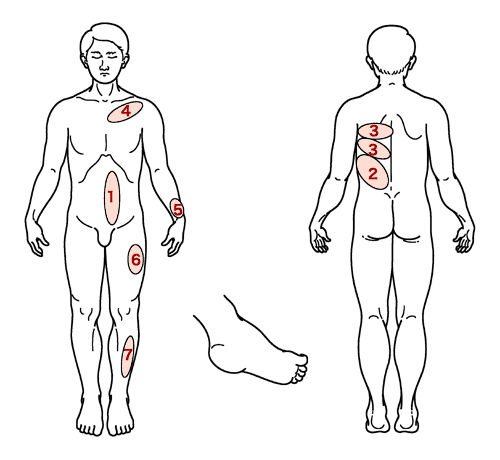
| 血管柄 | 特徴 | |
|---|---|---|
| (1)腹直筋皮弁 | 下腹壁動静脈 | 厚みのある皮弁であるが、筋肉成分の量を加減して用量を調節出来る。舌の再建の第一選択 |
| (2)広背筋皮弁 | 胸背動静脈 | 非常に大きな皮弁として採取・移植でき、広い範囲の欠損の修復に利用出来る。上顎の再建等に使用 |
| (3)肩胛皮弁 | 肩甲回旋動静脈 | 背部の厚い皮膚を含んだ皮弁で、皮弁を二つに分割して使用出来る。下顎・上顎の再建等に使用 |
| (4)胸三角筋皮弁 (DP皮弁) | 内胸動静脈 | 薄く、顔面皮膚の色調との調和が良い。下咽頭、頸部食道等の再建に使用 |
| (5)前腕皮弁 | 橈骨動静脈 | 採取部に植皮を要する点が難点だが、薄くしなやかで血行に富み、血管柄も長い。頭頸部再建では繁用されている |
| (6)大腿皮弁 | 大腿動静脈 | 大腿深動静脈からの穿通枝 鼡経皮弁とよく似た性状だが、血管柄がかなり長く採れ、舌の再建等に使用 |
| (7)腓骨皮弁 | 腓骨動静脈 | 下腿後外側に位置する薄い皮弁。下顎骨の再建等に使用 |
*生着=移植された細胞が新しい場所で、血液がめぐり栄養が補給され、身体の一部として生きて機能し続けること
治療技術は発達し、様々なケースでの再建が可能となった


頭頸部がんは舌・口腔がんをはじめ、副鼻腔がん、咽頭がん、喉頭がん、唾液腺がん、甲状腺がん、さらに顔面に発生する皮膚がんなどだ。その大半は放射線が効きやすい扁平上皮がんだが、これまで手術で切除すると形態や機能が損なわれ、患者のQOLが大きく低下しかねない進行がんには、仕方なく放射線治療を選択することも少なくなかった。しかし、形成外科の再建手術の発達によって頭頸部の形態や機能がきちんと修復されるようになると、より広範な手術による切除が可能となり、頭頸部がんの治療成績の向上がもたらされるようになった。
頭頸部がんの再建はがんを切除した後、ただちに再建手術を行う即時再建がもっとも多い。ただし、腫瘍を切除した痕が変形をきたしたときの欠損部が変形をきたしやすいときや、放射線治療による組織壊死などに対しては、最初の手術から時間をおいた2次的な再建手術が行われることも少なくない。
「もちろん、何年も前に頭頸部がんの手術を受け、うまく再建されなかったケースに対しても、再度の手術によって再建することもあります。よりよい再建を求められる患者さんは、頭頸部がんの再建に熟練した専門医を受診してみるとよいでしょう」(中塚さん)
現在、国立がん研究センターをはじめ、癌研究会付属病院、東大病院、杏林大学付属病院、埼玉医大付属病院などでは、頭頸部外科医と形成外科医が連携して頭頸部腫瘍の手術にあたっている。大幅な再建が必要とされる患者は、通常、そうした病院を紹介されることが多い。再建手術に不安を覚えたときは、いままで手がけてきた再建手術の症例数を主治医にきちんと尋ねることも必要だろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR
- 光免疫療法が踏み出した第一歩、膨らむ期待値 世界初、頭頸部がんにアキャルックス承認!
- 世界で初めての画期的なBNCT治療が間近に! 頭頸部がんに対する適応承認は今後の大きな発展契機に
- 前がん病変の白板症に注意を! 自分で気づくことができる舌がんは早期発見を
- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!
- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 咽喉頭がんに ダヴィンチの特徴が発揮される微細な作業による治療法
- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策


