より効果が高く、より副作用の穏やかな新薬インライタの登場に期待集まる 転移性腎がんのセカンドライン治療はどう変わるか
インライタの登場で2次治療はどう変わる?
現時点では、1次治療には基本として、スーテントというチロシンキナーゼ阻害剤が使われる。そのため、2次治療として作用メカニズムの違うmTOR阻害剤であるアフィニトールが使われることが多い。しかし、インライタの登場によって、これが変わりそうだ。
「アフィニトールでは間質性肺疾患が25%程度の頻度で起こります。この副作用が出たら治療は続けるのが難しくなります。そこで、抗腫瘍効果が得られ、さらに副作用の少ないインライタが検討されると思います」
例えば、【1次治療スーテント→2次治療インライタ→3次治療mTOR阻害剤】とか【1次治療スーテント→2次治療インライタ→3次治療ネクサバール】といった具合だ。2次治療にインライタが使われるようになるだろうという。薬剤の選択肢が広がった転移性腎がんの薬物療法にはさまざまなバリエーションが考えられるが、植村さんは「使用する薬をタイミングよく切り替えていくことが重要」と指摘する。
「薬を切り替え、副作用をコントロールして、長く治療を続けることが大切なので、どのタイミングで薬を替えるのか、見極めが今後の課題です。投与初期に有害事象の出方、薬の反応具合をみて、腫瘍が増大するなど悪化していると判断したら別の薬に替える。例えば、以前よりも増悪の速度が速くなるようなケースでは、それ以上長く使っても効くとは限らないので早めに次の薬剤に切り替えたほうがいいですね。またしばらくしたら、以前使った薬剤に再び交替しても効果があります」
副作用は自己管理と休薬で乗り切れる
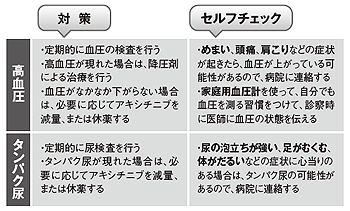
では、インライタの副作用はどうか。「従来の薬に比べて、副作用が少なく、非常に使いやすい薬です」と植村さんは言う。しかし、副作用はなくはない。注意すべき副作用は、高血圧とタンパク尿という。日本人では甲状腺機能低下と皮疹も出る傾向がある。高血圧は���薬を始めるとすぐに出現するので、開始直後が要注意だ(図6)。
「患者さんには毎日血圧を計測してもらい、血圧が上昇したら休薬してもらいます。薬をやめたら血圧は速やかに下がります。毎日飲まなくても『今日はしんどいからやめよう』という日があっても構いません。ある程度治療効果が維持できている患者さんなら3~5日程度薬を止めても大丈夫です。急激にがんが進行することはありません。慣れてきたら患者さん自身で服薬をコントロールできるようになります」
タンパク尿は、深刻な状態になるのは少なく、自覚症状はほとんどない場合もある。
「タンパク尿は休薬をはさむことで減量せずに継続できる可能性があります。タンパク尿を軽視してはいけませんが、致命的ではないのでうまくコントロールすることが重要です」
肺転移がほぼ消失し4年間維持したケースも
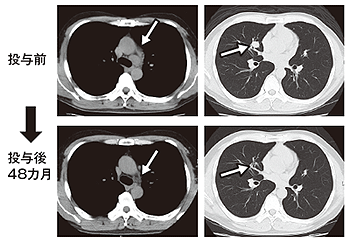
投与経過:2008年4月よりアキシチニブの投与(10mg/day)を受ける。投与後2カ月で、腫瘍が半分以上縮小する(最大43%の縮小効果)。32カ月後にタンパク尿のため休薬後、投与量を減らし(6mg/day)、その後、さらに減量(2mg/day)しながらも、50カ月目まで、縮小効果を維持した。51カ月目に肝転移によりアキシチニブの投与を中止し、薬剤をエベロリムスに変更し治療を続けている
インライタの臨床試験で、高い効果がみられた患者さんの事例を紹介しよう。
48歳の男性。腎臓の摘除術後、インターフェロン治療を行っていたが、転移後、インライタを服用し始めた。
服用開始後8週目、3㎝以上もあった巨大なリンパ節転移がCT画像上43%縮小し、48カ月後ほぼ消失した。肺転移もほとんど消え、それが4年間維持されたという(図7)。
ただ、副作用はいくつか出た。とりわけ影響が出たのは前述のタンパク尿。初めは少量だったがじわじわと増え、薬の減量を余儀なくされた。
このように、転移性腎がんでも、長期に治療が継続できるようになったのは患者さんには朗報だ。また薬の選択肢が増えることは患者さんにはありがたい。植村さんは次のようにアドバイスする。
「自分に合う治療法を医師に考えてもらい、選ぶことです。ただし、目の前の効果だけで判断すると足元をすくわれます。副作用を上手にケアしながら、薬とうまくつきあい、がんともつきあうことです。分子標的薬による治療の歴史は浅く、医師がまだ見たことがない副作用が出るかもしれません。患者さんご自身が状態を把握して、自分で管理していく。自分の体は自分で守るように、医師と情報を共有していくのが理想的です」
同じカテゴリーの最新記事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場
- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択
- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!
- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に
- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に
- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ
- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える
- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術


