腎がんは全摘手術から機能温存へ。問題は機器の認可 体に優しい腎がんの凍結療法
気になる合併症や再発は?
ではまた、がんが小さければできるかというと、必ずしもそういうわけではない。がんのある所によっては、腸管などを避けてプローブを挿入しなければならず、厄介だ。
「大切な腎臓の動脈や静脈のそばにあるもの、腹側にあるもの、がんが臓器の深いところに入り込んでいるものなどはプローブをがんに到達させるのが難しい。がんのある場所もネックになってきます」
凍結療法のおもな合併症は出血や尿漏れだが、これらは同じ経皮的局所療法であるラジオ波と比べても少なく、腸に穴が開くというのもごくまれ。プローブで胸膜を刺してしまうことで起こる気胸も極めて少ない合併症の1つだという。
凍結療法を行っても、再発はある。
「ラジオ波治療と同じように何度か繰り返して行う人もいます。実施回数が多くなれば、その部分の腎機能は落ちます。何度も再発するということは、転移する能力も同時にもっているということになります。もし肝臓や肺などへの転移が現れたら、全身治療へ切り替えることになります」
米国における長期予後調査で証明された効果
米国で行われた腎凍結療法後の長期予後調査結果で、凍結療法の有効性が明らかになっているので紹介しよう。この調査には鴨井さんも加わっている。
1997~2008年までに行われた340例の腎凍結治療のうち5年以上経過観察できた80例が分析された。
80例の平均年齢は66歳、がんの大きさは平均2.3センチ(最大5センチ)である。治療後5~10年の観察期間で局所再発5例、遠隔転移を伴う局所再発2例、遠隔転移のみ4例、全体の死亡は11例、うちがんが原因で亡くなったのは6例。
実はこの80例中がんが証明されたのは55例。なかには良性腫瘍や、たまたま病理検査のために採取した細胞にがん細胞が含まれていなかったという症例もある。そこで、確実にがんがあった55例をみると、5年全生存率84パーセント、非再発生存率は81パーセントと高率で、10年全生存率でも51パーセント、非再発生存率は78パーセントという結果であった。
「がんで亡くなられた6人のうち5人は反対側の腎がんで腎臓を片方とっている人です。多くは肺や肝臓にも転移し、全身状態が非常に悪くなって追加治療をできずに亡くなられています。がん治療自体はうまくいったものの、腎不全の進行で透析治療となり最終的に心不全で亡くなった方もおられます。いわゆる局所再発は5例のみ、いずれも追加治療で長期の生存が得られています。このことから凍結療法を施した場所に対しては再発しにくく、単独の治療としての効果はあるということ、また再発には反対側の腎臓をがんでとっていることが最も影響していることがわかりました」
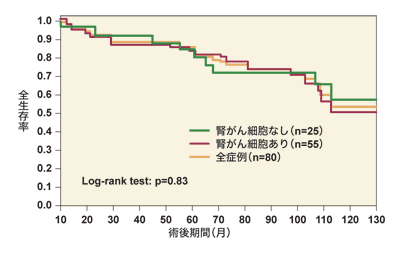
[腎凍結療法の効果(非再発生存率)]
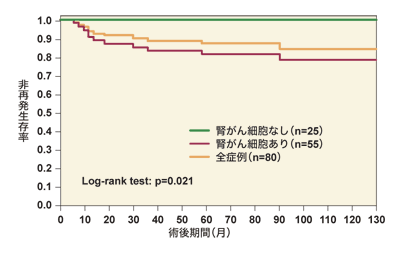
日本での実施へ大きな期待
さて、日本での状況であるが、現在、凍結療法に使用する機器が認可されておらず、保険適応にもなっていない。治験として実施しているのは東京慈恵会医科大学付属病院や慶應義塾大学病院など数施設のみ。
「一般的に受けられる治療にはなっていないことを知っておいてほしい」
と鴨井さんは話す。
「ラジオ波療法はある程度どの施設でもできるようになりつつあります。先行して普及したラジオ波療法と凍結療法は技術的には同じ。機器が臨床現場で使用できるようになればすぐにでも始められるのですが」
鴨井さんは「凍結治療はいい治療法」と確信をもっている。
「ただ機器の認可に少し時間がかかりそうです。それさえクリアすれば日本で広がると思われます。
ラジオ波療法ができる施設は凍結療法の装置を導入できれば治療できるはず。がんの制御という点からいえば、凍結療法がラジオ波療法を上回ると私は考えていて、凍結療法がラジオ波にかわる可能性もあると期待がもてます」
同じカテゴリーの最新記事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場
- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択
- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!
- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に
- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に
- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ
- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える
- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術


