分子標的薬が初めて認可され、腎がん治療は大きな変革期に 「腎癌診療ガイドライン」をわかりやすく読み解く
分子標的薬の使い方が重要
そして、いまもっとも注目されているのが分子標的薬を始めとする薬物療法です。腎がんは、抗がん剤の効かないがんと言われてきました。
しかし、その代わりに進行した腎がんにはインターフェロンαとインターロイキン2というサイトカイン療法が効きます。これは、人体で少量で働く生理活性物質です。インターフェロンとホルモン剤との比較試験(臨床試験)でも、インターフェロンを使うと1年生存率は12パーセント上昇し、生存期間の中央値が2.5カ月延びること。また、エクザール(一般名ビンブラスチン)単独とインターフェロンを併用した比較試験では生存率や非進行生存期間、いずれもインターフェロンを併用したほうが長いことが示されています。併用療法では生存期間の中央値が30週近く延びたのです。
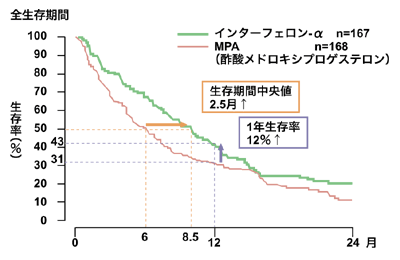
[インターフェロンαの治療効果(2)]
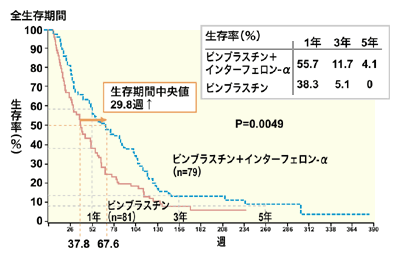
しかし、「実際にサイトカイン療法の有効率(効果を示す人の割合)は20パーセント足らずで、それも比較した群より少し生存期間が延びるという程度。決して満足できる数字ではなかったのです」と藤岡さんは言います。肺転移に関して言えば、縮小あるいは消失することはありましたが、延命効果は明らかにされていませんでした。
ところが、ここに来て進行がん治療に大きな変革をもたらそうとしているのが、スーテント(一般名スニチニブ)やネクサバール(一般名ソラフェニブ)などの分子標的薬です。
たとえば、インターフェロン単独とスーテント単独では、非進行生存期間が5カ月対11カ月とスーテントのほうが長いなど、期待できる成績が次々と発表されています。そこで、日本でも2008年から分子標的薬が腎がん治療に認可されるようになっ��のです。
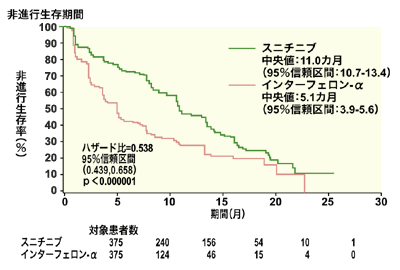
ただし、分子標的薬の使い方はこれからの問題です。分子標的薬にはさまざまな副作用があります。たとえば、ネクサバールには高血圧、手足口症候群、血小板の減少、甲状腺機能が低下して元気がなくなるなど、さまざまな副作用があります。こうした副作用をどうするか。さらに、経済的な問題もあります。
サイトカインも分子標的薬も非常に高価な薬です。藤岡さんによると、すでに「3割負担でも、サイトカイン療法の治療費が払えない患者さんが出てきている」と言います。
今のところ治癒はないわけですから、数カ月の延命にそれだけの価値があるのか、そのあたりも考えなければならない時に来ているのです。
この3年が治療の変革期に
腎がん診療ガイドラインの改訂版は、2009年から準備を始めて3年後には発刊の予定です。そのときには、分子標的薬の位置づけが明確になると藤岡さんは見ています。
「開腹手術の役割は変わらないと思いますが、腹腔鏡手術もラジオ波などの低侵襲治療(体への負担が小さい治療)も大きく変わる可能性があります」
適応が広がる可能性が大きいのです。
遺伝子の研究も進歩しています。
「腎がんは肥満が危険因子の1つなので、がんになりやすい遺伝子多型(遺伝子の塩基の配列が人によって異なっていること)も発見されるかもしれません。薬の効く効かないも遺伝子多型が関与している可能性があります。
インターフェロンも遺伝子多型により感受性(よく効く人)を予測する研究が報告されているので、インターロイキンにもその可能性はあります。また分子標的薬も、遺伝子レベルで感受性や副作用の予測ができるようになるかもしれませんね」
この3年は、がん治療の大きな変革期になりそうです。
「患者さんはただ医師におまかせします、ではだめなのです。問題点を医師と患者が共有し、一緒に考えた上でおまかせしますなら別ですが」と藤岡さん。そして、治療に大事なのは、「患者さんのために」という思い。それが臨床や研究に欠如している場合に、医療不信を招いていると考えるからです。ガイドラインは、日本癌治療学会のホームページからも見ることができるので、「ぜひアクセスして読んでみてください」と藤岡さんは勧めています。
同じカテゴリーの最新記事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場
- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択
- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!
- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に
- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に
- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ
- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える
- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術


