全摘すると腎機能低下で慢性腎臓病→心筋梗塞などになる危険が高まる やっぱり「1つより2つ」の腎がんの温存療法
メタボと関連深い慢性腎臓病
ガイドラインでも述べているように、部分切除の最大のメリットは、正常な一方の腎臓とともに、もう片方も残ることになり、2つの腎機能が保持できる点だろう。
それは単に「ないよりはあったほうがいい」という漠然とした理由からではない。腎臓を丸ごと取ってしまう腎摘より、腎機能を残す部分切除のほうが、長生きにつながる可能性が示唆されているのだ。
「近年、慢性腎臓病という、慢性的に腎機能が低下している状態を指す、新しい概念が普及されるようになってきました。長い時間を経て徐々に腎機能が低下し、慢性腎臓病になると、腎不全を起こして人工透析を必要とするようになるだけでなく、心筋梗塞や心不全などの心血管疾患、脳卒中などの脳血管疾患など重大な合併症を起こすことがわかってきたのです」
つまり、腎摘によって腎臓をすべて切除すると、腎機能の低下が進んで、慢性腎臓病になる危険が高まることが明らかとなってきたのだ。
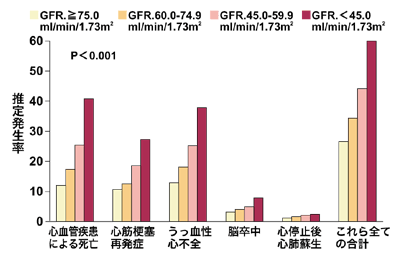
06年に英医学誌「ランセット・オンコロジー」に掲載されたアメリカの研究グループの論文によると、10年以内にクレアチニン・クリアランス(腎機能の低下を示す糸球体ろ過量=GFR)が1分あたり60ミリリットル以下となり、慢性腎臓病になる割合は、腎摘では90パーセント以上だったのに対し、部分切除では50パーセントにとどまっていた。
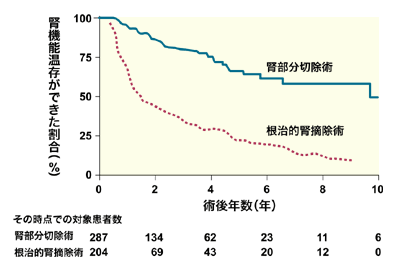
出典:Lancet Oncol 7:735-740,2006
また、GFRが1分あたり45ミリリットル以下になると重症となり、心疾患や動脈硬化の頻度がグンと上がってくるが、腎摘だと10年以内に約半数が45ミリリットル以下となってしまう。これに対して部分切除では1割以下でしかなかったことが明らかになった。
たとえ手術でがんが治ったとしても、そのおかげで腎機能が低下して慢性腎臓病を発症し、心臓病など別の病気で命を失うのでは本当の治療とは言えない。
また、今年発表された医学誌「ジャーナル・オブ・ウロロジー」によると、65歳未満の患者さんにおいて、腎摘よりも部分切除のほうが10年間の生存率が優っていたという結果も出ているという。特に、手術後の人生が長い若い人や、肥満や高血圧、糖尿病、高脂血症などの素因を持っている人にとって、できるだけ腎機能を維持することが肝心であり、そのためにも部分切除は有効ということになる。
北海道まで診断を受けに……
一方、部分切除のデメリットとしてあげられるのは技術的な難しさだ。
「たしかに、出血のコントロールや尿路の修復などは経験を積まないと難しいが、十分にトレーニングすれば決して難しい手術ではない」と近藤さん。
それでも、手術の難しさゆえか、あるいは腎機能温存の意義がまだ理解されていないためか、「積極的に部分切除を行う泌尿器科医はまだそれほど多くない」と近藤さんは言う。
こんな例がある。30代後半の男性。検診で腎がんが見つかった。大きさは3.5センチで、比較的腎臓の上のほうにあった。国立大学病院を受診したところ、腎摘と言われた。「何とか腎臓を残せないものか」と近藤さんのところにセカンドオピニオン(第2の意見)を求めてきた。
基礎疾患もないため、近藤さんは腎臓を残す部分切除を勧めた。そこで男性はサードオピニオンを求めてがん専門の病院を訪ねたところ、そこで言われたのはまたしても腎摘だった。
再びやってきた男性に近藤さんは言った。
「それでもボクなら残しますよ」
ついに男性は、近藤さんの紹介で部分切除に積極的な北海道大学の篠原信雄医師のところまで行き、篠原医師から部分切除を勧められ、ようやく納得して東京に戻り、東京女子医大で部分切除の手術を受けた。
「手術はまったく問題なく終わって、腎機能ももちろんしっかり残せました。今はとてもお元気で、半年に1回、検査のために通院するだけとなりました」
4センチ超でも適応可能
東京女子医大では、4~7センチの1b期でも部分切除を行うようになっている。
「これまでは部分切除は4センチまでが限界と言われてきました。しかし、最近、外に突き出たタイプの腫瘍に対しては、4センチ以上でも腎摘と同等という研究成績が報告されるようになりました。ヨーロッパのガイドラインでも『4~7センチの腫瘍に対する腎部分切除は、経験豊富な施設では施行可能である』として、『その分、腎内局所再発の可能性が高くなるため、より慎重な経過観察が必要である』と書かれています。
当院でも、手術による侵襲はやや大きくなりますが、年齢の若い患者さんに対しては1b期でも積極的に行うようにしています。2007年は1b期の患者さん25例のうち9例で部分切除を行いました」
4センチ以下でも4センチ以上でも、手術方法は開腹手術が中心。4センチ以下の場合なら入院期間は短く、5日目ぐらいで退院できるという。
なお、最近は腹腔鏡による部分切除が普及しはじめているが、同大学では腫瘍がかなり小さい例を除き、あまり行っていない。
「なぜ腹腔鏡にしないかというと、1つは腹腔鏡でやると術後の出血などの合併症の率が少し高いためです。
また、多くの施設では、部分切除するとき、腎臓を氷で冷やした上で切除しています。冷やすことで腎臓を長持ちさせるのですが、腹腔鏡だと腎臓を冷やすのが難しい。冷やさずに手術するとどうしても腎臓の機能が低下し、手術後の成績がよくないので、今のところ開腹手術が中心です」
体外に取り出し、部分切除
さらに同大学では、普通の方法では部分切除が困難な症例に対しても“究極の部分切除”とも言える手術法を行っている。「体外腎部分切除+自家腎移植術」と呼ばれる手術がそれだ。
56歳男性の例だが、25年前に腎がんになり、右腎臓を摘出。残った左腎臓に9.4センチの腫瘍が見つかった。大きさや腫瘍の位置などから、開腹による一般的な部分切除は困難。通常なら左腎臓も完全に摘出し、人工透析を受けるところだが、何とか腎機能を温存させたいと行われたのが体外腎部分切除+自家腎移植術だった。
腎臓を1度体外に取り出し、腫瘍を切除して、残った腎臓を患者の体の中に埋め込むという最新の手術法だ。
この男性の場合、術後3年経って局所再発も遠隔転移もない。透析の必要もなく、元気に仕事をしているという。
「腎がんは治る病気なので、治ったあとの生活のことまで考えないといけません。とくに最近は、検診の普及に伴って20代、30代の若い患者さんが増えているので、なおさら、その方の人生を見据えた治療が大切になっています」
と近藤さんは話している。
同じカテゴリーの最新記事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場
- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択
- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!
- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に
- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に
- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ
- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える
- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術


