がんとの共存生活を支える新薬など登場 分子標的薬が変える腎がんの治療地図
日本と欧米では治療成績が大きく異なる
篠原さんによれば、ネクサバールの臨床試験は、インターフェロンの効かなくなった患者さんに対するセカンドラインの治療として、まず欧米で行われたのだという。
「その結果、ベスト・サポーティブ・ケア(ケアのみで無治療)のグループに比べ、ネクサバールを使うことで、2倍も進行を抑えられることがわかりました。予後を見ても、ネクサバールを使ったグループのほうがいいようでした」
次に、ファーストラインの治療として、インターフェロンとネクサバールを比較する臨床試験が行われた。やはり欧米での試験だ。その結果は、どちらも無病生存期間(がんが進展を始めるまでの期間)が6カ月ほどで、はっきりした差はつかなかった。ただ、QOLに関しては、ネクサバールのほうがいいという結論だった。
これらの臨床試験は欧米で行われたもので、日本人の腎がん治療にそのまま当てはめることはできない、と篠原さんは言う。なぜなら、インターフェロンによる治療成績が、日本と欧米では大きく異なっているからなのだ。
「日本では、インターフェロンを使った場合の無病生存期間は10カ月ぐらいと考えられています。欧米の2倍近いわけですね。なぜ日本人はインターフェロンの治療成績がいいのか、いくつかの仮説はありますが、はっきりしたことはわかっていません。ネクサバールをファーストライン(1次治療)で使った場合、無病生存期間がどのくらいになるのかも、まだ日本で臨床試験が行われていないのでわかりません」
ネクサバールに関しては、今年4月から特定使用成績調査(全例調査)が始まっている。薬が市販された後も、しばらくは特定の施設だけで使用するようにし、使用した全例の治療成績や副作用などに関するデータを集めようというものだ。
日本ではインターフェロンの成績がいいため、ネクサバールをファーストラインで使用しても、無病生存期間がそれを超えられるかどうかはわからない。しかし、インターフェロンとネクサバールのどちらかを選択するのではなく、双方を治療に投入するという前提に立てば、どちらの無病生存期間が長いかは、あまり問題にはならない。むしろ、両者を合計した期間の長さが、患者にとって最も重要��問題といえそうだ。
同時併用するより順次使用が合理的
ネクサバールやスーテントといった分子標的薬が加わることで、腎がんの薬物療法は、複数の薬を駆使して治療する時代に入ろうとしている。ネクサバールとスーテントは、血管新生阻害作用を持つという共通点がある。同じ作用機序を持つ薬は、耐性ができて効果が弱まることが多いが、ネクサバールとスーテントは、両者を続けて使っても効果が減じられることはないという。
そこで問題となるのは、インターフェロン、ネクサバール、スーテントを、どのように組み合わせるのが最もよいのかということだ。
「2種類を同時併用するのがいいのか、それとも1種類ずつ順次使っていくほうがいいのか、という議論がありますね。欧米で行われた臨床試験ですが、インターフェロンとネクサバールを併用したら、奏効率が20~30パーセントと高く、奏効期間も11カ月と長かったという結果が出ています。ただ、2種類使って11カ月なら、単独でそれぞれ6カ月ですから、順次使って12カ月まで延ばしたほうがいいとも言えます。同時併用すると副作用も大きくなるので、その点からも、遂次使用のほうがいいように思えます。効いている期間が同じなら、副作用が軽いほうがいいですからね。ただ、この点については、臨床試験が行われていないので結論は出ていません」
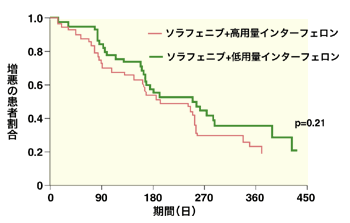
篠原さんによれば、インターフェロンには得意と不得意があるので、それを考慮して治療に生かすことも考えられるという。
腎がんは組織学的に、淡明細胞がん、乳頭状がん、嫌色素細胞がん、紡錘細胞がんなどに分かれるが、インターフェロンは淡明細胞がんにはよく効き、乳頭状がんやその他のタイプには、あまり効かないと言われている。その点、分子標的薬はどのタイプにも効く。
また、インターフェロンは肺転移にはよく効くが、肺以外の部位、肝臓、膵臓、リンパ節などへの転移にはあまり効かない。ところが、分子標的薬はこれにもよく効くのだ。
以上のことから、淡明細胞がんで肺転移がある場合にはインターフェロンから治療を開始し、それ以外の場合には分子標的薬から治療を開始する、という方法が考えられるのだ。
まったく性格の異なる2つの分子標的薬
実際に治療を進めていくと、ネクサバールとスーテントをどう使い分けるのか、という問題が生じてくる。同じ分子標的薬でありながら、この2つの薬は性格の異なる薬なのだ。
ネクサバールにも副作用はあるが、一般的な抗がん剤やスーテントに比べると、対応しやすいのが特徴だ。高血圧、下痢、手足症候群(手足の皮膚に起こる皮疹や腫れなど)などが現れるが、降圧剤や下痢止めの薬などで対応でき、休薬すれば症状は消える。
| 総数 | グレード3 | グレード4 | |
|---|---|---|---|
| 皮膚科/皮膚 | |||
| 手足皮膚反応 | 72(55.0%) | 12(9.2%) | 0- |
| 抜毛 | 51(38.9%) | 0- | 0- |
| 皮疹/落屑 | 49(37.4%) | 5(3.8%) | 0- |
| 掻痒 | 14(10.7%) | 0- | 0- |
| 消化管 | |||
| 食欲不振 | 18(13.7%) | 4(3.1%) | 0- |
| 下痢 | 45(34.4%) | 1(0.8%) | 0- |
| 心・血管 | |||
| 高血圧 | 36(27.5%) | 1(12.2%) | 0- |
| 全身症状 | |||
| 疲労 | 21(16.0%) | 1(0.8%) | 0- |
| 代謝/検査 | |||
| リパーゼ | 73(55.7%) | 32(24.4%) | 8(6.1%) |
| アミラーゼ | 50(38.2%) | 7(5.3%) | 0- |
| 代謝/検査-その他 (トリプシンなど) | 39(29.8%) | 18(13.7%) | 1(0.8%) |
| 肺/上気道 | |||
| 声の変化 | 16(12.2%) | 0- | 0- |
スーテントは、効果の点ではネクサバールを明らかに上回っているが、副作用も強く現れるのが特徴だ。最も重大な副作用は骨髄抑制で、とくに血小板減少が起きやすい。さらに、甲状腺機能低下が出やすく、手足症候群はネクサバールと同じように現れる。
どちらも血管に働きかける薬なので、心毒性には注意する必要がある。とくにスーテントでは、心筋梗塞を含めた心臓合併症が報告されているという。
「ネクサバールとスーテントは、ずいぶんイメージの違う薬です。どちらを選ぶかは、患者さんがどのような闘病生活を望むのかも、重要なポイントになりそうですね」
とにかくがんを攻撃して、はっきりした効果を望むなら、スーテントが向いていそうだ。QOLを優先し、普通の生活をしながらがんと共存しようというのなら、ネクサバールが向いているだろう。
「2つの分子標的薬を順次使う場合、どの順番がいいかという研究も行われています。『スーテント→ネクサバール』と『ネクサバール→スーテント』で、どちらが無病生存期間が長いかを比較したところ、後者のほうが長かったというデータが出ているのです。アメリカとヨーロッパで研究が行われ、どちらも同じ結果になっています」
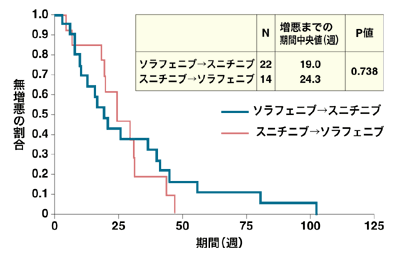
インターフェロンと分子標的薬の組み合わせ方も、分子標的薬同士の組み合わせ方も、今後の研究で何が最も効果的なのか明らかになっていくだろう。
「ネクサバールもスーテントも、これから広く使われるようになっていくでしょう。現在、すでに明らかになっている副作用に気をつけることはもちろんですが、新しい薬は予期せぬ合併症が起こることがある、ということを忘れないでほしいですね」
この点については、とくに強調しておきたいと篠原さんは言う。薬を服用していて、何か体の具合がおかしいと感じたら、医師や薬剤師や看護師に連絡することが大切だ。
図版提供:篠原信雄
同じカテゴリーの最新記事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場
- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択
- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!
- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に
- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に
- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ
- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える
- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術


