渡辺亨チームが医療サポートする:腎臓がん編
渡辺亨チームが医療サポートする:腎臓がん編
篠原信雄さんのお話
*1 腹腔鏡下手術
腎臓がんの手術は従来、腹部を切って腎臓を摘出する開腹手術(お腹を開く手術)が一般的でした。しかし、一部の施設では腹部を大きく切らず、内視鏡を腹壁から挿入して手術する方法(腹腔鏡下手術、腹腔鏡補助手術)が行われています。
この手術は、腹部に穴を開けるだけで行うため傷が目立たず、術後早く退院できるといったメリットがあります。しかし、一般には、この手術は開腹手術より十分な慣れが求められ、手術時間も一般には開腹手術より長くなる傾向があります。
また、急な出血をした場合、対応しにくいという問題もあります。さらに、非常に小さな傷で手術しても、組織を取り出すために腹部にある程度の大きさの切れ目を作る必要があります(下図参照)。
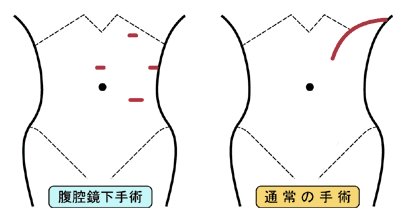
*2 腎臓がん手術の術式
腎臓はその上部に位置する副腎とともにゲロータ筋膜という膜に包まれています。そのため、腎臓がんに対する外科療法としては、副腎も含めてゲロータ筋膜ごと腎臓を摘出する方法が一般的ですが、近年では副腎を一緒に摘出する必要はないのではないかとも考えられるようなっています。
各種画像診断の普及から、腫瘍サイズが小さい腎臓がんが発見される機会が増加しています。このように大きさが4センチ未満の小さい腎臓がんに対しては腎臓を全部摘出せず、腫瘍とともに腎臓の一部のみを摘出(腎部分切除)する手術が行われています。
こうした手術を受けて腎臓を全部摘出した場合でも、再発率、生存率については大差がなく、腎部分切除もさかんに行われるようになっています。
*3 腎臓がんの病期
腎臓の被膜を越えず、がんが腎臓の中にとどまっているのが早期のステージ1です。ステージ2の段階ではがんが腎周囲の脂肪組織まで浸潤するものの、ゲロータ筋膜を越えない状態を指します。
がんがさらに進行して、腎静脈や下大静脈の中にまで広がるか、もしくはがんが大きくなくても隣接したリンパ節に転移しているのがステージ3です。ステージ4はゲローダ筋膜を越えて隣接する臓器(肝臓、十二指腸、すい臓など)、さらにもっと遠隔の臓器(肺、骨など)に転移しています。
| PT 原発腫瘍の状態による分類 | |
|---|---|
| pTX | 原発腫瘍の評価が不可能 |
| pT0 | 原発腫瘍を認めない |
| pT1 | 最大径が7.0cm以下で、腎に限局する腫瘍 |
| pT1a | 最大径が4.0cm以下で、腎に限局する腫瘍 |
| pT1b | 最大径が4.0cmを越えるが7.0cm以下で、腎に限局する腫瘍 |
| pT2 | 最大径が7.0cmを越え、腎に限局する腫瘍 |
| pT3 | 腫瘍は主静脈内に進展、または副腎に浸潤、または腎周囲脂肪組織に浸潤するが、ゲロータ筋膜を越えない |
| pT3a | 腫瘍は副腎または腎周囲脂肪組織または腎洞脂肪組織に浸潤するが、ゲロータ筋膜を越えない |
| pT3b | 腫瘍は腎静脈または横隔膜下までの下大静脈内に進展する |
| pT3c | 腫瘍は横隔膜を越える下大静脈内に進展する |
| pT4 | 腫瘍はゲロータ筋膜を越えて浸潤する |
| PN 所属リンパ節転移の有無による分類 | |
|---|---|
| pNX | 所属リンパ節の評価が不可能 |
| pN0 | 所属リンパ節転移なし |
| pN1 | 1個の所属リンパ節転移 |
| pN2 | 2個以上の所属リンパ節転移 |
| PM 遠隔転移の有無による分類 | |
|---|---|
| pMX | 遠隔転移があるかどうか評価不能 |
| pM0 | 遠隔転移なし |
| pM1 | 遠隔転移あり |
T:Tumor(腫瘍)N:lymph Nodes(リンパ節)M:Metastasis(転移)
*4 腎臓がんの予後
生存率は、通常、がんの進行度や治療内容別に算出しますが、患者さんの年齢や合併症(糖尿病などがん以外の病気)の有無などの影響も受けます。用いるデータによってこうした他の要素の分布(頻度)が異なるため、生存率の値が異なる可能性があります。国立がん研究センター内科レジデント編の『がん診療レジデントマニュアル』によると、腎臓がんの5年生存率はステージごとに次のように分類されています。
ステージ1 75%
ステージ2 63%
ステージ3 38%
ステージ4 11%
*5 腎臓がんの転移
腎臓がんは肺や肝臓、骨、脳などに転移しやすいことが知られています。多くの臓器がんの転移ルートになっているリンパ節へはあまり転移せず、他のがんとは異なった転移の仕方をすることが考えられています。
また多くのがんは転移巣を治療しても、あまり予後がよくなることはありませんが、腎臓がんの場合は、欧米で臨床試験が行われた結果、肺や骨などの転移巣を治療すると、しないよりは予後がよくなることがわかっています。そのため、腎臓がんが転移した場合、全身状態がよい人などについては、転移巣の治療が検討されます。(下グラフ参照)
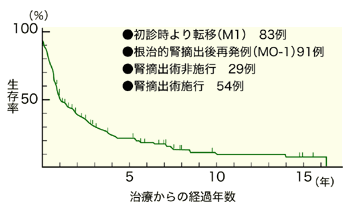
*6 インターフェロン療法
腎臓がんには抗がん剤の治療効果はほとんど期待できません。そのため腎臓がんが広く転移した場合、全身療法の免疫療法が主体となります。インターフェロンαやインターロイキン2という薬を点滴したり、注射したりします。
インターフェロンαの奏効率(腫瘍を小さくする割合)は15パーセント程度で、がんが進行しない平均無増悪期間は半年くらいです。インターロイキン2の奏効率も15パーセント程度で、うち4パーセントで完全寛解(腫瘍が消失した状態)になりますが、日本では高価な治療法なので、一般にはインターフェロンαが使われます。インターフェロンの自己注射は保険がきいて、3割負担で月7万円程度の自己負担になります。
*7 インターフェロンαの副作用
インターフェロンαの副作用には、発熱や頭痛など、インフルエンザに似た症状のほか、血小板減少による出血傾向や座骨神経痛、コレステロールの減少、アレルギーの出現などがあります。命に関わるような副作用としては間質性肺炎がありとくに小柴胡湯との併用は禁忌。また抑うつや不安等が現れることもあり、比較的安全な治療法ですが、場合によっては投薬中止になるケースもあります。
*8 骨転移への治療
腎臓がんの骨転移については、痛みを緩和する上で放射線治療が有効です。また、ビスフォスフォネート製剤の有用性が認められています。その中で、ゾメタ(ゾレドロン酸)は、固形腫瘍の骨転移に対する治療薬として保険適応が通っています。
同じカテゴリーの最新記事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場
- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択
- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!
- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に
- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に
- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ
- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える
- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術


