進行別 がん標準治療 治療の基本は手術。しかし、患者により負担の少ない治療法が最近の流れ
4期・再発の標準治療
がんとの共存を図るインターフェロン療法
腎臓を包んでいるゲロータ筋膜と呼ばれる被膜を越えて、隣接する肝臓や十二指腸、膵臓などにがんが広がっていたり、もっと遠くの肺や骨などの臓器に転移している場合が、4期です。
この場合は、免疫療法の一種であるインターフェロンやインターロイキン2療法が標準治療です。特に再発した場合は、全身療法をする必要があり、このような*サイトカインを注射や点滴で投与する治療は期待されます。
アメリカではインターロイキン2が多く、ヨーロッパや日本ではインターフェロンが主流ですが、どちらも効果はそれほど変わらないようです。奏効率(有効率)は、インターフェロンが12~20パーセント、インターロイキン2が15~20パーセントと、それほど高くありません。「しかし、がんは縮小こそしないけれども、このようなサイトカインによってがんと共存を図ることができます」(篠原さん)
ただし、日本では、インターロイキン2が異常に高価なのが難点です。そのため、インターフェロンが効かなくなった場合、インターロイキン2を使いたくても、なかなか使えないのが現状です。
もう一つ、インターフェロン療法の問題点は副作用です。発熱をはじめ、倦怠感、頭痛、筋肉痛、うつ、甲状腺機能低下、肝障害、骨髄抑制、内分泌異常、眼底出血などの副作用が現れることがあり、決して安全な薬とはいえません。北大でもこのような副作用のために投与中止に至った例が92例中13例あったそうです。
*サイトカイン=細胞が生み出す生理活性物質。細胞の増殖、分化、免疫反応など、微量で重要な役目をする
転移があっても、腎臓を摘出すべきか
このステージで今一番問題になっていることがあります。それは、肺や骨に転移があっても、腎臓の外科的摘出をすべきかどうか、です。腎臓を摘出した後、転移巣に対して免疫療法などを行うことにより、治癒したり、がんの進行が抑えられることがあること、またがんをそのままにしていた場合、将来、出血や腹痛、発熱、貧血などが発生し、生活の質が低下することなどを配慮して摘出が行われますが、欧米で腎臓を摘出した場合と摘出しない場合とを比較した臨床試験が行われました。結論は、腎臓を摘出したほうが予後がよいというものでした。
しかし、篠原さんは問題点をこう指摘します。
「症例数が少ないのと、手術した患者のほうがパフォーマンス・ステータス(PS、全身状態)が良好なことから、臨床試験に対する信頼性に疑問が投げかけられ、手術すべきかどうか、まだ意見が分かれています。ただし、臨床試験の内容を考慮すれば、パフォーマンス・ステータスがよく、転移が肺だけに限局している場合は、腎臓を摘出するのがいいと思います」
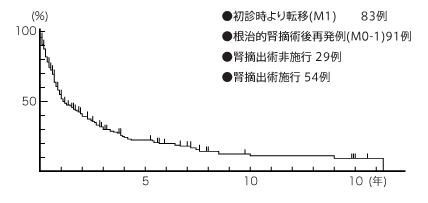
腎臓がんが転移した174例の生存率
大腸がん同様、転移巣は摘出したほうがよい

肺転移に対しては胸腔鏡で治療すると
QOLがよい
[肺転移の放射線治療]
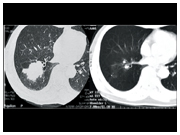
定位放射線治療で肺転移を治療した例。
40グレイの放射線をかける(左)と
23カ月後に転移がほぼ消失(右)
もう一つの問題は、転移先のがん(転移巣)に対する治療です。
欧米で、転移巣を切除した場合としない場合の比較試験が行われ、転移巣を切除したほうが予後がよいという結果が出たのです。その条件として、パフォーマンス・ステータスが良好で、手術から転移するまでの無病生存期間の長い人がよく、転移巣の数は多くても少なくても変わらない、とされています。
「特に肺転移に対しては胸 腔 鏡で切除をすると苦痛がなく、QOLが非常にいいですね」と篠原さんは言います。実際に、驚くべき例として、1991年に腎臓がんが発見され、手術で腎臓を摘出した人がいます。当時47歳という若さです。3年後肺転移が起こり、インターフェロンを投与したが、副作用で強烈な肝臓障害が起こって投与不能となりました。しかし、年齢的にあきらめきれないので、転移巣を胸腔鏡で摘出したのです。その後、放射線治療を何回か繰り返していますが、今も元気に生存中とのことです。
転移に対する治療は手術ばかりではありません。放射線治療も有効です。篠原さんはこう言います。
「骨転移に対しては放射線治療が有効です。痛みを緩和します。神経障害の改善は十分ではありません。脳転移も放射線でコントロールできることがあります。特にガンマナイフという治療が有効です。脳転移が起こると、2、3カ月で死亡することが多いのですが、放射線をかけステロイドをうまく併用すると、長期生存こそできませんが、1年ぐらい生きられます。しかもその間のQOLが非常にいいのです」
そして篠原さんは、このような緩和療法こそががん治療の鉄則だと力説します。
「一般的に緩和療法を始めるともう終わりという観念がありますが、そうではありません。症状緩和こそが命を永らえる治療なのです。症状が緩和すれば十分に寝られ、食欲が出、免疫力が上がり、治療の効果もよくなるからです。どんな治療も、患者のパフォーマンス・ステータスを落とすようなことをしてはいけないのです」
試験的治療
腎臓がんに対してミニ移植(骨髄非破壊的同種造血幹細胞移植)と呼ばれる治療も臨床研究されています。これは、他人の血液細胞を輸血し、それを生着させることによって、他人の免疫細胞にがんを殺してもらおうというものです。しかし、他人の免疫細胞はがん細胞だけでなく、正常細胞をも攻撃するので、非常に激しい副作用が現れます。
これに対して、「腎臓がんにはこんな激しい治療はすべきではない」というのが篠原さんの見解です。
腎臓がんに対する遺伝子治療の臨床試験も1998年から始まっています。手術で腎臓がんを摘出した後、免疫力を高める遺伝子をそのがん細胞に入れ、再び患者の体内に戻すという治療です。アメリカでは多数の臨床試験が行われ、日本でも東大医科学研究所や筑波大など行われていますが、まだ有効な結果が出ていないのが現状です。
同じカテゴリーの最新記事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場
- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択
- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!
- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に
- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に
- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ
- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える
- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術


