肝がんの病診連携:東葛北部肝炎・肝がん診療連携講演会 変わる肝炎、肝がんの治療。新薬の登場がブレークスルーに
肝がん治療にはさまざまな選択肢が

続いて、国立がん研究センター東病院肝胆膵内科科長の池田公史さんが「肝細胞がんに対する治療のUP date─分子標的治療薬の役割は?」と題して講演、肝がん治療の動向や、国立がん研究センター東病院の取り組みなどを紹介しました。
肝がんの治療法には、手術、局所療法(ラジオ波焼灼術)、放射線療法、肝動脈化学塞栓術、肝動注化学療法、全身化学療法(抗がん薬)があります。どの治療法を選択するかは、がんの個数、大きさ、血管への広がり、他臓器への転移、肝機能の程度(肝予備能)などを考慮して総合的に判断されます。その参考となるのがガイドラインです。
たとえば、日本肝臓学会の「肝細胞癌治療アルゴリズム2010改訂版」によると、肝機能が十分に保たれていて、腫瘍が1~3個までなら、大きながんでも手術が第1選択になります。
また、腫瘍が3個以内で、3㎝以下であれば、手術(肝切除)とともに、高周波でがん細胞を焼き切るラジオ波焼灼術も治療の選択肢に入ります。池田さんもこのラジオ波焼灼術を積極的に行っており、がんが多発したようなケースでも、良好な成績を得ているといいます。では、手術とラジオ波焼灼術のどちらがより有効なのか。これについては比較試験が行われていますが、生存期間などに有意差は認められていないということです。
また、局所治療の1つとして肝動脈化学塞栓術という方法もあります。塞栓物質で肝動脈をふさぎ、がんを兵糧攻めにするもので、手術やラジオ波焼灼術を適応できないケースが主な対象となります。
塞栓物質として一般的なのはゼラチンスポンジ(多孔性ゼラチン粒)ですが、池田さんによると、現在ビーズという新しい物質が開発中でより高い効果が期待できそうだといいます。
肝がんで初の延命効果を示したネクサバール
一方、肝がんが血管内に浸潤したり、肝臓以外に転移したりした場合は、抗がん薬による治療が行われますが、肝がんは抗がん薬が効きにくく、大きな問題となっていました。ところが3年前より、ネクサバール(*)という新しい分子標的薬が登場、突破口を切り開こうとしています。
ネクサバールは、がんの増殖にかかわる因子を阻害したり、血管の新生を邪魔したりすることでがんの増殖を抑えます。臨床効果も多くの比較試験で実証されています。たとえば、進行肝細胞がん患者さんを対象にしたSHARP試験(欧米)では、ネクサバールを投与した群はプラセボ群と比較して、生存期間とがんが増悪 するまでの期間が、有意に延長しました(図4)。
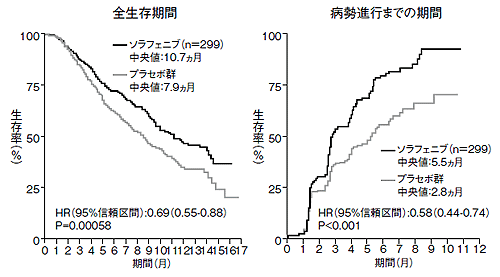 ソラフェニブは、プラセボと比べて病勢進行までの期間と全生存期間の両者において、有意な延長が示された
ソラフェニブは、プラセボと比べて病勢進行までの期間と全生存期間の両者において、有意な延長が示されたまた、アジアで実施されたAsia・Pacific試験でも、同様の結果が得られています。池田さんによると、肝細胞がんで延命効果が認められたのはネクサバールが初めてということです。
従来の抗がん薬はがんを叩き、小さくさせるものでした。これを抗腫瘍効果といいます。これに対してネクサバールは、抗腫瘍効果は乏しいものの、がんを大きくさせないようにして、生存期間を延ばします。また、飲み薬のため使いやすいという利点もあります。
ところで、肝がんに対する化学療法の1つに、高濃度の抗がん薬を直接肝動脈に注入する肝動注化学療法という方法があります。日本独自のもので世界的な標準治療として認められてはいませんが、一部の患者さんには劇的に効くことがあります。
最近、よく議論になるのが、ネクサバールとこの肝動注化学療法の比較です。これについて池田さんは、ネクサバールを堅実なアベレージヒッター、肝動注化学療法を、時に大きなホームランを打つ一発屋にたとえ、「2つの治療法の住み分けを明らかにし、うまく使い分けていくことが望ましい」と持論を述べました。
*ネクサバール=一般名ソラフェニブ
「チームネクサバール」で副作用をマネージメント
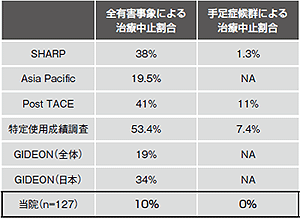
ネクサバールはまず進行肝細胞がんで、延命効果が立証されましたが、その後、手術あるいはラジオ波焼灼術後の補助療法、肝動脈化学塞栓術との併用、さらに他の分子標的薬との併用などの検討が進められており、今後、応用範囲はさらに広がっていくものと期待されています。
ただ、注意しなければならないのは副作用です。ネクサバールには、従来の抗がん薬のような、白血球や血小板の減少といった副作用はほとんどありません。しかし、分子標的薬に特有な、手足に炎症や痛みが集中的に起こる手足症候群といった皮膚症状がみられます。これらは、患者さんにとっては想像以上につらく、治療が中断するケースも少なくないといいます。
そこで池田さんは、こうしたネクサバールの副作用をマネージメントする「チームネクサバール」を院内に組織し、対応に当たっています。メンバーは、医師、薬剤師、看護師など総勢25名。異なる職種のスタッフが連携し、最小限の副作用での治療の継続、それによる最大の治療効果を得ることを目指しています。
先に触れたSHARP試験などこれまでの臨床試験をみると、副作用による治療の中止割合は19.0~53.4%とかなり高いのですが、同院では10%、手足症候群による中止はゼロと効果を上げています(図5)。池田さんは「知識を共有し、副作用を適切に管理する上でチームネクサバールはとても有用。他の施設でもぜひ参考にしてほしい」と述べ、講演を終えました。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


