東大病院「チームネクサバール」の取組み 医師、薬剤師、看護師が連携して抗がん剤の副作用をマネジメント
なぜ東大病院ではできないのか
このネクサバールが、「切除不能な肝がん患者」の治療薬として、わが国で承認されたのは09年5月です。
「進行性肝がんに対する有効性が証明された初めての抗がん剤。しかも内服薬です。スタッフの期待はとても大きかったのですが、実際に使ってみると、思わぬ事態が起こりました」
こう振り返るのは、当時、東大肝胆膵外科に在籍し、チームネクサバール東大の仕掛け人となった井上陽介さん(現がん研有明病院)です。
"思わぬ事態"とは、ネクサバールによる副作用(手足症候群、高血圧、下痢など)です。なかでも手足症候群は、手のひらや足の裏にチクチク感、ヒリヒリ感といった違和感、ほてり感、赤くはれる、角質が厚くなるなどの症状がみられ、もっとも頻度の高い副作用です。放置すると、痛んだり水ぶくれができ、手を使った日常的な活動や歩行が困難になることもあります。手足症候群自体は、国内の臨床試験でも半数近くの患者さんに起こり、既知の副作用でした。しかし、実際の現場では予防策としてのスキンケア、内服などに関する情報が十分浸透していなかったため、休薬や中断に追い込まれる患者さんが相次いだのです。そして、スタッフの間に「ネクサバールは使えない」という声が広がっていったといいます。

「このままでは、画期的な抗がん剤が消えてしまいかねない」
危惧した井上さんは、関係する診療科の医師やコ・メディカルに呼びかけ、ネクサバールの適正使用を検討するワーキング・グループを立ち上げます。
当時、すでに国立がん研究センター東病院やがん研有明病院などでは、ネクサバールの適正使用を推進するためチームが作られ、副作用をうまくコントロールしながら同剤を安定的に使用する体制が整っていました。
「そうした施設の医師に話を聞くと、『うちでは、皮膚の副作用のためネクサバールを中止するようなケース���ない』とのこと。なぜそれが東大病院ではできないのか。ちょっと悔しかったですね」と井上さん。
薬剤師、看護師からも懸念の声が
井上さんとは少し違う視点から、ネクサバールの使い方について懸念を抱いていたのが、東大病院薬剤部の黒田誠一郎さん(がん専門薬剤師)です。
黒田さんによると、院内ではすでに数種類の分子標的薬が用いられ、マニュアルも作られていました。しかしすべて注射薬で、処方する場所が、病棟と外来がん化学療法室に限られます。したがって、たとえ未知の副作用が起こったとしても、関係する部門同士がしっかり連携すれば、迅速に対応できます。ところが、ネクサバールは内服薬です。最初は入院で薬を服用してもらいますが、時期がくれば患者さんは退院し、外来、自宅療養へと移ります。
「もし、こうした場で副作用が頻発することになれば、せっかくの薬の評価が下がります。それを防ぐためにも、誰もが使える標準的なマニュアルを作り、ネクサバールの適正な使い方を院内はもとより、かかりつけ医や保険薬局にも広め、患者さんをフォローしていく必要があると痛感していました」(黒田さん)
一方、現場で患者さんと1番身近に接触する看護師サイドでも、苦労が続いていました。同院看護部の片岡ヤス子さんは「薬に副作用はつきもの。ネクサバールについても事前に情報を得ていましたが、手足症候群で日常生活に支障をきたすなど、予測を超えたケースもあり、最初はとても戸惑った」と話します。
チームネクサバール東大が動き出す
こうしたスタッフが結集して、院内キャンサーボード(*)の下部組織と位置づけられたワーキング・グループが動き出します。メンバーは15名。消化器内科、循環器内科、肝胆膵外科、泌尿器科、皮膚科、腎臓・内分泌科の医師、薬剤師、看護師、医療ソーシャルワーカーなどが参加しました。
グループがまず目指したのはマニュアル作りです。全員出席の勉強会を重ね、ネクサバールの特徴、効果、副作用、そのメカニズムなど基礎知識を理解し、共有する。その上で、医師、薬剤師、看護師などの部門ごとに、副作用への対処法、予防策、患者指導などのエビデンス(科学的根拠)、東大病院での使用経験をベースにまとめ、全員で討議するというステップを繰り返したといいます。
その過程で大きな役割を果たしたのが、メンバーの1人である皮膚科の鑑慎司さん(現関東中央病院皮膚科部長)です。前述したように、ネクサバールで高頻度にみられる副作用は、手足症候群などの皮膚症状です。しかし、あらかじめ保湿剤やステロイド薬を手足に塗ることで、皮膚反応は軽減します。また、仮に皮膚症状が出ても、多くは軽度で、塗り薬や内服薬によって回復し、ネクサバールを続けることが可能です。
「それまで、ステロイド薬の予防投与などについては、医師によってバラツキがありました。しかし、文献や実例を示してていねいに説明していく中で理解が進み、院内全体のコンセンサスとなりました」と鑑さん。このように、医師や薬剤師、看護師などチームで対応することで、手足症候群などの副作用を軽減し、患者さんも無理なくネクサバールを続けることができるようになったのです。
*キャンサーボード=外科や内科、放射線科など、多数の診療科にまたがって行われる医師による症例検討会
マニュアルが完成、チーム医療も進む
| 重症度 | 症状 | 対処法 |
| 初期 症状 | 他覚的な皮膚の変化を伴わない、自覚的な皮膚の違和感(チクチク感など) | ・予防対策の見直し・徹底 ・原因を追及し、圧力や刺激の除去・軽減策の実施 ・本剤の減量は不要(治療続行可能) |
| グレード 1 | 疼痛を伴わないわずかな皮膚の変化または皮膚炎(例:紅斑、浮腫、角質増殖症) | ・予防策の見直し、患部への保湿クリームの塗布 ・本剤の減量は不要(治療続行可能) |
| グレード 2 | 疼痛を伴う皮膚の変化(例:角質剥離、水疱、出血、浮腫、角質増殖症);身の回り以外の日常生活動作の制限 | 1)本剤の1段階減量:400mgを1日1回 2)対症療法の実施と経過観察(1週間程度) ・疼痛が強い場合:消炎鎮痛薬(内服) ・紅斑に対してはステロイド外用療法が行われる場合がある ・4mmまでの小水疱:破疱せず。保存的に治療する 3)本剤通常量への復帰:症状がグレード1以下に軽快後、患者の状態に応じ段階的に増量。 |
| グレード 3 | 疼痛を伴う高度の皮膚の変化(例:角層剥離、水疱、出血、浮腫、角質増殖症);身の回りの日常生活動作の制限 | 1)本剤の休薬 2)対処療法の実施と経過観察(疼痛は多くの場合3日~1週間程度で改善し始める) ・ステロイド外用療法(very strong)の開始:皮膚科医との連携で実施。適宜ステロイド全身療法(内服)も考慮 ・大きな水疱・膿疱は内容を吸引する ・びらん・亀裂にはグリセリン系あるいはワセリン系保湿剤を塗布する(尿素系等は刺激があるので塗布しない) 3)本剤の再開:症状がグレード1以下に軽快後、患者の状況に応じ、1段階減量にて(400mgを1日1回)投与を再開 4)減量投与下で経過観察(1カ月程度) 5)本剤通常量への復帰:患者の状況に応じ段階的に増量 ・グレード2までしか軽快しない場合:基本的にグレード1以下と同じ対応だが、患者の状況をみて検討 |
山崎直也, 他:皮膚病診療:32(8):836-840. 2010
スタートして約5カ月でマニュアル(チームネクサバールマニュアル)は完成します。全体の構成は、ネクサバールの説明から始まり、適応、対象患者、投与方法と続き、ここでは手足症候群が発症した場合の対処法や休薬基準がわかりやすく書かれています(図2)。さらに、投与時の準備として、ネクサバールを入院で服用する際の段取りがフローチャートで示され(図3)、その後に、医師、薬剤師、看護師の役割が詳細に記載されています。
マニュアルの特徴は、ネクサバールの使い方のノウハウをコンパクトに詰め込んでいること。淺岡さんは「肝がん治療に携わる医療関係者なら誰でも利用できる標準的なものを目指しました。ぜひ参考にしてほしい」と訴えます。
ところで、これまで東大病院のワーキング・グループの多くはマニュアルができると解散するのが普通でした。しかし、チームネクサバールは、その後も定期的に症例検討会を開催し、医師同士や薬剤師、看護師との連携を深めています。「これからのがん治療には、異なる視点を持つスタッフが揃うチーム医療が欠かせない。このチームネクサバールが、診療科、部門間の壁を越える1つのモデルになればいい」と淺岡さんは話しています。
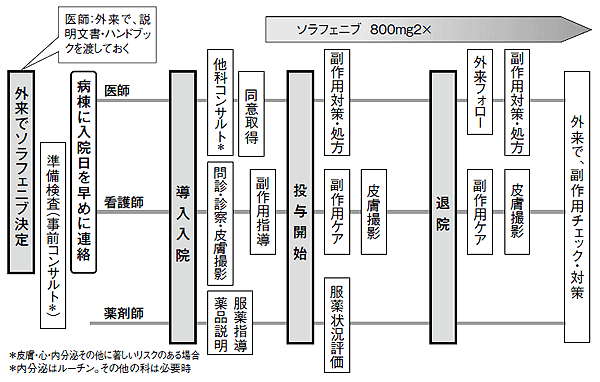
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


