あきらめないで!! 治療選択肢も多い 肝がん丸わかり完全図解
Q 肝がんの種類は?
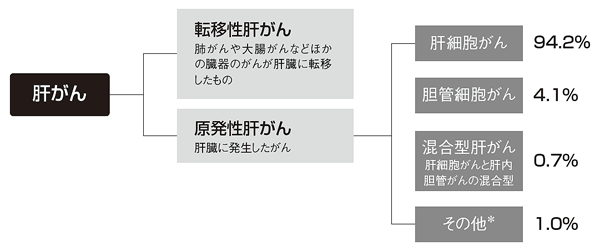
肝がんは狭い意味では原発性肝がんを指す。原発性肝がんには、肝細胞から発生する肝細胞がん、肝臓内の微細な胆管から発生する胆管細胞がんなどがあるが、ほとんどを肝細胞がんが占めている。
Q 肝がんではどんな検査をするの?
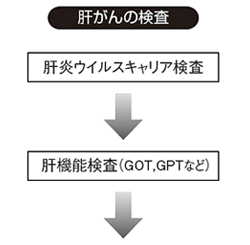
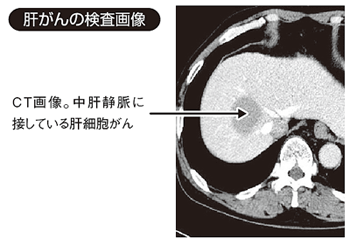
| 腫瘍マーカー | がんが発生すると血液中に特異的に増える物質。血液検査でこれらの物質を調べる。肝がん特有の腫瘍マーカーにはアルファ・フェトプロテイン、PIVKA-2などがある |
| 超音波検査(エコー) | 超音波を体に当て、その反響を利用して肝臓の様子やがんの有無、形状などを調べる |
| CT検査 | X線撮影したデータをコンピュータが分析して、断面の状態に画像化し、がんの有無など体内の様子を調べる。血管に造影剤を注入し、肝臓のくわしい血流の状態を調べる造影CTもある |
| MRI検査 | 磁気の共鳴を利用して体内の状態をさまざまな角度から画像化し、がんの有無などを調べる。血管に造影剤を注入し、肝臓のくわしい血流の状態を調べる造影MRIもある |
まず肝炎ウイルスへの感染を検査で確かめる。肝機能検査と組み合わせることで精度が高まる。肝がんの確定診断に重要なのは腫瘍マーカーや超音波検査で、微小ながんを見分けるなら、造影CTも定期的に(2年に1度程度)受けるとよい。
Q 肝がんはどうやって増殖・転移するの?
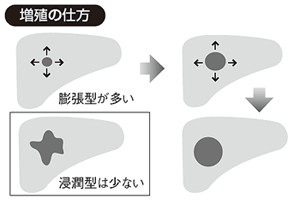
肝がんは、周囲に膜を作ってボールが膨らむように増殖する膨張型が多い。このタイプは周囲の正常組織にはなかなか食い込まず、離れた臓器にも転移しにくい。逆にモザイク状に増殖する浸潤型は少ない。これが肝がんの大きな特徴だ。
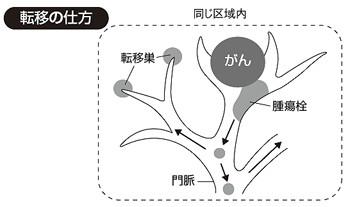
肝がんはまず肝臓の別の場所に転移することが多い。しかも、脈管侵襲(血管や胆管への広がり)が多く、ほとんどが門脈を伝って同じ系統(区域)内に転移する。脈管侵襲を起こすと予後が悪い。ごく一部が肺や骨に転移する。
Q 肝がんの進行度は?
| がんの進行度 (ステージ) | ★肝がんの状態 | リンパ節転移 | 離れた臓器 への転移 | |
| 1 | T1 | なし | なし | |
| 2 | T2 | なし | なし | |
| 3 | T3 | なし | なし | |
| 4A | T4 | なし | なし | |
| T1~T4 | あり | なし | ||
| 4B | T1~T4 | - | あり |
★がんの大きさ、数、肝臓内の血管への広がりの判定基準
T1 大きさ2cm以下、数1個、肝臓内の血管に広がっていない
T2 T1のうち、2つが当てはまる
T3 T1のうち、1つが当てはまる
T4 T1のうち、どれも当てはまらない
| 検査項目 | A | B | C |
| 腹 水 | なし | 治療効果あり | 治療効果少ない |
| 血清ビリルビン値(mg/dl) | 2.0未満 | 2.0以上3.0以下 | 3.0超 |
| 血清アルブミン値(g/dl) | 3.5超 | 3.0以上3.5以下 | 3.0未満 |
| ICGR15(%) | 15未満 | 15以上40以下 | 40超 |
| プロトロンビン活性値(%) | 80超 | 50以上80以下 | 50未満 |
*検査項目のうち、2項目以上該当し、かつ障害度の高い分類をとる
肝がんの進行度(病期)は低い順に1~4期の4段階に分けられ、治療法を決める目安や予後予測に使われる。がんの大きさや数、ほかの臓器への転移などが基準になる。また、治療法を決めるさいには肝機能のよしあしを測る肝障害度も重要で、肝機能の高い順にA、B、Cの3段階に分類される。とくに、古い血液の分解能を示すビリルビン値、たんぱく質の合成能を示すアルブミン値が重視される。
Q 肝がんの主な治療法は?
| 手 術 | 肝機能がよく、がんの数が少ない場合に第1選択となる。積極的な治療ができないときに肝移植手術を行う場合も |
| 局所療法 | 肝がんに皮膚から針を刺し、その針を通じて高周波(ラジオ波やマイクロ波)を発生させたり、エタノールを注入したりして、 がんを死滅させる治療法 |
| 塞栓療法 | 肝がんが肝動脈から栄養を取り入れる特性を利用。肝機能が低下している場合に行われる。肝動脈塞栓療法、肝動 脈化学塞栓療法(抗がん剤を使う)がある |
| 化学療法 | 経口剤による全身化学療法もあるが、肝動脈から抗がん剤を直接注入する効果の高い動注化学療法が主流。最近 は分子標的治療も |
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


