肝機能をよりよく維持することは、がんと闘う大きな武器 知っておきたい、小さく、確実に取る肝がん「系統的切除術」
門脈の支配域という系統に沿って、切除範囲を決定
最近、このように領域ごとに切除する方法は、「系統的切除」とも呼ばれます。ヒーリー&シュロイの分類でもクイノーの分類でも、各区域はある系統にしたがって分けられているためです。
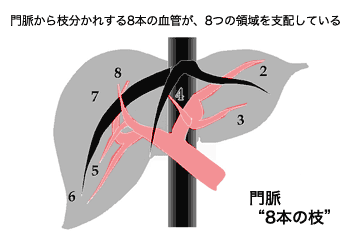
その系統とは「門脈の系統」です。先にお話ししたように、肝臓の左右を分けているのは門脈、肝動脈などの大きな血管ですが、肝細胞がんは門脈に沿って発生し、門脈の血流に乗って転移すると考えられています。ですから、がんのできた場所から門脈が枝分かれし、血流が向かう領域、つまり、門脈の支配域を「系統」ととらえ、その領域を丸ごと切除するのです。目に見えるがんがなくても、微細ながんが潜んでいる可能性が高いためです。
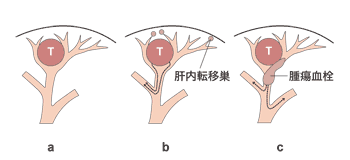
系統という言葉はちょっとわかりにくいですが、バスの路線が系統と呼ばれていることを考えると、何となくおわかりいただけるのではないでしょうか。
実をいうと、日本以外の国では、このように系統をたぐるこまごました手術より、肝移植が選ばれる傾向にあります。肝細胞がんが発生する母体そのものを取ってしまえば、再発の可能性が低く、手っ取り早く完治が目指せる、というわけです。
しかし、日本ではドナーが少なく生体肝移植が中心など、移植���ハードルが高いうえ、移植後の免疫反応など、副作用が少なくないことから、系統的切除が非常に進歩しました。
「領域ごと切る」切除方法はがんだけでなく、いわばまわりも一緒に大きめにとる切除方法ですが、切る体積が大きければ、体へのダメージは大きくなります。「系統的切除」は再発しやすい領域を必要最小限切除し、再発リスクを下げながら、できるだけ肝機能を温存するための方法でもあります。事実、系統的切除の有用性は今日、国際的にも認められ、証明するデータも揃ってきています。
肝臓の状態のよしあしが、手術内容を決める大きな条件
では、実際にはどんな症状や体調状態のとき、どんな区域切除(=系統的切除)が行われるのでしょうか。
肝臓がんでは、治療法の決め方もほかの多くのがんとは違っています。多くのがんで重視されるのはがんの大きさと深さ(深達度)、リンパ節転移の有無ですが、肝臓がん、とくに原発性の肝細胞がんでは、肝臓の状態のよしあしが重視されます。
というのは、原発性肝細胞がんのほとんどはC型またはB型肝炎を背景に発生するので、肝臓そのものの状態がよくないことが少なくないのです。いくらがんが小さくても、肝臓の状態が極端に悪い場合、区域切除をしても肝機能が戻らず、肝不全を起こすことがあります。術後に肝不全を起こすと、助かることが非常にむずかしいので、「切っても、残った肝臓でやっていけるかどうか」は、たいへん重要なポイントです。
もちろん、状態がいい場合は、大きく切除しても肝臓が再生しますから、がんのサイズが大きくても切除が行われ、大きめに切ることができます。
現在、最も標準的に行われている治療法を記した『肝癌診療ガイドライン』には、治療法をどう選ぶか図解した「肝細胞癌治療アルゴリズム」が掲載されていますが、これを見ても、肝細胞がんの治療法は「肝障害度」、「腫瘍数」、「腫瘍径(がんの大きさ)」の3つの条件で決めるようになっています。
ちなみに、ガイドラインで切除が標準治療とされているのは、
(1)肝障害度が悪くなく(AまたはB)、腫瘍数が1つ
(2)肝障害度が悪くなく(AまたはB)、腫瘍が2~3個、腫瘍の大きさが3センチメートル以内
(3)肝障害度が悪くなく(AまたはB)、腫瘍数が2~3個、腫瘍の大きさが3センチメートル以上
という3つの場合です。
切る範囲を決定するのは、腹水と肝機能を表す数値
さて、肝障害度と腫瘍の数・大きさから「切除」が選択されると、次は「どこをどれだけ切るか」ということになります。これも今日では基準があり、多くの医療施設がこの基準によって切除範囲を決定しています。
その基準とは、肝臓がん外科治療の世界的権威であり、系統的切除のパイオニアでもある幕内雅敏(現・日本赤十字医療センター院長)さんが作成したもので、「幕内基準」と呼ばれています。
「幕内基準」では、肝臓の状態を示す3つの材料から、切除する領域の広さを導き出します。3つの材料とは「腹水の有無」、黄疸の状態を調べる「血清総ビリルビン値(※1)」、肝機能を調べる「インドシアニン・グリーン試験15分値(ICG15分値)(※2)」の3つ。たとえば腹水がなく、血清総ビリルビン値が1.0ミリグラム/デシリットル以下、ICG15分値が10パーセント未満なら、右葉(肝臓全体の3分の2)やクイノー分類の3区域分が切除できる――というように判断します。
腹水があったら手術は行いませんし、腹水がなくても血清ビリルビン値が2.0ミリグラム/デシリットルを超えていたら、これも手術は行いません。要は、「この条件でこれだけ切除しても、残った肝臓でやっていけるか」というのを、図式化したものなのです。
実際にはさまざまな条件、たとえば、どの位置にがんがあるかなどによっても、切除範囲は変わってきます。極端な例をあげると、がんの大きさが小さく数が1つでも、右葉を支配する門脈の根元にあれば、門脈の支配域は右葉全体ということになりますから、右葉を全部取る術式を考慮しなければなりません。逆に、区域6の端に小さいがんができた場合、区域全体を切るか、そこだけ部分切除するかどうかは大きな検討事項になります。
※1ビリルビン=肝障害や赤血球がこわれる溶血が起こると値が高くなる
※2インドシアニン・グリーン(ICG)試験=インドシアニングリーンという暗緑色の色素を腕の静脈に注射し、一定時間後に採血したときに色素がどれだけ残っている かを調べることによって、色素が肝臓でどれだけ処理されたかを調べる
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


