肝臓にやさしく身体にも優しい、反復繰り返し治療できる点が注目される 新剤形抗がん剤の登場で進化する肝がんのIVR治療
新旧抗がん剤の比較検討
従来の肝動注化学療法で用いられていたファルモルビシン(一般名エピルビシン)とアイエーコールとの開発時でのデータ比較では、ファルモルビシンの奏効率が15パーセント程度に対し、アイエーコールは約34パーセントに向上している。
実際にアイエーコールの治療効果はどんなものだろう。
淀野さんたちは、2004年7月から2006年12月までにこの治療を受け、さらに追跡調査が完結した肝臓がん患者202名を対象に、従来よく使われているファルモルビシンとリピオドールの混和剤を投与した患者106名と、アイエーコールとリピオドールの混和剤を投与した患者96名の治療後の予後を比較検討している。
ファルモルビシンを投与した患者の1年、2年、3年後の生存率はそれぞれ83パーセント、58パーセント、37パーセント。それに対してアイエーコールを投与した患者のそれは89パーセント、72パーセント、62パーセント。治療後3年を経過した段階で、すでに生存率で26パーセントもの差異が生じている。この結果からも、淀野さんは、アイエーコールを第1選択薬にすべきだと考えている。
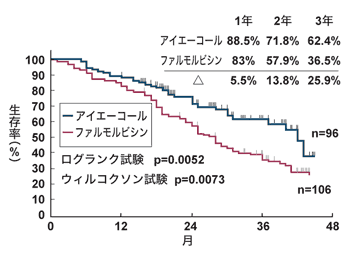
アイエーコールとファルモルビシンの生存率で差が出た
抗がん剤の併用でがんに対する感度が高まった
もっともがんが進んでくると、治療内容も変わってくる。3期以降のかなり進行した肝臓がんでは、それ以上肝機能を低下させないため塞栓物質を使わず抗がん剤のみを動脈に注入する肝動注化学療法が治療の中心となる。淀野さんによると、日本ではこの治療が1960年代から70年代にかけて一般的な治療法として、肝臓がんに適用されていたが、その後あまり用いられなくなってしまった時期がある。原因は予想以上に肝障害が強かったことにあったという。
「当時は肝動注化学療法に大量の5-FU(一般名フルオロウラシル)を用いていました。この抗がん剤は効果も高いが、肝毒性も強力です。それで治療中に肝機能障害が多く現われたため、治療そのものが行われなくなりました」(淀野さん)
しかし、その後再びこの治療法が肝臓がん治療の中核と位置づけられるようになったのは、シスプラチンの登場が幸いしているという。
「シスプラチンにはそれ自体で肝臓がんを叩く作用があることに加え、5-FUの感度を高める作用もあります。つまり、シスプラチンをを併用することで、5-FUの投与量を少量に抑えて高い効果を得ることができるようになったのです」 と、淀野さんは語る。
リザーバー設置で抗がん剤をくり返し肝臓へ
治療法はどんなものだろう。肝動注化学療法では一般的にリザーバーという小さな器具が腹壁に埋め込まれる。これは動脈に挿入されたカテーテルの窓口であり、これを使うと簡便に抗がん剤を注入でき、またくり返し投与することができる。
「シスプラチンと5-FUのレジメン(※2)を用いる場合は、抗がん剤注入にまる1日を費やします。まず最初にシスプラチンを2時間かけて点滴で注入、その後で5-FUを22時間かけて注入します。1週間にこの治療を5日続け2日休んで1クールとし、約1カ月で4クールをこなして治療は終了します」(淀野さん)
と、いうから現実の治療はなかなか大変だ。これらのカテーテルを用いたIVR治療にもやはりリスクは潜んでいる。
「抗がん剤の副作用により骨髄抑制や肝萎縮が起こることもあります。非常にまれですが、留置カテーテルが鎖骨下動脈から挿入されている場合、血栓が脳に飛んで脳梗塞が生じる危険もあります。治療を受けるなら、そうしたリスクについても知っておく必要があるでしょう」
と、淀野さんは警告する。
もっともそうしたリスクを勘案しても、この治療法が全身化学療法に比べると、効果的で、しかも体に優しい治療法であり、だからこそ、再発しても何度でも行えるわけだ。また最近では、この治療法で腫瘍を小さくした後で、肝移植や、ラジオ波焼灼療法が行われることも少なくないという。
淀野さんによれば、今後、分子標的薬のネクサバール(一般名ソラフェニブ)との併用で、この治療の効果がさらにに向上する可能性もあるという。難治性の肝臓がん患者にとっては、今後のIVR治療の進歩にさらに注目する必要がありそうだ。
※2 レジメン=薬の種類や量、使用方法などを示す治療実施計画書
(構成/常蔭純一)
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


