低侵襲、負担の少ないラジオ波焼灼療法。さらに効果を高めるために併用も 次々に進化する肝臓がんの内科的療法
制限をあまり受けない「肝動脈塞栓療法」
肝臓がんが進行性で、肝臓全体に広がっている場合などには、肝動脈塞栓療法が行われる。これは、がん細胞へ栄養を送り込んでいる肝動脈を塞ぎ、がん細胞を兵糧攻めすることで、がん細胞を死滅させる治療法だ。
具体的には、鎮静・鎮痛剤を筋肉注射した太股の付け根の大腿動脈(患者によっては上腕動脈の場合もあり)からカテーテルを挿し込み、先端を肝動脈へ進める。そして画像上で、がん細胞に栄養を送っている肝動脈に届いたことを確認した上で、このカテーテルを通じて、1ミリ角大に切断したゼラチン・スポンジなどを注入して肝動脈を詰まらせ、血液を遮断。その結果、がん細胞を死滅させる。なお、治療効果を高めるために、抗がん剤と肝臓がんに取り込まれやすい造影剤「リピオドール」を懸濁して、事前に投与する場合が多い。
この療法のメリットとしては、がんが肝臓の内部にとどまっている限りは、解剖学的条件による制限をあまり受けない点が挙げられる。さらに、肝機能の制限も比較的緩いため、黄疸・腹水などがなければ、ほぼ施行可能であることに加え、退院後は1~2週間ほどで社会復帰が可能でもある。ただし、完治の確率はあまり高くないため、繰り返し治療を行う必要があるケースが多くなるという欠点がある。
今ではほとんど行われることは無くなっているが、かつて肝臓がん治療の主流だったのが工藤さんも触れた「エタノール注入療法」だ。これは、エタノールの脱水作用とタンパク質の凝固作用を利用して、がん細胞を壊死させる治療法で、超音波診断装置などでがん細胞の位置を確認しながら、肝細胞がんに細い針を穿刺する。そして99パーセントのエタノール(純アルコール)を肝がんの大きさに応じて2~3ミリリットルから10ミリリットル程度注入することで、がん組織を破壊する。一般的には、3センチ以下で3個以内の肝細胞がんで、特に手術ができないような肝機能不良例に適しているとされている。
予後の改善にも成功
以上のように、現在は、ラジオ波焼灼療法が最も効果がある内科的療法となっている。
だが、患者の肝炎ウイルスを駆除しない限り、治療によって死滅したがん以外の場所に、何度でも新たに再発する可能性がある。こうしたことから工藤さんの研究室では、現��、発がん抑制・再発抑制の目的で肝臓がんを根治後、患者さんに対するインターフェロンの長期・間欠・少量投与にも積極的に取り組んでいる。
同教室では現在、世界に先駆けて術後の再発抑制・予後改善を目的とする、インターフェロンを長期にわたって少量投与し続ける維持療法「メンテナンスインターフェロンセラピー」を実施している。
これは、長期持続型の「ペグインターフェロン」の投与を、1~2週間に1回、終了期日を決めずに投与し続ける治療法であり、同研究室では、一般に80~90パーセントあるといわれている複数回の5年再発率を20パーセントまで低減させるなど、患者の予後の改善に成功している。また、肝動脈塞栓療法とラジオ波焼灼療法の併用療法など、より効果的な根治的方法も開発中である。
さらに診断においても、超音波造影や造影下ラジオ波焼灼療法を開発し実施しているほか、慢性肝炎、肝硬変及び局所根治後の肝臓がんに対しても抗炎症治療、インターフェロン少量・長期維持療法などによる発がん制御、再発制御の研究などにも積極的に取り組んでいる。
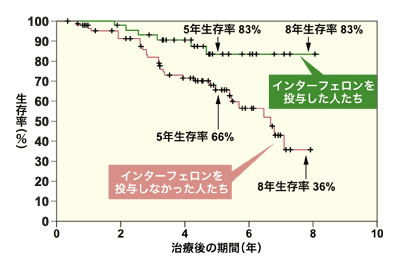
[ラジオ波治療後累積生存率]
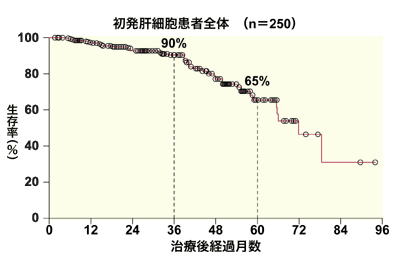
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


