『肝癌診療ガイドライン』をわかりやすく解説する 肝臓がん治療で世界のトップに立つ日本~さらに高い治療成績が期待されている
肝機能が良好な単発がんは手術が基本
肝臓の働きがある程度以上維持されている場合(AとBのレベル)は、がんの進展度によって治療法が選択されます。
がんの大きさに関係なく単発か、3センチ以下のがんが3個以内であれば、手術かラジオ波などの経皮的局所療法の適応になります。どちらも、局所のがんを治療する、つまり局所療法であるという点は同じです。
ここで気になるのは、その優劣です。ラジオ波など経皮的局所療法は、手術に比べて体への負担が少ないのが利点といわれますが、がんに対する効果という点ではどうなのでしょうか。
今村さんによると、「どちらが優れているか、科学的な比較試験が十分に行われていないので、結論は出ていないのが現状」だそうです。ただ、ラジオ波焼灼療法などの経皮的治療法は、がんが大きくなるほど成績が悪くなることがわかっています。
3センチぐらいまでの大きさならば、他の部位に別のがんができやすいという肝細胞がんの特徴を考えれば、局所の根治性を100パーセント目指すよりも、そこそこの治療成績ではあるが侵襲の少ない治療を選んでおいても最終的な治療成績(生存率)は変わらないだろうというのが、ラジオ波を施行している医師たちの主張です。しかし、と今村さんは言います。
「どの大きさまでのがんがラジオ波で治してもいいのかが、よく議論されていますが、この議論で抜け落ちているのが、腫瘤の存在場所です。たとえば胆のうのそば、肝内の太い門脈の枝のそば、肝の表面にあり、腸管と接している場所に存在しているような場合は、ラジオ波で治療するとこれらを一緒に焼いてしまう危険があり、一般的には標準治療である手術のほうがはるかに安全で確実と考えるのが妥当です。
その意味では一律に何センチ以下はラジオ波でということはできません。ではラジオ波で焼いてだめだったら手術という考えもありますが、ラジオ波後の手術は技術的に困難になります。またラジオ波にうまく反応しないというような腫瘤は嫌らしい増殖をすることがあるので、そう言う意味でも根治的な治療ができないことが多いので、勧められません」(今村さん)
そこであらためてガイドラインをみると、「単発のがんは大きさに関係なく手術による切除が標準で、肝臓の機能が少し低下(Bクラス)していて2センチ以下ならば、経皮的局所療法も選択できる」となっています。つまり、単発の場合は手術による切除が基本なのです。
これに対して、がんの数が2個から3個になると、手術と経皮的局所療法がより近い選択肢になっています。この違いは、どこにあるのでしょうか。
今村さんは、「がんが2個以上ある場合は、土壌としての肝臓の発がん性が高まっており、がんをとってもまた発生してくる可能性が高い。しかし、1個だけの場合はまだあまりがん発生のポテンシャルが高くないので、完全にとれば治る、あるいは長く発生してこない可能性が高い。だから、単発の場合は本来の治療法である手術で確実に摘出しましょう、という意味です」と、説明しています。
実際に、手術では多発性の肝臓がんのほうが再発が多いことがわかっているそうです。もっとも、こうした考え方は国の状態によっても異なり、スペインでは単発は手術ですが、複数になると肝臓の働きが良くても肝移植を行うそうです。
手術でがんを摘出しても、がんが発生しやすい肝臓の母地はそのままなので、移植をしてその危険性も抑えようという考え方です。これは、スペインが世界1脳死のドナーが多い国である、といった背景にもよるそうです。 ただし、日本は肝臓がんの手術死が0.9パーセント(肝癌研究会追跡報告調査。ちなみに東大の術死率は0.07パーセント)世界一少ないので、たとえドナーが増えても危険を伴う移植をこの段階で選択するかどうかは疑問だそうです。
効果の高い抗ウイルス薬の登場で肝臓移植が可能に
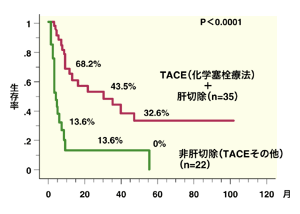
[各種治療後の生存率(%)]
| 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|
| 肝切除 | 69.2 | 53.4 | 27.7 |
| 局所療法 | 66.0 | 42.0 | 13.2 |
| 肝動脈塞栓療法 | 42.4 | 22.6 | 4.4 |
大きさに関係なくがんの数が4個以上になると、肝動脈塞栓術か動注療法の適応になります。がんが4個以上見つかるということは、肝臓全体にがんがあるという意味ですから、手術もラジオ波も局所的な治療法は適応にならないのです。
肝臓は、肝動脈と門脈という2つの大きな動脈によって養われていますが、肝動脈塞栓術はそのうち肝動脈を閉塞させて、がんを兵糧攻めにする治療法です。
4個以上の場合は、まずこの塞栓術が優先して行われます。ところが、門脈本管ががんで詰まっていると、肝動脈を詰めるとがんだけではなく肝臓まで兵糧攻めになってしまうので、この治療もできなくなります。これに対して開発されたのが、動注療法、つまり肝動脈から肝臓に直接抗がん剤などを注入する治療法です。
今村さんによると「残念ながら、ここまで進行してしまったがんに対しては、動注療法を含めて全ての治療があまり効果は高くないのですが、塞栓術ができない人や効果のない人が対象になる」そうです。肝動脈塞栓術は、最初は効果があっても繰り返し行っているうちに効果がなくなってくることがあります。こうした場合にも、次の策として動注療法を行うことがあるそうです。ただし、動注療法自体は保険適用ですが、では現在、5-FUという抗がん剤とインターフェロンを注入するので、インターフェロンは肝臓がん治療の保険適用になっていないのが現状です。
これが、肝臓がん治療の現状です。しかし、「状況によって、治療方針は変わっていくものです」と今村さん。肝臓移植も以前はB型もC型ウイルスと同じで、せっかく移植をしても、また体内のウイルスに移植した肝臓が再感染するリスクが高いので適応になっていませんでした。しかし、今ではラミブジンやエンテカビルという効果の高い抗ウイルス薬が登場。B型肝炎の場合は、移植前後にこうした薬を併用することで肝臓移植が可能になっています。
さらに、肝臓がんの切除手術後に、インターフェロン、B型肝炎ならばラミブジンやエンテカビルを使えば、再発が抑えられるのではないかという期待もあります。今のところまだ効果は証明されていませんが「手術後の治療にいい方法が出てくれば、また手術か経皮的局所療法かという問題にも、新しい見方が出てくるかもしれません」と今村さん。
現在、再発予防効果が期待されるレチノイド(ビタミンAの誘導体)の臨床試験が進んでいる最中です。「1年生存率が1~2割という極めて厳しい状況にある門脈腫瘍栓にも、今5-FUとインターフェロンの効果が期待されている」そうです。現在でも、日本は肝臓がん治療では世界のトップにありますが、こうした新しい治療法が出てくればより高い治療成績も望めるのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


