肝臓がん治療のベストチョイス 早期がんのベスト治療は手術か、ラジオ波焼灼療法か!?
患者の負担が小さいラジオ波焼灼療法
エタノール注入療法、マイクロ波焼灼療法
これらはいずれも経皮的局所療法と呼ばれ、エタノール注入療法は、腹部(または胸部)から針を刺して患部にエタノールを注入、がんを凝固させる治療法だ。90年代には早期の肝臓がんを対象に盛んに行われていた。
一方、マイクロ波焼灼療法は電極を通して流したマイクロ波により、高熱を発生させてがんを死滅させる治療法で、直径1~3センチ程度のがんを対象に用いられていた。しかし、現在ではいずれの治療法ともラジオ波焼灼療法にとって代わられているのが実情だ。
ラジオ波焼灼療法
もともとはイタリアで開発された治療法で、マイクロ波焼灼療法と同じように、患部に電極を差し込み、高熱を発生させてがんを死滅させる治療法だ。もっともラジオ波の場合はマイクロ波に比べると、温度が低く、それだけ広範囲の治療が行える利点がある。そのため90年代からは、前にあげたエタノール注入療法やマイクロ波焼灼療法にとって代わる治療法になっており、現在では肝臓がん治療の25パーセントが、この治療で占められている。
開腹しないため患者の負担が小さく、手術とは違って何度も治療を行えるのがこの治療の利点だが、高山さんは、「超音波による画像で治療を進めるため、確実さという点で100パーセントといいきれないのが弱点でしょう」という。
このラジオ波焼灼療法は、現在では手術と競合するような形で治療が広がっている。じっさいにどちらの治療がより高い効果が得られるのか。たとえば中国では100人の患者を対象に手術とラジオ波焼灼療法の比較試験が行われたが、数値的には手術が勝ったものの有意差が認められるには至っておらず、日本でも結論が出ていないのが実情だ。しかし高山さんは、手術とこの治療の適応範囲を明確化すべきだという。
「今はラジオ波による治療が単発の小さな肝臓がんに対しても行われています。しかし単発の場合であれば、確実性という点で手術に利があるでしょう。そのことを考えると、ラジオ波の適応範囲は、がんの大きさが3センチ以内、個数が2または3個の場合に限られると思います」
ちなみに高山さんによると、肝障害の度合いがAまたはBの状態で、がんの個数は3個までだが、大きさが3センチを上回っている場合は手術、または後で述べる肝動脈塞���療法がベストチョイスになるという。
再発がんには塞栓療法を
肝動脈塞栓療法
肝臓には動脈、門脈という2つの血管によって栄養や酸素が運ばれている。そのなかでがん細胞は動脈によってのみ養われている。そこで前にあげた肝障害の度合いがAまたはBの段階で、がんが3個以内だが大きさが3センチ以上の場合、また、がんの個数が4個以上の場合は大きさにかかわらず動脈を塞栓して、兵糧攻めによってがんを死滅させる肝動脈塞栓療法が行われる。
より具体的には足や腕の動脈からカテーテルを介して詰め物が注入される。その場合にはエピルビシンやシスプラチンなどの抗がん剤も同時に注入される場合が多い。この肝動脈塞栓療法に動注化学療法を加えた化学療法は、肝臓がん治療の50パーセントを占めている。もっとも肝動脈塞栓療法の場合は、あくまでも効果の中心は兵糧攻めにある。
さて、この治療の効果はどのようなものだろうか。
「塞栓療法には高い効果があり、治療を行うとがん細胞が激減します。ただ残念ながら、なかなか完全にがんを死滅させるには至らないことが多い。この治療での完全治癒率は10~20パーセントといったところでしょう。そのため、しばらくすると再発が明らかになり、再び同じ治療を行うことになる」
と、高山さんはいう。
ちなみにこの治療は手術後などにがんが再発した場合の治療としても行われる。
「塞栓療法があるから私たち外科医は意を強くして手術に臨むことができる。それだけ効果が確実な治療法といえるでしょう」と、高山さんはいう。
肝動注化学療法
詰め物を使わずに、動脈に抗がん剤だけを注入し、がん細胞を攻撃する治療法だ。一般的に肝臓がんには抗がん剤が効きにくいといわれるが、この治療法だと静脈から抗がん剤を投与した場合に比べると、より高い効果があげられ、副作用も少ないといわれるが、本当かどうかはまだ定かではではない。この治療は肝動脈塞栓療法と同じように、肝障害の度合いがAまたはBの段階で、がんの個数が4個以上の場合に適応される。
生体肝移植の実施基準「ミラノ基準」
肝移植
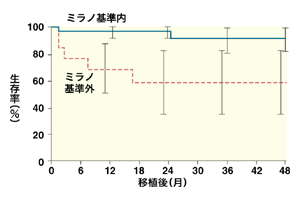
(1)単発で、5cm以下
(2)多発の場合、3cm以下、3個まで
(3)血管侵襲なし、リンパ節転移なし
その名称どおりドナー(提供者)の肝臓を移植する治療法だ。日本では脳死者のドナーがほとんど期待できない(年に3例ほど)ので、生体肝移植が中心になっている。かつては適応範囲を定めずに移植が行われ、そのために再発が多く治療効果も上がらなかったと高山さんはいう。
「がんの個数が多かったり、大きくなりすぎている場合は、門脈を介して血液中にがんが拡散していることが少なくない。がんがある程度以上、進行している場合には、移植治療後に免疫抑制剤を用いることに加えて、そうした悪条件が重なって、がんが再発することがしばしばでした」
そこで96年に、ミラノ大学でがんを対象にした肝移植を行う場合の実施基準が設けられた。これは単発がんで大きさが5センチ以内、3個までで3センチ以内を移植の適応範囲に限定するもので、「ミラノ基準」と呼ばれている。日本では、この条件を満たしている場合の生体肝移植後の生存率は80パーセントに達している。しかし、それよりもがんが進行している場合の生存率は60パーセントに低下する。
この移植治療の適応範囲は肝障害がCの段階まで進んでいるにもかかわらず、「ミラノ基準」がクリアされている場合に限られる。現実にはこうしたケースは少なく、そのために高山さんは生体肝移植は、現実のがん治療の選択肢としては限定的であるという。
緩和医療
肝障害の度合いがCの段階に達しており、がんの個数が4個以上である場合は、積極的な治療は意味を持たないという。その場合には症状を抑えながら、QОL(生活の質)の向上を目的とする緩和医療が唯一の選択肢となる。がんの個数が3個以内でも、門脈にの腫瘍栓がある場合は、やはり治療が難しく、緩和医療に治療の方向が切り替えられることが少なくないと高山さんはいう。
以上、高山さんを含めた研究班が作成したガイドラインを基に肝臓がんの治療について概括した。自らの肝障害の度合い、がんの進行状況を見極めたうえで的確な治療を選択したい。
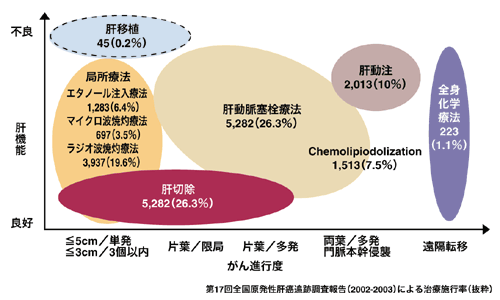
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


