渡辺亨チームが医療サポートする:肝臓がん編
肝切除術を受けたが、1年後再発。どうしたらいい?
| 川上裕輔さんの経過 | |
| 1968年 | 交通事故に遭い輸血を受ける。 |
| 1988年 | 検診から肝機能異常が発覚。「非A非B型肝炎かもしれない」といわれる。 |
| 1991年 | C型慢性肝炎の指摘。のみ薬で経過観察。 |
| 2000年 | 疲れやすさ、食欲不振、よく足がつる、などの自覚症状あり。 |
| 2001年 12月5日 | 総合病院内科を受診。「すでに肝硬変に移行している可能性あり」と指摘される。インターフェロン+リバビリン併用療法を受ける目的で超音波検査を受ける。5cmの肝臓がんが見つかる。 |
| 12月7日 | 総合病院で血管塞栓療法の説明 |
| 12月14日 | がん専門病院にセカンドオピニオンを求める |
| 2002年 1月16日 | がんセンターに転院 |
| 1月21日 | 肝切除術 |
| 1月31日 | 退院 |
| 2003年 1月末 | 検診で肝臓に2cmのがん判明 |
| 2月10日 | 再入院 |
| 2月11日 | ラジオ波焼灼療法 |
2001年12月、肝細胞がんが見つかった川上裕輔さんは、専門医たちによる検討の結果、肝切除術を推奨された。
川上さんは納得して手術を受けた。
しかし、1年後には肝臓の中に再発が見つかってしまう。
ここから、川上さんのがんとの長い闘いがはじまる。
局所コントロールとは?
2001年12月5日、川上裕輔さんはT総合病院の内科で超音波検査の結果、肝細胞がんの疑いがあり、精密検査の必要があるといわれる。翌日は引き続いて、CT、MRIによる撮影、腫瘍マーカー検査のための採血が行われた(*1肝臓がんの診断)。さらにその翌日、川上さんは検査の結果を聞くために、E医師の外来を訪れる。
「やはり肝細胞がんであることは間違いないと思います。腫瘍は5センチあり、ステージ(*2)は2期と呼ばれる段階です。さいわい単発なので、局所コントロールが可能ですから、前向きに治療に取り組んでいきましょう」
E医師はCT画像とMRI画像を並べて、腫瘍のある箇所を示した。2日前まで自分の肝臓がそれほど悪くなっているとは想像していなかった川上さんは、まだ半ば信じられない思いで医師の声を聞いている。それに、「局所コントロール」と言われてもなんのことかわからない。
「コントロールが可能というのは、治��のは難しいということなのでしょうか?」
やっとの思いでE医師に尋ねる。
「局所コントロールというのは、病変のある部分を消してそこから再発しないように治療するということです。ただし、肝臓がんは見た目の病変をなくすることができても、肝臓のほかの部位にすでに目に見えない小さな転移があったり、もともとのC型肝炎からの新たな発がんがこれからも起こったりすることから、いずれ再発する可能性が大きいのです。ですから、局所コントロールは病気の進行を遅らせる上では意味があると思いますが、それだけでがんの根治を期待することは難しいと考えられています」
川上さんはがんを告知されたばかりか、治すことが難しいと言われたのだ。すっかり意気消沈してしまった。その様子を見てE医師が話す。
「もちろん治療を受けた方の中には、その後がんが治ったのと同じくらい長く生きられる方もおられます」
その言葉に励まされて、川上さんは聞いた。
「肝臓がんの治療法はいろいろあるそうですが、どんな治療法だったら長く生きられるのでしょうか?」
「肝臓がんの治療法の中で局所コントロールがより確実にできるのは、原発巣を摘出する外科手術です。これが胃がんや肺がんなど他の臓器がんだったら、手術で原発のがんを取りきれば長期の生存に結びつくことがわかっているのですが、肝臓がんはわかりません。病変をなくしても再発するという例もたくさんあるからです。現在この病院では外科手術には対応しておらず、肝臓がんの治療法は、肝動脈塞栓術とエタノール注入療法という内科的な処置で対応しています。これらの治療法は確かに局所コントロールでは外科手術に劣るかもしれませんが、長期の生存の成績となると手術に劣らないと考えているのです。ただ、もし手術がご希望なら、Cがんセンターに外科専門の先生がおられるので、紹介状を書きます。あそこなら、ラジオ波波焼灼療法や放射線の治療も取り入れていますので、選択の幅は広がるかもしれません」
セカンドオピニオンを求める
川上さんは自分で買い込んだ医学書を読んだり、インターネットで検索しながら、自分にはどんな治療がいいのかを必死に考えた。肝臓がんのそれぞれの治療法がどんなものかについてはだいたいわかってきたが、それらを比較してどれが成績がいいのかまったく見当がつかない。
「E先生は真面目な人だとは思うけれど、『ぜひこの治療法を』という押しの強さがないから、こっちも迷ってしまうよな。こうなったら、『スパッと切りましょう』と言ってもらったほうが、従いやすいんだけど。本当にT総合病院で治療を受けていいのかなあ?」
妻の悦子さんにこんなふうに話しかけている。悦子さんも夫が肝臓がんであることを知ってたいそうショックを受けていた。そして、友人の看護師に電話で相談をするなど、いろいろ肝臓がんについて調べている。夫にこう話した。
「今の病院ではあまり選択肢がないのだったら、やっぱりCがんセンターに変えたほうがいいんじゃないの? 手術を選ぶかどうかは別にして、セカンドオピニオン(*3)という意味で、そっちのほうがいいと思うわ。選択肢が広い病院のほうがあなたに合った治療法が見つかるかもしれないでしょ? E先生に紹介状を書いてもらったら?」
単発では切除術が第1選択
こうして1週間後、川上さんはE医師が話していたCがんセンター消化器外科のH医師を受診することになったのである。40代半ばと見られるH医師は、師走の寒さがつのるシーズンだというのに、半袖の白衣を着て太い両腕をのぞかせている。
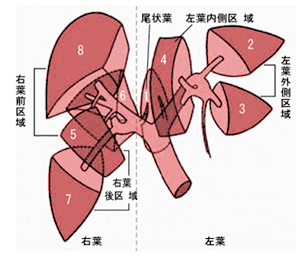
「E先生から紹介状を送っていただきましたので、うちではまだT総合病院で行われていない検査だけ受けていただきます。その結果を見て、内科、外科、放射線科の合同会議で川上さんに最も有効と思われる治療法をご提案したいと思います」
H医師から最初にこう説明され、川上さんは転院を決意、Cがんセンターへの入院を予約する。3日後にはH医師から、合同会議の結果を聞いた。
「がんは肝臓の左葉内側区域という場所にあって5センチの大きさで単発です。脈管浸襲はなく、肝予備能は良好であることがわかりました。肝切除が最も治療効果が高いと考えられますのでこれが第1選択となります。肝動脈塞栓術や体外照射の放射線治療などは、なんらかの理由で手術が困難な場合に選択されるものであり、私は川上さんには手術をお勧めします(*4肝臓がんの治療法)」
年が明けて2002年1月16日、川上さんはCがんセンターに入院する。すぐにH医師が川上さんのベッドを訪れて「明日の手術は私が執刀します」と告げた。川上さんはH医師の太い腕が、とりわけ頼もしく思えたのだった。
術後1年で再発を発見
1月21日、H医師の執刀のもとに川上さんの肝臓がんの切除手術が行われた。術後の経過は順調で、川上さんは3日目で普通食を食べることができるようになり、食欲も回復していく。退院を翌日に控えた1月30日の夜、H医師が川上さんのベッドを訪れてこう話した。
「肝臓がんは手術で原発巣を切除しても再発する可能性がまた高く、いつ顔を出すかわかりません。もぐら叩きと同じで、頭が見えたらすぐ叩く必要があります。今後3カ月に1回、定期的に検査を受けてくださいね」
手術を受けてから体が日に日に快調になっていくのを感じていた川上さんは、「本当に健康とはありがたいものだ」と思っていた。H医師のアドバイスに、小学生のようにいちいち「はい!」「はい!」と答えている。
そして、最後にH医師に礼を述べた。
「私のがんが5センチもの大きさになって見つかったのは、定期的に画像診断を受けていなかったためですね。クリニックのお医者さんからあまりきつく言われなかったので、私も病気をなめていたんです。お医者さんの言う通り定期的に検査を受けて、もらった薬を飲んでいれば、まだ肝硬変やがんになっていなかったかもしれませんね。今度のことでは検査の大切さが身にしみてわかりました。本当にありがとうございます」

CTで見た左葉内側区域(S4)の晩期相004(isii)
こうして川上さんは1月31日に退院する。以後、4月、7月、10月の月末に腫瘍マーカーと超音波検査、CTの肝臓がん検査を受け、再発は見つかっていなかった。
2003年を迎えて1月末、初めての検査に訪れると、H医師は超音波検査のとき、「あー、何か映っていますね」と話す。さらにCTとMRIで調べた結果、2センチの腫瘍が確認された。H医師から再発を告げられて川上さんは、「想像していたより、ずっと進行が早かったな」と感じた。
「今度も肝臓に単発ですから、手術は可能です。ただ、再発したからにはほかにもまだ見えない転移があって、すぐまた顔を出すかもしれません(*5再発肝臓がんに対する治療法)。治療法は、また内科の先生たちとの合同会議で方針を出しますが、ここでは体への負担が少ない経皮的局所壊死療法を選んだほうがいいと思います。とくにラジオ波焼灼療法はがんを叩く確実性が高いので、これを選ぶことになるでしょう」
H医師は再発巣への治療方針をこう説明した。
2月10日に川上さんは再入院する。翌日、ラジオ波焼灼療法が行われた。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


