渡辺亨チームが医療サポートする:肝臓がん編
C型慢性肝炎発見から10年、肝臓がんを発症
肝臓がんの8割はC型肝炎ウイルスが原因
石井浩さんのお話
*1 C型肝炎
| ウィルス性肝炎 | A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、 D型肝炎、E型肝炎、G型肝炎、 |
|---|---|
| その他の肝炎 | 劇症肝炎(含む亜急性肝炎) 自己免疫肝炎 |
C型肝炎ウイルスに感染して起こる肝炎をC型肝炎といいます。肝炎ウイルスにはC型のほかA、B、D、E、などの種類があり、このうちB、Cの2種類は肝臓がんにつながる可能性があります。肝臓がんと診断される人のうち、約1割はB型肝炎ウイルスに、そして8割はC型肝炎ウイルスに感染しているのです。
B型またはC型のウイルスに感染すると免疫システムが過剰反応を引き起こすために、肝臓に炎症が発生して肝細胞にダメージを与えます。
日本人は欧米人に比べて肝臓がんが多く、このことは長い間謎とされていました。ところが、1988年にそれまで「非A非B型肝炎」といわれていた肝炎の原因ウイルスが発見されたことから、その謎が解け始めます。このウイルスはC型肝炎ウイルスと名づけられ、それまで肝がんの原因の1つであることがわかっていたB型肝炎ウイルスよりもはるかに大きな肝臓がんの原因ウイルスであることが明らかになったのです。
これらのウイルスに感染している人をキャリア(感染者)といいますが、日本にはB型およびC型肝炎ウイルスのキャリアは、合わせて約500万人と推定されています。
日本にこのようにC型肝炎ウイルスの感染者がまん延している理由の1つは、長らく予防接種などの注射の針・筒の連続使用が行われてきたからだといわれます。一方、C型肝炎ウィルスが発見されていなかった時代には、輸血による感染もかなり多かったとみられます。また、血液そのものだけではなく、大きな手術を受けた人などに用いられた血液製剤(フィブリノーゲンなど)によってもかなり感染したと考えられています。
さらにB型・C型肝炎ウイルスは、まれに性感染することがわかっています。
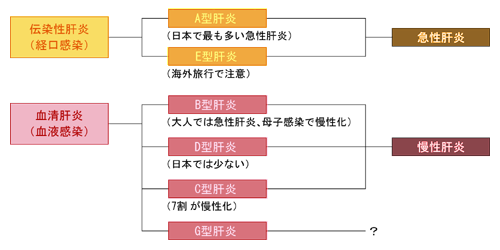
*2 肝機能の検査
肝臓は、胸郭内側の右上腹部を占め、成人で800~1200グラムと体の中で最も大きな臓器の1つで、大きな右葉とやや小さな左葉の2つの部分から構成されています。
肝臓は小腸で吸収された栄養素を合成してタンパク質を作ります。また、食べ物から吸収される有害物質を解毒する機能もあります。
この肝臓の機能を調べるためには、血液検査でGOT(AST)、GTP(ALT)、γ―GTP、lDH、総ビリルビン、アルブミンなどの検査項目を調べます。これらが、正常値と大きく外れるようなら、肝炎や脂肪肝、ときには肝臓がんなどの障害が肝臓の内部で起きていることが疑われます。
GOT
肝細胞の中にあってアミノ酸の合成を促進する酵素で、肝臓組織が損傷すると血液中の量が増加します。最近学会などでは、GOTはASTと呼ぶようになりました。参考になる正常値は0~40IU/L。
GPT
GOTと同じく肝細胞の中にありアミノ酸の合成を促進する酵素の仲間。肝細胞の変性や壊死により血液中に流れ出し急性肝炎で最も強く上昇します。最近学会などではGPTはALTと呼ぶようになりました。参考になる正常値は35IU/L。
γ―GTP
肝臓の解毒作用に関する酵素で、特にアルコールによる肝障害で高くなります。胆道系酵素とも言います。参考になる正常値は0~40IU/L。
LDH
糖質をエネルギーに変える時に働く酵素の1つで全身の臓器に含まれます。これだけでは、何の病気かの判定はできませんが、肝機能障害があると高くなります。参考になる正常値は100~220IU/L。
総ビリルビン
ビリルビンは、赤血球が分解したもので、血しょうや水に溶けない「間接ビリルビン」と、肝臓で処理を受け水に溶けるようになった「直接ビリルビン」があります。「直接ビリルビン」は、胆汁の成分になります。この2つを合わせて、総ビリルビンと呼びます。肝臓がんなどがあると高くなります。参考になる正常値は0.2~1.0mg/dl。
アルブミン(Alb)
肝臓でしか生成していないタンパク質で、総タンパクの約60パーセントを占めます。低下するということは、肝臓のタンパク質合成能力が落ちているということを意味します。参考になる正常値は、3.8~5.3g/dl。
| 1 タンパク質の合成 | 門脈から吸収されたアミノ酸から人体に必要なタンパク質を生成する。(特に血しょうタンパク、凝固因子) |
|---|---|
| 2 グリコーゲンによる糖の貯蔵 | 糖からグリコーゲンを生成して肝に貯蔵する。血糖が低下するとグリコーゲンを分解して血糖を保つ。 |
| 3 脂質の合成 | コレステロールや中性脂肪を生成する。コレステロールは細胞膜の構成に重要。中性脂肪はエネルギーになる。 |
| 4 ビリルビンの排泄 | 赤血球の寿命が尽きるとその中からヘモグロビンが放出され、非水溶性のビリルビンができる。肝臓はこれを水溶性にして胆汁中へ排泄する。 |
| 5 胆汁酸の合成と排泄 | コレステロールから胆汁酸がつくられる。胆汁酸は脂質の消化吸収に重要。同時にコレステロールを体外に排泄する唯一の方法となる。 |
| 6 アンモニアの解毒 | 身体の窒素化合物の代謝の過程で有毒なアンモニアができる。 肝臓ではこれを尿素にして尿に排泄する。 |
| 7 薬物の解毒 | 有害な薬物を無毒化する。 |
| 8 その他の代謝 | ビタミン、鉄、銅やその他の金属イオン、ホルモンの代謝を行っている。 |
*3 小柴胡湯
小柴胡湯は肝炎の人の炎症を抑える(GOT、GPTの検査値を改善する)作用を示すことがある漢方薬です。
かつて肝炎の治療には、なかなか効果的な薬がないため、小柴胡湯がよく処方されました。ところが、1996年にインターフェロンと小柴胡湯を併用したときに間質性肺炎という重篤な副作用が発生することが問題になり、小柴胡湯がやり玉にあがったのです。これは併用によって起こった事故であり、小柴胡湯自体が薬害を引き起こしたわけではありませんでした。小柴胡湯は現在も肝炎治療薬として用いられていますが、アメリカでは漢方薬のC型肝炎に対する無作為化比較試験が行われ、「効果はない」とされています。
ウイルス持続感染者は肝臓がんの高危険群
石井浩さんのお話
*4 肝炎ウイルスの検査
一般に職場の検診や地方自治体が行う住民検診では、肝炎ウイルスの感染チェックは行われません。肝細胞がダメージを受けていればGOT、GPTの値が高くなるので、これにより肝機能異常が判明したら、次にはその原因が肝炎ウイルスであるのかどうかの検査が必要です。最初はB型肝炎ウイルス表面抗原(HBsAg)とC型肝炎ウイルス抗体(HCVAb)を調べ、陽性であればさらに病状を確認する血液検査が行われます。B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの持続感染者は肝臓がんにかかりやすい候補者と心得るべきで、専門的には「肝臓がんの高危険群」といいます。
| 1 | 平成4年以前に輸血を受けた人 |
| 2 | 長期に血液透析を受けている人 |
| 3 | 輸入非加熱製剤凝固因子製剤を投与された人 |
| 4 | 3と同等のリスクを有する非加熱凝固因子製剤を投与された人 |
| 5 | フィブリノーゲン製剤 (フィブリノーゲン糊としての使用を含む)を投与された人 |
| 6 | 大きな手術を受けた人 |
| 7 | 臓器移植を受けた人 |
| 8 | 薬物乱用者、入れ墨をしている人 |
| 9 | ボディピアスをしている人 |
| 10 | 過去に健康診断などで肝機能検査の異常を指摘され、その後肝炎の検査を実施していない人など |
*5 ウイルス肝炎の治療薬
肝炎の一般治療薬としては、のみ薬として小柴胡湯のほか、ウルソ、プロヘパールなどが、また、注射薬として強力ミノファーゲンC、タチオンなどが以前から使われてきました。これらの薬の効果は肝炎の沈静化(対症療法)であり、検査値はいくぶん改善しますが、肝炎ウィルス駆除(原因治療)ではありません。近年、肝炎ウイルスに対する直接効果のある薬剤として、インターフェロン、B型肝炎ウイルスに対するラミブジン、C型肝炎ウイルスに対するリバビリンが登場し、ウイルス駆除が可能になってきています。
*6 肝炎の症状
急性肝炎では倦怠感、発熱、吐き気、黄だんなどの症状が出現し、血液検査でGOT、GPTの数値がはね上がります。A型肝炎やB型肝炎(水平感染:親から子への垂直感染以外)では時に重症化しますが一過性感染として経過し、慢性肝炎には移行しません。しかしC型肝炎は高率(6割から8割)に慢性肝炎に移行します。肝臓は「沈黙の臓器」ともいわれ、慢性肝炎から初期の肝硬変の間はほとんど症状がないので治ったと勘違いすることも少なくありません。肝硬変に移行すると、全身倦怠感、食欲不振、尿の濃染(尿の色が紅茶のように濃くなる)、吐下血、黄だんなどの症状がでることがあります。
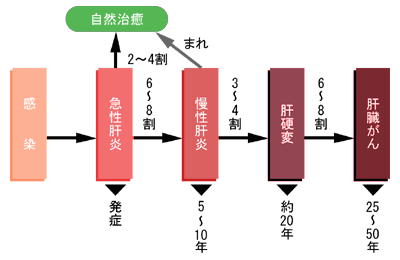
併用療法は専門医とよく相談してから
石井浩さんのお話
*7 肝硬変・肝臓がんの症状
肝硬変や肝臓がんはほとんどが無症状です。しかし、進行した肝硬変、肝臓がんでは以下のような症状がみられることがあります。自覚症状がみられた際には医師の診察を勧めます。
- ・胸郭のすぐ下右側における硬いしこり。
- ・右側上腹部の不快感。
- ・右側肩甲骨周囲の疼痛。
- ・原因不明の体重減少。
- ・黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)。
- ・異常な疲労感。
- ・悪心。
- ・食欲低下。
*8 インターフェロン+リバビリンの併用療法
インターフェロンは、ウイルスを抑える作用を持った薬です。インターフェロンには、α、β、γの3種類があり、現在使用されているのはインターフェロンαとインターフェロンβです。αは筋肉注射・皮下注射、βは静脈注射で投与されます。インターフェロンでウイルスを完全に駆除できる確率は、平均すると3割程度とされます。必ずしもウイルスが駆除できなくても、治療後肝臓の炎症が軽くなったり炎症が治まったりするケースがかなりあり、肝臓がんへの進行を抑える効果が期待できる有力な方法です。一方、リバビリンの抗ウイルス作用自体は微弱で、単独投与での効果は期待できません。ところが、C型肝炎患者に対するインターフェロンの単独投与と、インターフェロンとリバビリンの併用療法を比較した臨床試験で、明らかに後者のほうが高いウイルス抑制効果をあげられることがわかってきました。著効率が高くなる一方で、併用療法はインターフェロンの単独療法に比べ副作用も強くなるので、ウイルスの型、ウイルスの量、治療の目的(ウイルス駆除か、発がん予防か)などにより、どちらの治療を選択するかは専門医とよく相談する必要があります。
*9 超音波検査

肝臓がんの検査にも使われる超音波検査装置
超音波を使って体内組織の像を描出する装置です。体に対する負担が少なく、繰り返し行うことが可能です。最近では造影剤により肝臓がんの病態診断が試みられています。ただし、場所によっては超音波では見えづらいところもあるので、CTスキャンと組み合わせたほうがより確実な診断が可能です。
*10 日本の肝臓がん
わが国の原発性肝臓がんは、大部分(90パーセント)は肝細胞がんです。次に多いのは胆管細胞がんで、両者で95パーセントを占めます。残りの5パーセントには、小児の肝臓がんである肝細胞芽腫、成人での胆管嚢胞腺がん、カルチノイド腫瘍などごくまれな腫瘍が含まれます。肝臓がんの年間死亡者数は約3万4000人であり、わが国の男性のがんによる死亡数では、1位の胃がん、2位の肺がんに次いで多く、しかも年々増加傾向にあります。女性の発生率は男子の5分の1で、こちらはむしろ減少傾向にあります。
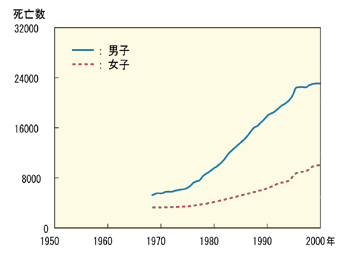
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


