進行別 がん標準治療 手術、経皮的局所療法、肝動脈塞栓が治療の3本柱
肝不全を激減させた系統的区域切除術
以前は、肝臓がんの手術といえば、ほとんどが葉単位での大きな切除でした。これを大きく変えたのが、高山さんの恩師でもある東大外科教授の幕内雅敏さんでした。それ以前から、フランスの学者によって肝臓は八つの領域に分かれていることが提唱されていたのですが、実際にどこで分かれるのかがわかりませんでした。
ところが1985年、幕内さんは、術中超音波検査を導入し、門脈から枝分かれした8本の血管が支配する八つの領域を明らかにしました。これによって初めて、八つの区域ごとに肝臓を切除することが可能になったのです。これが、系統的区域切除術です。こうして必要最小限の範囲を切除できるようになったおかげで、肝不全の発生率は激減したのです。
また、高山さんは、これまで手術が難しかった肝臓の尾状葉の手術を可能にしました。尾状葉は、ちょうど肝臓の裏側にあたる部分で、下大静脈という大きな血管に接しています。以前は、肝臓の機能が低下して左右の肝葉が切除できない人の場合、尾状葉だけを切除することができなかったのです。これを、左右の肝葉は残して尾状葉だけを切除する手術方式を考案したのです。こうした手術の工夫で現在、手術による1期の肝臓がんの5年生存率は73パーセントにのぼっています。
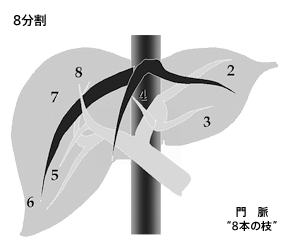
術中超音波検査の導入により、門脈から枝分かれした
8本の血管が8つの領域を支配することが明らかにされた
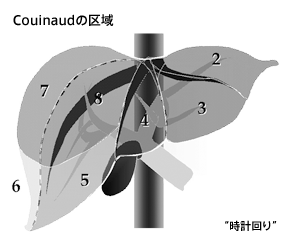
肝臓はこのような8つの区域に分かれ、
区域ごとの切除が可能になった
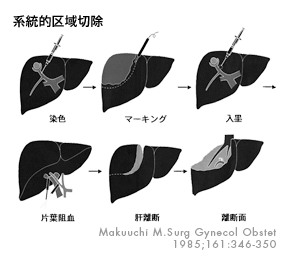
東大教授の幕内雅敏さんが編み出した系統的区域切除の方法
補助療法
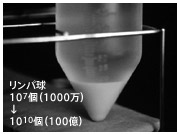
肝臓がんの免疫療法に使われるリンパ球
手術、あるいは経皮的局所療法を行えば、1期の肝臓がんの治療は終了です。とくに標準治療といえるような補助療法は、今のところありません。しかし、肝臓がんはあとでお話するように、肝硬変などをベースに起こるため、再発が多いのも特徴です。したがって、現在再発を抑えるための補助療法として、レチノイド(岐阜大)、患者さん自身のリンパ球を使ってがん細胞を殺す免疫療法(高山さん)、ウイルス性肝炎の治療薬として知られるインターフェロンという三つの治療法の研究が進行しています。「いずれも臨床試験では効果があると検証されていますが、まだ一般化はしていない」そうです。
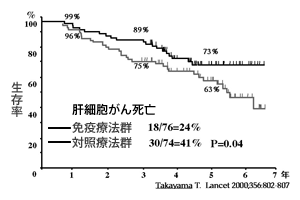
レチノイド
レチノイドとは、ビタミンAの活性の本体。最近マスコミでも話題になっているのは、そのビタミンAの誘導体で、人工的に合成された非環式レチノイドという、肝臓がんの再発予防薬のこと。
人間がビタミンAを摂取すると、体内で分解され、レチナール、レチノイン酸になる。レチナールがないと夜盲症になるが、実はレチノイン酸のほうがビタミンAの活性の本体。このレチノイン酸と同じ作用を持つ化合物を総称したものがレチノイドである。
ビタミンAの作用には、昔から先ほどの夜盲症をはじめ、皮膚や生殖機能に対して重要な役割をすることが知られているが、ここ10年ぐらいで新しく明らかになった作用の一つに、細胞が正常な細胞であることを保つ、つまり分化を誘導する作用がある。この作用が働かないと脱分化が起こり、異型細胞になる。
もう一つの作用は、正常な組織の構造を保つ作用(形態形成作用)で、これがおかしいと、細胞の構造が維持できなくなる。そしてこの二つの作用が働かなくなると、細胞はがん化するのである。
元岐阜大学医学部教授の武藤泰敏さんらのグループがこのレチノイドの作用に着目して研究を積み重ね、臨床試験を行った。レチノイドを1年間服用した群としない群では、最初の数年は再発率、生存率で差がないが、5年以上経つと服用したほうが明らかに再発率は低く、生存率は高くなり、これによって有効性が証明された。
にもかかわらず、メーカーによる製品化は断念され、この新薬の目は一旦はなくなりかけた。
ところが最近、大阪市の開業医、三浦捷一さん(65)が「未承認薬を使えないまま亡くなっている多くの患者の救済を目的」に、医師が主体になって行う医師主導型の治験に乗り出し、独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」に届け出た。レチノイドは、製薬会社から治験用薬として有償で提供を受けるという。
2期・3期の標準治療
基本は手術、手術不能なら肝動脈塞栓
1期の条件、すなわちがんの大きさ、個数、脈管侵襲のうち、一つがはずれると2期、二つがはずれると3期になります。
2期、3期の場合、治療は手術が基本です。手術が不可能な場合は、肝動脈塞栓を行うのが、現在の標準的治療です。たとえば、がんの数が4個以上あれば肝動脈塞栓の適応です。また、肝臓の機能からみれば、手術できるのは、総ビリルビン値が血液1デシリットル中に2ミリグラム未満の人までです。これを超えると、肝動脈塞栓になります。
この場合は、がんも大きいことがあるので、区域切除術だけでなく、右葉か左葉を葉単位で切除することもあります。
肝動脈塞栓は、いわゆる肝臓がんの兵糧攻めです。がんの個数に関係なく治療ができるのも特徴です。肝臓は、本来肝動脈と門脈という二つの血管から栄養や酸素を補給されています。しかし、がんは肝動脈のみから補給を受けています。そこで、肝動脈をつぶしてがんを壊死に追い込むのが肝動脈塞栓です。実際には、足のつけ根の動脈(最近では腕の動脈を使うこともある)から肝動脈まで細い管を入れ、詰め物(ゼラチンスポンジ)を注入します。このとき、抗がん剤も一緒に注入して、兵糧攻めに加えて抗がん剤による補助的効果を期待するのが一般的です。
注入する抗がん剤は、病院や医師によって異なりますが、「かつてはマイトマイシンやアドリアシン(一般名ドキソルビシン)がよく使われましたが、今はファルモルビシン(一般名エピルビシン)が中心です。人によってはブリプラチン(もしくはランダ、一般名シスプラチン)やスマンクス(一般名ジノスタチンスチマラマー)を使うこともある」といいます。効果の9割は兵糧攻めのほうにあるのです。
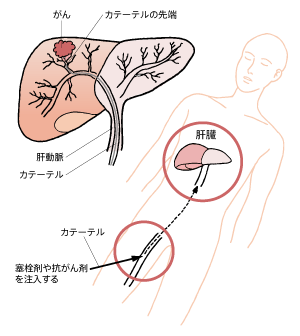
カテーテルを足の付け根にあるそ径部から血管を通じて肝臓がんの
病巣まで入れ、詰め物をして血流を断ち、がんを兵糧攻めにする
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


