ウイルス駆除率が飛躍的に向上し、治療効果は肝臓移植にも匹敵する根治療法 肝臓がんの再発を抑えるペグインターフェロン、リバビリン併用療法
従来の治療に比べ副作用が格段に軽微に
肝臓がんの再発を予防するためのペグインターフェロン+リバビリンの併用療法は、毎日リバビリンを服用すると同時に、1週間おきにペグインターフェロンを注射で投与するのを1年間(48週間)継続する。そしてウイルスが消失後、6カ月間様子を見てウイルスが再出現しなかったら駆除に成功したと判定し、再発予防効果を期待できる。
「駆除に成功するか否かは、併用療法を開始してから12週目の時点で大体予測できます。12週目でウイルスの量が減っている患者さんは、駆除に成功する可能性が大きいといえます。しかし、ウイルス量が減っていない患者さんは、駆除に成功する確率が低いと考えられます」(小俣さん)
一方、従来のインターフェロンは発熱や頭痛、関節痛、全身倦怠感等のインフルエンザ様症状や、患者によってはうつや自殺企図などの精神症状等の副作用が伴い、患者に苦痛を強いていた。
「それに比べるとペグインターフェロンとリバビリンの併用療法の副作用はかなり軽微にとどまり、より楽に治療が完遂できるようになりました」(小俣さん)
もっとも大きな副作用は、リバビリンによる貧血だ。貧血によって約3分の1の患者さんが途中で薬の減量を行うほどだ。アメリカでは貧血予防のためにエリスロポエチン(赤血球増殖因子)という薬の併用を行うのが一般的である。
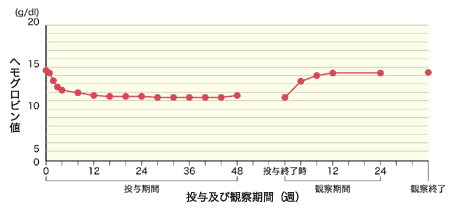
[投与薬剤の処置の有無別ウイルス駆除率]
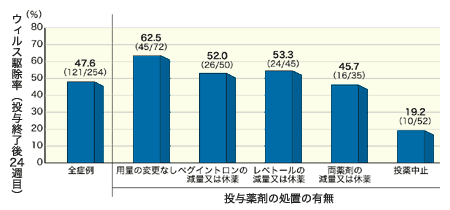
予後改善のためにも早急に望まれる健康保険の適応
ペグインターフェロン+リバビリンの併用療法は肝臓がんの再発を抑え、患者の予後の改善に大きく貢献する画期的治療法といえる。しかし、問題は健康保険が利かないという点だ。
「現在、健保が適用されるペグインターフェロン+リバビリン併用療法は、1型高ウイルス量の慢性肝炎のみです。肝臓がんの再発予防を目的とした場合は、いまのところ健保で認められていません。どうしても受けたい患者さんは、自費で行わざるを得ないという厳しい制約があります」(小俣さん)
もちろん、健保の枠内で行うための治験は始められたが、厚生労働省から承認されるのはまだ4~5年先のことだ。
ただし、手術やラジオ波焼灼療法等でがんをすべて消失させた後、保険診断名を「肝臓がん」から「慢性肝炎」や「肝硬変」に切り換え、事実上、健保で肝臓がんの再発予防を目的としたペグインターフェロン+リバビリン併用療法を受けている患者も少なくない。承認までの時間を待てない肝臓がん患者の窮状を見かねて、そうした便法で対応している医師も存在するからだ。
いずれにせよ、ペグインターフェロン+リバビリン併用療法によってウイルス駆除効果が飛躍的に高まり、再発の繰り返しを断ちきる道が切り拓かれたとはいえよう。早急な健保の適用が望まれている。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法


