肺がんに多い骨転移、新しい骨転移治療薬に注目が集まる
骨の破壊を抑える期待の薬
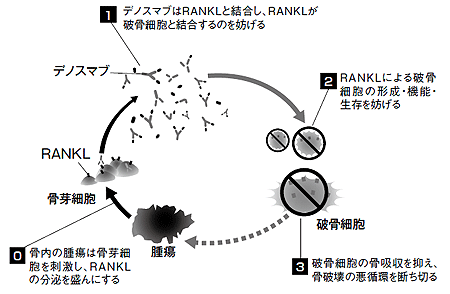
では、骨転移が起こるとなぜ骨がもろくなるのでしょうか? 骨はいつも同じようにみえますが、実は常にリニューアルされています。
新しい骨を作るのが骨芽細胞、古い骨を溶かすのが破骨細胞で、この両者がバランスよく働き、骨を生まれ変わらせているのです。しかし、がん細胞が骨に転移すると事情が変わってきます。骨に転移したがん細胞は、骨芽細胞を刺激してRANKLという物質の分泌を盛んにします。RANKLは、破骨細胞の働きを活発にしますから、これが増えすぎると、骨がどんどん溶けていきます。
また、破骨細胞が活発に働くと、骨の中に含まれる成分を取り込んで、さらにがん細胞の増殖が進んでしまいます。その結果、さらに破骨細胞が活性化するという悪循環に陥ってしまうのです。
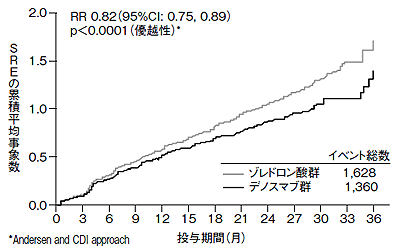
こうした骨転移の進行を抑える薬剤として、いま注目されているのがランマーク*という薬です。この薬は、前述したRANKLの作用を止めて、破骨細胞による骨の破壊を抑えます。その結果、がん細胞は骨から必要な栄養を得ることができなくなり、骨転移の進行が抑制されると考えられています(図4)。
骨転移の治療に広く用いられているビスホスホネート剤のゾメタ*との比較試験でも、ランマークは、骨転移している患者さんの骨関連事象(SRE)の発生を、有意に延長することが確かめられています(図5)。
ちなみに、骨関連事象には、「骨に対する外科処置」、「病的骨折」、「脊髄圧迫」などが含まれ、これらを抑えることは、QOLの維持に大きな意味を持ちます。
*ランマーク=一般名デノスマブ *ゾメタ=一般名ゾレドロン酸
低カルシウム血症・顎骨壊死などの副作用には注意を
一方、ランマークの副作用としてとく���注意したいのが「低カルシウム血症」とあごの骨が壊死する「顎骨壊死」の2つです。
通常、血液中のカルシウム濃度は一定に保たれています。「低カルシウム血症」とは、血液中のカルシウム濃度が低い状態を指し、逆に高い状態は「高カルシウム血症」といいます。ともに、そのまま放置すると、命に関わる場合があります。
低カルシウム血症は、ランマークによって破骨細胞の働きが抑えられることで起こります。低カルシウム血症は軽度なうちに発見し、重症化を防ぐための対処が必要となるので、治療中は頻回に血液中のカルシウムを調べ、手足のふるえ、筋肉の脱力感、けいれん、しびれ(唇のまわり、手・指など)、不整脈などの症状があったときには、すぐ医師に相談することが大切です。
また、腎臓の機能が低下していたり、過去に頸部(首のまわり)への放射線治療、甲状腺の手術などを受けたことがある場合などは、ビタミンDの作用が低下していることがあり、低カルシウム血症を起こしやすくなりますので、低カルシウム血症を防ぐために医師の指導どおりカルシウム・ビタミンDを毎日服用してください。
顎骨壊死は、あごの骨が炎症を起こし、骨の破壊が進んでいくもので、これを防ぐには、抜歯などの歯科治療を避けることや、歯磨きを励行するなど口腔内を清潔に保つことが欠かせません。
また、中西さんは、このランマークについて「転移の進行を抑制する作用は、既存の薬剤より優れているという研究結果があり有望」と高く評価し、「肺がん患者さんで骨転移が認められたケースでは、できるだけ早く投与するのが望ましい。ただ、低カルシウム血症や顎骨壊死などの副作用にはくれぐれも注意するように」とアドバイスしています。
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで


