本人はもちろん、家族や周囲のサポートが重要 高齢者の肺がん治療 個々の肉体年齢に応じた治療を
EGFR遺伝子変異があればイレッサを
一方、同じステージ3でも、遠隔転移はないものの広い範囲のリンパ節に転移があるものや、病変の分布が広くて放射線治療が難しい進行がんについては、ステージ4と同様に化学療法が単独で行われます。
「高齢者の進行がんの化学療法については、基本的には、暦年齢はあまり考慮しません。高齢者というと、先ほど述べたとおり、一般的に75歳以上を想定していますが、75歳以上であっても、若年者と同じ治療を選択する場合もあります。検査結果のデータはもちろん重視しますが、その人の生活習慣、たとえば、家の中でじっとテレビばかり見ている人なのか、外出が好きで、体を動かす仕事や趣味をもっている人なのかといったことによっても、治療の選択は変わってきます。問診・診察時に、いきいきとしていて、元気そうであるかないかが判断材料になります」
現在、ステージ3、4に対する化学療法で、まず考慮されるのは、患者さんに、肺がんの増殖に関わるEGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異があるかどうかです。
「日本人の肺がん(非小細胞肺がん)の5~6割は腺がんという組織型ですが、そのうちの4割ぐらいはこの変異を持っています。EGFR遺伝子の変異を持っていると、がんの増殖に関わる分子をピンポイントに狙い撃ちできる分子標的治療薬イレッサが使えます」
イレッサは内服薬であり、QOL(生活の質)を良好に保つため、肺がんの治療ガイドラインでも「1次治療で使う妥当性が示された」と記されています。
「高齢者の方ではとくに、イレッサを初回治療で用いることが多いですね。というのも、これは若年者で調べた臨床試験の結果ですが、先に抗がん剤治療を行った群と、イレッサを用いた群とで比較したところ、生存期間という点では変わらなかったものの、QOLという点からは、イレッサを用いたほうが良かったからです。これは全ての患者さんに言えることですが、抗がん剤治療を受けながら、いかにいい日常生活を送ってもらうかが治療を行う上で大切になってきます。そういった意味でも、高齢者の方でEGFR遺伝子変異がある方には、まずはイレ��サを使うことをお勧めします」
EGFR遺伝子変異がなければ個人に応じた化学療法
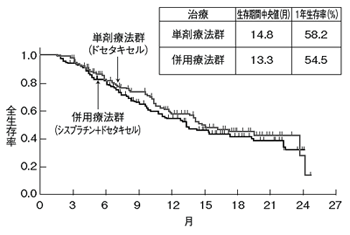
EGFR遺伝子変異がない場合は、化学療法が選択されます。これまで、そういった高齢者に対する標準的な治療としては、ナベルビンやタキソテール(*)といった薬剤を用いた単剤療法が基本でした。
しかし、昨年のASCO(米国臨床腫瘍学会)において、単剤療法よりも、プラチナ系(*)と呼ばれる抗がん剤を併用したほうが、生存期間を延ばすという結果が出たのです。
具体的には、70歳以上の高齢者の方を対象に、単剤療法群(ナベルビンまたはジェムザール(*))と、併用療法群(パラプラチン+ タキソール(*))を比較した結果、併用療法群のほうが、生存期間や無増悪生存期間(がんが悪化せずに生存している期間)が延びているという結果でした。
「こうした結果を受けて、海外では、高齢者の方でも、体力などに問題がない人には、プラチナ系の薬剤を併用していこうという流れになってきています」
(静岡がんセンターでの結果)
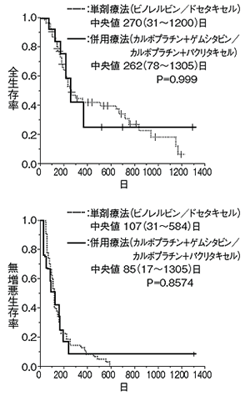
一方、日本ではどうでしょうか。今年発表された、日本人を対象に行われた試験では、先の海外の結果とは、異なるエビデンスが出てきたのです。
高齢者に対して単剤療法群(タキソテール)と併用療法群(シスプラチン+タキソテール)を比較したところ、生存という点ではとくに優劣はなく、QOLはむしろ、単剤療法群のほうが良いという結果が出たのです。つまり、日本の臨床試験では、プラチナ製剤を併用した場合の治療のメリットがはっきりと証明されなかったのです。こうした結果を踏まえて、高橋さんは次のように語っています。
「プラチナ製剤を併用できるような体力的に問題のない高齢者の方には、併用した治療を行ったほうがいいですが、だからといって無理に併用療法を行わなくてもいいと考えています。静岡がんセンターでも高齢者の化学療法について、単剤療法がいいか、プラチナ製剤を併用した治療がいいか、調べたことがありますが、明らかな差は認められませんでした。ですので、基本的な考えとして、年齢で分けた場合、75歳ぐらいまでは若年者と同様にプラチナ製剤の併用療法を行い、75歳から80歳までは、その人の全身状態に応じて併用療法か単剤かを決め、80歳以上の方には原則的に単剤療法を実施しています」
*タキソテール=一般名ドセタキセル
*プラチナ系抗がん剤=ブリプラチン、パラプラチンなど
*ジェムザール=一般名ゲムシタビン
*タキソール=一般名パクリタキセル
がん推進役の遺伝子の解明で肺がん治療は細分化
さらに今後は治療の選択肢がより細分化していき、高齢者の治療においても期待が高まると高橋さんは話します。
「先ほどのイレッサ以外にも、今後ALKという遺伝子の変異が陽性の人には、ALK阻害剤のクリゾチニブ(一般名)という薬が使えるようになってきます。現在がんを活性化させる、いわば、がんの推進役となっている遺伝子の解明に対する研究が進んでいますので、今後はそれらのターゲットを狙い撃ちできる薬が、いろいろと出てくる可能性があります。そうすると、個々の患者さんに最適な治療薬を使えるようになるはずです」
高齢者の肺がん治療は周囲の理解とサポートが大切
高齢者の肺がん治療は、治療のみならず、治療に臨む環境や態勢づくりも大切です。家族など周囲の人々の病気に対する理解とサポートはとても重要だと高橋さんは強調します。
「高齢者の場合は通院治療に不安を持っています。しかしできれば、入院せずに自宅で過ごしたいという人が多いのも確かです。自宅で過ごしながら通院治療を受けるためには、副作用に対する対応など、病状や治療内容についての知識を、ご家族に知っておいていだくことは大切だと思います。たとえば、夜中に急に熱が出たときに、白血球の減少などで敗血症になり得る緊急を要するものなのか、あるいはそうではないものかなどについて、家族の方があらかじめ知っておけば、あわてずに対処できます。
私たち医療者の側は、できるだけ治療に前向きになってもらえる努力をしますので、医師や看護師をはじめとする治療に関わるさまざまな人々と、密にコミュニケーションをとっていただき、患者の皆さんがよりよい治療を受けられることを望んでいます」
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


