普通の治療とどう違うの? なぜ必要なの? の基礎から知っておこう 肺がんの個別化治療って、何?
1つの抗がん剤の登場が個別化治療の道を開いた
「がんの組織型ごとに有効性が違うというのがわかったのは、アリムタ(一般名ペメトレキセド)という抗がん剤が出てきてからでしょう」
こう語る久保田さんによると、アリムタは新しいタイプの抗がん剤。水溶性ビタミンの一種、葉酸と分子構造がよく似ている葉酸代謝拮抗剤です。がん細胞は増殖するために葉酸を必要とします。そこで葉酸の代謝過程を阻害することでがん細胞の増殖を抑え、細胞死を誘発するのがアリムタの働きです。
もともとアリムタは、アスベストが原因とされる悪性中皮腫の薬として承認されました。その後2009年になって、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん」への適応拡大が承認されました。
ただし、進行・再発の非小細胞肺がんといっても、そのすべてがアリムタの対象となるわけではありません。非小細胞がんの中でも、扁平上皮がん以外の非扁平上皮がん、つまり、腺がんや大細胞がんに有効と考えられています。
非小細胞がん全体で、アリムタ+シスプラチン(一般名)併用群と、進行非小細胞肺がんの標準的治療の1つであるジェムザール(一般名ゲムシタビン)+シスプラチン併用群とを比較した海外の臨床試験の結果では、生存期間の中央値は両群に差がありませんでした。
しかし、非扁平上皮がんでの効果をみてみると、アリムタ+シスプラチン併用群のほうが有意に生存期間を延ばすという結果が得られたのです。
「それまで、非小細胞がんの治療では使用する薬の有効性に大きな違いがなく、副作用の出やすさなどで使い分けていたのですが、アリムタの承認により、非扁平上皮がんならアリムタ、それ以外なら別の薬、という明確な薬剤選択の基準が設けられることになります」
遺伝子変異の有無でも個別化治療が進んだ
このような組織型の違いに加え、さらに患者さんの遺伝子に変異があるかないかでも薬の効果に違いがあることがわかりました。これも個別化治療を実現する重要なポイントになっています。
代表的なのがEGFR(上皮成長因子受容体)という受容体の遺伝子変異があるかないかです。
非小���胞肺がんに有効な薬として登場したものに分子標的薬のイレッサ(一般名ゲフィチニブ)があります。
イレッサは、女性、腺がん、アジア人、非喫煙者に効きやすいということが報告されていました。しかし、経験上そう言われるだけで、理由は不明でした。その後の研究で明らかになったのがEGFRの遺伝子変異です。
そもそもがんは遺伝子に異常が起こることで発生するのですが、非小細胞がんでは、そのタイプのがんに特有の遺伝子に異常が認められることがあり、それがEGFRの遺伝子変異でした。
この異常がある患者さんとない患者さんとでは、イレッサによる治療効果に差が認められることがわかってきました。
アジア人で、腺がん、非喫煙者または軽喫煙者を対象に、肺がんの従来の標準的治療の1つであるパラプラチン(一般名カルボプラチン)+タキソール(一般名パクリタキセル)併用群とイレッサの治療効果を比較したIPASS試験と呼ばれる大規模臨床試験の結果が明らかになっています。
EGFRの遺伝子変異がある人では、従来の標準的治療よりイレッサのほうが、がんが増悪するまでの期間を2倍に延長することができました。
一方、EGFRの遺伝子変異がない人では、イレッサを使うと従来の標準的治療よりも早く増悪することがわかりました。
また、従来の標準的治療では、EGFRの遺伝子変異があってもなくても、増悪までの期間に大きな差はありませんでした。
「EGFRの遺伝子変異がある日本人を対象とした別の試験でも、同様の結果が得られていて、EGFRの遺伝子変異のある人にイレッサを投与すると、がんが増悪するまでの期間が最も延びることがわかりました」
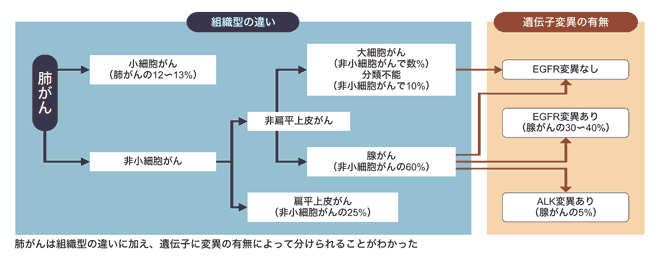
個別化治療によって生存期間が延びた
久保田さんによると、腺がんの中で、EGFRの遺伝子変異がある人の割合は3~4割。しかし、腺がん以外だと、せいぜい2パーセントぐらいでしかありません。さらに、非喫煙者となるとその割合はさらに増し、6割ほどにEGFRの遺伝子変異があるということです。
「EGFRの遺伝子変異のある人にイレッサが有効とわかって、明らかに患者さんの生存期間は延びています。国立がん研究センター東病院での調査によると、腺がんとか女性、非喫煙者では、イレッサを使えるようになった前と後とで比較すると生存期間が4~5カ月延びています。
その一方で、扁平上皮がんや男性の患者さんではほとんど生存期間が変わっていません。やはり、EGFRの遺伝子変異のある患者さんに対するイレッサ投与の影響が大きいと思います」
また、イレッサと同じ系統の分子標的薬であるタルセバ(一般名エルロチニブ)も、EGFRの遺伝子変異のある人に有効との結果が得られています。
「タルセバは、非小細胞がんの扁平上皮がんでも生存期間の延長が認められたとのデータがあるし、イレッサで効果がなかった患者さんがタルセバで効果があったとの論文もあります。タルセバもイレッサと同様にEGFR遺伝子の変異があると奏効率(*)が高いので、今後は遺伝子変異と組織型を組み合わせて、イレッサとタルセバを使い分けることになっていくでしょう」
*奏効率=がんの大きさに50パーセント以上の縮小が見られた割合
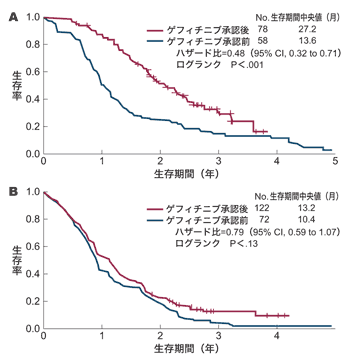
Bは、ゲフィチニブの登場前後で、EGFRに変異の無い患者さんの生存率の変化を表している。ゲフィチニブ登場前後も生存率に差がないことから、EGFRに変異の無い患者さんには効果がないことがわかる
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


