普通の治療とどう違うの? なぜ必要なの? の基礎から知っておこう 肺がんの個別化治療って、何?
新たに解明されたもう1つの遺伝子EML4-ALKとは?
ホットな話題となっているのが、腺がんの患者さんの一部にみられる遺伝子異常で、EML4-ALK遺伝子と呼ばれる遺伝子の存在です。
この遺伝子は、細胞の骨格タンパクをつくるEML4という遺伝子と、キナーゼと呼ばれるタンパク質リン酸化酵素をつくるALK遺伝子が入れ替わって(転座)できる融合遺伝子。
その結果、活性化した酵素がつくられ、ますますがんが増殖することになるのですが、この遺伝子を持つ患者さんにALKの働きを阻害するALK阻害剤を投与したところ、高い奏効率を示しました。試験の結果は今年のASCO(米国臨床腫瘍学会)で発表されて注目を浴び、現在、日本でも比較試験が行われています。
「この遺伝子を持つ人は、腺がんの5パーセントぐらいですが、非喫煙者の腺がんで、比較的若い人に多く、男女比は半々ぐらい。非喫煙者腺がんの8割ほどは女性なので、割合からすると非喫煙者の男性に該当する人が多いことになります」
副作用を遺伝子から予測する
それぞれがんのタイプに合った治療を行うということは、無駄な治療を受けなくてすみ、また副作用を少なくすることもできます。
それに加え、遺伝子を調べることによって、副作用をある程度予測できることもわかってきました。
小細胞がん(とくに進展型)では、カンプト/トポテシン(一般名イリノテカン)+シスプラチンの併用療法が試験され、エトポシド(一般名)+シスプラチン併用より有意に生存期間を延長し、奏効率84パーセントという良好な成績が得られ、現在わが国での標準的治療となっています。ただし、イリノテカンには、10人に2人くらいの割合で強い副作用(白血球減少、下痢など)が出ることがわかっています。このため、全身状態の良好な患者さんに限って投与されているのが現状です。
なぜ副作用がでるかというと、イリノテカンは、体内である活性物質(SN-38)に変換されて抗がん効果を発揮しますが、その物質は細胞に対する障害性が強く、そのままでは正常細胞にも作用するので副作用が強くあらわれてしまいます。
しかし、人によっては副作用がそれほどひどく��い場合もあります。それは、UGT1A1という代謝酵素の働きによって、毒性を抑えるからで、UGT1A1の遺伝子のタイプによっては、副作用が強く出る人と弱く出る人がいることがわかってきました。
そこで最近、UGT1A1の遺伝子を調べることで、イリノテカンの副作用が出やすい人、出にくい人を見つけ出す検査も開発されています。
個別化治療を受けるにはどのような検査が必要か
それでは、自分のがんのタイプはどのようにしたらわかるのでしょうか。
「肺がんの確定診断を行うための細胞診や組織診などの病理診断のときに、小細胞肺がんなのか、それとも非小細胞がんなのか、また扁平上皮がんなのか非扁平上皮がんなのかという、がんの組織型を診断することでわかります。そしてそこから腺がんと診断された場合や、またそれを否定できない場合は、EGFRの遺伝子変異があるかどうかを調べる遺伝子検査を行います」
遺伝子検査と聞くと、大きな病院でしか受けられないように思うかもしれませんが、気管支鏡で細胞や組織を採取し、検査会社に出して調べるので、細胞や組織を採取できる設備のある病院なら、遺伝子検査を受けることができます。
検査料金は2万円ですが、保険適用なので3割負担だと窓口での支払いは6000円。ただし、保険適用は原則として1回のみで、あとは自己負担となります。
組織型で「分類不能」といわれた中にはひょっとして腺がんが含まれているかもしれないので、「腺がんが否定できない」といわれたらEGFRの検査を受けたほうがよさそうです。
イリノテカンの副作用をチェックするUGT1A1の検査は血液を調べます。検査費用はEGFRの遺伝子変異検査と同じで、3割負担の場合、自己負担は6000円です。
患者さんの年齢や希望など、自身の問題も重要
このように、新しい薬の開発や遺伝子研究など医療のめざましい進歩に伴い、個別化治療が急速に進んでいるわけですが、「ほかにも個別化治療が大切な理由がある」と久保田さんは強調します。
「がんの組織型や遺伝子のタイプに合った治療というのは、あくまで医学的な観点に立つもの。しかし、実際の診療で問題となるのは、患者さんの年齢とか、どんな合併症を持っているかとか、あるいは患者さん自身の希望とか、まわりの家族の問題もあるでしょう。そうしたもろもろのことを考慮して行うことも個別化治療といえます」
1人ひとりの患者さんに対して、どんな治療を行うかを決める上で、「何が1番重要かというとPS(パフォーマンスステータス:全身状態の指標)です」と久保田さんは語ります。
PSは5段階に分かれていて、0は「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等に振る舞える」、つまり「元気な人」。5は「身の回りのこともできず、常に介助が必要で、終日就床を必要としている」、つまり「寝たきり」ということ。
「少しでも通常の生活ができるようにするための治療が重要で、個別化治療とはそのためにあるともいえます。
患者さん自身の治療に対する希望はとても大切です。たとえばかなりの高齢者でも、積極的治療を望まれている方は抗がん剤治療もうまく進むことが多いようです。「患者さんとのコミュニケーションも重要な個別化治療の1つです」と久保田さんは語ります。
進行非小細胞肺がんの患者さんに早期緩和ケアと標準治療を行った群と標準治療だけを行った群とを比較した試験がアメリカで行われ、前者のほうのQOL(生活の質)が良好であったのみならず、全生存期間の中央値も2.7カ月も有意に長くなっていました。
緩和ケア群では何をしたかというと、症状コントロールだけでなく、病状の理解の促進とか意思決定の支援なども含め、全人的なかかわりによるケアです。そうやってコミュニケーションを深めたことがQOLを向上させ、寿命を延ばしたと考えられます。
これこそ究極の個別化治療といえるかもしれません。
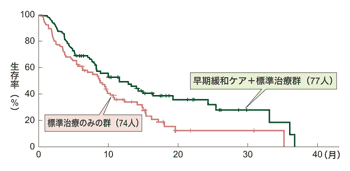
標準治療のみ受けた患者さんの生存期間中央値が8・9カ月だったのに対し、早期から緩和ケアを併せて受けた患者さんの生存期間中央値は11.6カ月と延長していた
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


