高齢に伴う合併症を考慮しながら、QOLを重視した化学療法の選択を 有効性があらわれてきた高齢者への化学療法
高齢者の進行非細胞肺がん
高齢者の進行非小細胞肺がん治療の歴史を振り返ると、90年代のはじめは、高齢者ががんになると病名告知もまだ十分に行われず、「無治療」と「治療」を比べてどちらが患者にとって有益かが問題になっていました。
その後、高齢者に対するナベルビンを使った治療の有効性が証明され、単剤を推奨しているのが今の段階。もちろんそれは、全身状態のいい高齢者という条件がつきますが、単剤でも有効なら、若い人で推奨されている併用療法でも効果があるのではないかというのが次の課題となり、ようやく、高齢者だけを集めた比較試験が行われるようになってきたところです。ただし、世界中で、高齢者だけを対象とした比較試験に積極的なのは日本とイタリアだけといいます。
武田さんも参加して日本で行われた「WJTOG9904」という臨床試験があります。70歳以上の進行非小細胞肺がん患者を対象にタキソテール(一般名ドセタキセル)とナベルビンとの第3相無作為化比較試験です。ナベルビンは現在標準治療として使われている薬であり、タキソテールはナベルビンと比べて毒性は若干強いものの、非小細胞肺がんに効果があるといわれている薬です。
試験結果は、生存期間の平均値はタキソテールのほうがやや成績がいいものの、統計学的な差はなく、ほぼ同等。QOLでは食欲不振、疲労、悪心などでタキソテールのほうに有意な改善が認められ、「高齢者進行非小細胞肺がんに対するタキソテール単剤療法は標準治療の1つと考えられる」との結論でした。
この試験でタキソテール群の生存期間の中央値は14.3カ月。高齢者を対象とした試験は90年代から行われていますが、別の薬剤を使った最初のころの試験結果で生存期間がせいぜい6カ月だったのが、14カ月にまで延びたのですから大変な進歩といえるでしょう。
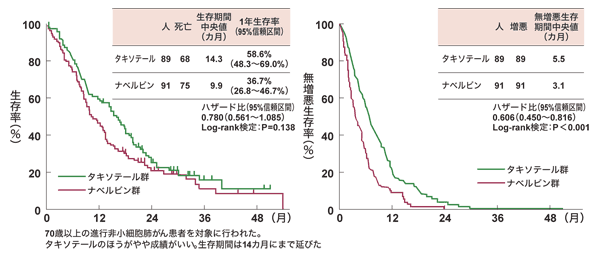
[タキソテールとナベルビンの副作用の比較]
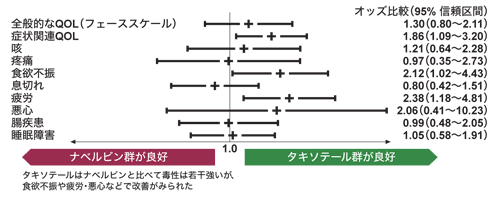
併用療法の是非は?
もう1つ、やはり日本で行われた「JCOG0207」という試験があります。
70歳以上の進行非小細胞肺がん患者を対象に、タキソテール単剤療法と、タキソテール+シスプラチン併用療法を比較した第3相無作為化試験です。
シスプラチンは腎毒性、神経毒性、嘔気などの点から、高齢者では使用困難と考えられている薬。タキソテールと併用して安全性と効果を検証する試験でしたが、結果は、75歳未満の全身状態良好な患者に対しては、若年者と同様シスプラチン併用の有用性が示唆されました。
しかし、症例数が少ない、投与方法が比較対象群と異なっていたため、さらなる検証が必要となり、再試験として、症例数を380人に増やした「JCOG0803/WJOG4307L」という臨床試験が始まっていて、その結果が注目されています。
新しい抗がん剤では分子標的治療薬(*)が期待されています。
「イレッサ(一般名ゲフィチニブ)、タルセバ(一般名エルロチニブ)などの分子標的治療薬は、治療効果を落とさず、毒性の軽減、QOLの向上、投与の簡便性などが評価されており、若い人以上に高齢者にメリットがあるかもしれません。患者さんによっては、初回治療として有用である可能性もあります」
*分子標的治療薬=体内の特定の分子を標的にして狙い撃ちする薬
家族や暮らしの問題も
高齢者の治療にあたっては、治療以外の問題、たとえば家族との関係とか、独り暮らしが多い問題などの配慮が大切です。
「人によっては治療を受けたくないという人もいますが、家族の思いとは違うことがあります。『治療してがんばれば長生きできるのだから』と家族は思うのですが、本人は『もうこれ以上つらい思いはしたくない』と思う。高齢の方にそういわれると、医学的にはもう少しできるという場合でも、こちらとしては引き下がるしかありません。
実際、治療をやめても元気にしていられる方もいらっしゃいます。残った時間が短くても充実した毎日をすごす、というのも1つの生き方であるのはたしかです」
また、武田さんが診療にあたる高齢者の患者さんの多くは通院治療を行っているといいます。
「なぜかというと、単剤治療なので副作用が軽いということもありますが、入院すると生活が変わって落ち込んだりするし、人によっては認知症を引き起こすこともあります。認知症になると化学療法を行うのは困難になるので、通える人はなるべく通ってもらうようにしています。独り暮らしの人も多いので、食事や生活の支援など、サポート部門との連携も重要です」
実は「年齢」より「状態」
本稿では高齢者の化学療法について、その有効性を見てきましたが、そもそも「高齢者向けの化学療法」というものが特別に存在するわけではない、と武田さんは語ります。
化学療法を行うにあたって何が問題かをつき詰めていくと、実は「年齢」ではないことに気づかされます。
化学療法で十分効果が得られるだけの身体機能がどこまで維持されているか、合併症を持っていないかが問題なのであり、高齢者は加齢ゆえにこうした点で不利を抱えているのはたしかです。しかし、若い人であっても、身体機能が低下していたり、合併症を持っていたりすれば、化学療法の適応にならないケースがあります。
「その意味で、全体の中で高齢者にフォーカスをあてるということは、若い人も含め、ほかの人たちをどう見るかにつながる意義があると思います。高齢者にスポットをあて、そこでの治療が成功すれば、その応用が今度は年齢が若くて状態の悪い人にも可能になるでしょう」
今までは“若くて元気な人”が中心だったのが、“高齢”の問題に着目することによって、高齢者にはどんな治療が有効かが明らかになれば、今度は“若くても状態の悪い人”など、さらに別の課題の解決にもつながります。たとえば、これまで治療が難しかった透析患者に対する有効な治療法も確立するかもしれません。
もちろん高齢者に対しても、単に高齢者という大まかな範囲ではなく、それぞれの年齢と全身状態を考えた、より患者の実情に即したきめ細かい治療法が実現するようになるに違いありません。
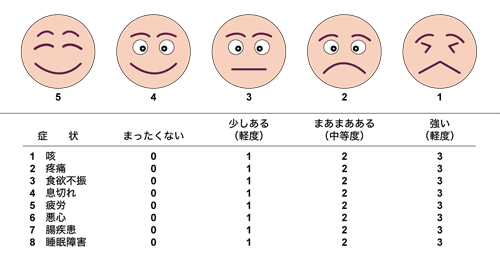
(下)症状の質問票
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


