転移がなく、腫瘍が3センチ以下なら5年生存率は80パーセントのデータも 体への負担が軽く、繰り返し治療できる肺がんラジオ波治療
手術や放射線治療に匹敵する成績
展開針には、針を広げたときの大きさが20~40ミリまで4種類あります。しかし、直径40ミリの展開針でも、焼ける大きさ直径3センチほど。大きさ自体はクールチップ・ニードルとあまり変わらないのです。
「ヨーロッパでは、肺の腺がんの場合、周囲8ミリに目に見えないがんが散らばっているという報告もあります。原発性肺がんならば少なくとも1.5から2センチ、転移性でも1センチは安全域が欲しい」と金澤さん(図2参照)。直径2センチのがんならば、少なくとも周囲4~5センチを焼灼するわけです。したがって、ごく小さながんは別にして、何度も針を刺したり、前後にずらしてラジオ波を流し、がん全体を大きく包み込むように焼灼します。
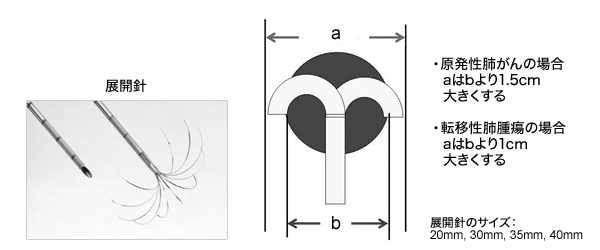
では、治療成績はどうなのでしょうか。
治療成績は、大きさによって大きく異なります。肺がんは、転移がなく3センチ以下のがんを1a期、転移がなくても3センチを越えると1b期と分類しています。図3は、岡山大学でラジオ波治療を行った1期の患者さん22例を分析したものです。これを見ると、3センチ以下ならば5年生存率は80パーセントに上っています。「手術や放射線治療に匹敵する成績です」と金澤さん。ところが、1b期、すなわちがんの大きさが3センチを越えると、2年生存率でも50パーセント、と成績がかなり落ちるのです。「3センチを越えると、目に見えない転移がある可能性がある」と金澤さんは話しています。
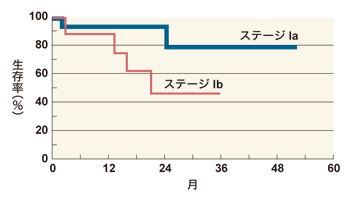
こうした結果からみても、原発性の場合、ラジオ波治療は「転移がない3センチ以下の肺がん、2センチ以下ならば最も良い適応」と金澤さんはみています。
がん細胞が本当に壊死したかその評価が重要
もう1つ、大きく進歩したのが画像診断装置です。
局所治療で、非常に重要なのはがんが本当に壊死したのか、その評価です。手術���違って、がんはその場で摘出されるわけではありません。組織を切除すればその断端を見て、がんが取りきれたかどうかを評価することもできます。しかし、ラジオ波の場合、基本的には画像、CTで評価することになります。しかも、ラジオ波治療の直後は、CTではむしろ病巣が大きくなり、2~3カ月経つとしだいに縮小、やがて消えるものもありますが、そのまま残骸が残ることも少なくありません。以前は、完全にがん細胞が壊死しているかどうか、患者さんの了解が得られればCTガイドに針で組織をとって生検を行うこともありました。あるいは、再度大きくなると再発と考えて、ラジオ波治療を再度行っていました。
しかし、現在はPETが登場し、がん細胞の生死を画像診断で見極めることが可能になりました。PETは、ブドウ糖の異性体に放射性同位元素で標識して、その代謝を画像化したもの。生きている細胞は糖代謝を行っているので赤くなりますが、壊死した細胞はもはやブドウ糖を消費していないので放射性同位元素の集積は見られません。
つまり、がんが壊死していればCT上では残骸があっても、PET上は消えてしまうのです。たとえば、3センチを越える肺がんをラジオ波で治療。CTでは再発の兆候はなかったのですが、PETでみると残骸の内側に放射性同位元素の集積を見ました。そこで、ただちに生検で確認。そこだけ、再度ラジオ波治療を行った例もありました。
もちろん、CTでもある程度壊死したかどうかはわかりますが、PETを使うとより正確に細胞の生死がわかるのです。ただ、PETは炎症にも放射性同位元素が集まってしまうので、「基本的にはCTで経過を観察し、炎症が治まる4~6カ月後にPETで再発や転移の有無をみます。あとは、CTとPETを組み合わせて半年から1年に1回ずつフォローしていきます」と金澤さんは現状を説明しています。
合併症が現れるのは5パーセント程度
このように、電極針が展開針になってより端まできちんと焼灼できるようになったこと、治療の評価にPETが使われるようになったことが、最近のラジオ波治療の進歩です。
これで、治療としての確実性はより高まったわけですが、合併症はどうなのでしょうか。
以前から、治療中には半分ほどの人に気胸が起こっていますが、これはたいてい自然に治ります。「持続脱気療法(*)が必要な人もいますが、きちんと対処できるので、心配はない」といいます。金澤さんが、今気にかけているのは、肺損傷と肺炎です。
展開針を使うと強力に病巣を焼灼できるのですが、焼きすぎると「組織が焼き切れて抜け落ち、肺に空洞ができるのです」。肺損傷です。やがて空洞は小さくはなりますが、必ずしも大きく焼いた人に起こるわけではないといいます。また、治療後に反応性の肺炎が起こることがあります。この肺炎は、細菌性ではないので白血球の数も増えず、抗生物質も効きません。そのかわり、ステロイド剤を使用することで、数日で落ちつきます。「治療した側と反対側に肺炎が起こることもあるので、焼灼によって何らかの物質が体内に放出されるのではないか」と金澤さんは考えています。
こうした合併症が現れる人は5パーセントほどで、命に関わるものでもありません。通常、ラジオ波治療は4~5日の入院ですみますが、こうした合併症が出ると入院期間が数日延びる程度です。しかし、金澤さんは「どういう人にこうした副作用が起きるのか、その原因を確かめてあらかじめ対策を講じられるようにしたい」と語っています。
さらに、問題はラジオ波で病巣を完全に焼灼したと思った人の中にも再発する人がいることです。つまり、1a期の残り20パーセントの人です。「外科手術でも同じなのですが、病巣をとっても再発する人がいるのです。まだわかっていない肺がんの性格なのか、原因は不明です。こういう人が出ると本当にガックリするのです」。もちろん、ラジオ波の場合、再発してもまた治療できるのが、大きな利点です。しかし、「できれば1度で治したい」というのが金澤さんの目標です。
*胸腔内にチューブを入れ、貯まった空気を持続的に対外に抜く治療
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


