検査技術の向上で1センチ前後のがんが発見され部分切除のニーズが高まる 術後の痛みも少なく早期に退院できる肺がん胸腔鏡下手術
手術成績は開胸手術に劣らないという評価が一般的
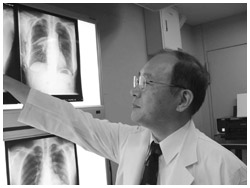
レントゲン写真を見ながら病状を説明する岩崎さん
胸腔鏡でも、切除する範囲などは開胸手術と同じです。では、手術成績はどうなのでしょうか。
岩崎さんは「生命予後も同じで、1期の場合胸腔鏡で手術をすると5年生存率は9割ぐらい。開胸手術でも8~9割なのでほぼ同じ成績なのです」と説明しています。この数字だけを見ると、多少なりとも胸腔鏡のほうが成績が良いように見えますが、岩崎さんによると「この数字は胸腔鏡が開胸手術に劣っていないと読むべき」なのだそうです。
というのも、同じ1期でも胸腔鏡下手術のほうが、がんが小さめで、リンパ節転移の可能性が少しでもある患者さんは受入れないなど、条件がよい患者さんが多い可能性があるからです。
「こうしたこれまでの手術成績からみて、1期の肺がんを胸腔鏡で行うことに問題はないと考えているのです」と、岩崎さんは語っています。
まだ、統一的な見解ではありませんが、手術成績は同じで開胸手術に劣らないという評価が、一般化しつつあると言えるようです。では、メリットはどうでしょうか。手術時間に関しては、ほとんど優劣はないようです。
岩崎さんによると、胸腔鏡で手術をした場合、「リンパ節の腫れがなく、肺葉もきれいに分かれているなど条件が良ければ2時間半から3時間」といったところだそうです。開胸だと2時間半ほど。内視鏡下外科手術は、操作が複雑なところもあるので、時間の短縮には繋がらないのです。
痛みも出血も少なく回復も早いメリットが
- 創傷が小さい
- 早く治癒する
- 出血が少ない
- 痛みが少ない
- 機能温存
- 術後の合併症が少ない
- 社会復帰が早い
やはり1番大きな���リットは、痛みが少なく、出血も少ない、回復も早いなど傷が小さいことに由来するものです。開胸手術にもいろいろな方法がありますが、一般的には背中から斜め前方に向かって大きく切開し、後ろ側の肋骨を1本離断するのがふつうです。筋肉も切られます。さらに、切開部分に開胸器を差し込み、肋骨と肋骨の間を広げて、手術操作のためにコブシ4個ぐらいが入るスペースを作ります。これが、術後の痛みの原因になり、また痛みのために呼吸がうまくできないので、肺炎などの合併症を起こす原因にもなるのです。
これに対して、胸腔鏡の場合、岩崎さんは4つの穴を開けるだけです。切除した肺葉を取り出す5センチの切開が1番大きな傷口ですが、ここにもカバーを挿入するだけで、押し広げるような操作はありません。したがって、「開胸でも胸腔鏡でも術後3日目までは硬膜外麻酔を続けるのですが、それを取ったあとの痛みが全く違う」と言います。
退院までの日数は、日本の場合地方に行くほど「できるだけ病院に置いてもらったほうが安心」といった感覚があるため、あまり指標になりませんが、「実際には1週間ぐらいで退院できる人がたくさんいる」そうです。
また、「浸出液などの排出のために留置するドレーン(排液管)が取れるのも胸腔鏡のほうが早いし、患者さんの顔つきに余裕があるというか、動きが全く違うのです」と岩崎さん。
最近は開胸手術でも早くから動くことを勧めている病院もありますが、無理に動いてもらうか、患者さんが自主的に動くかは大きな違いです。その違いを1番感じているのは、両方の手術を行い患者さんの様子を見ている医師たちかもしれません。
この日、胸腔鏡で一昨日手術をしたというA子さん(70歳)は、もうベッドに座り、家族とごくふつうにおしゃべりをしていました。食欲はまだもうひとつですが、トイレに行くにも不自由はないし、つらいほどの痛みはないとのこと。顔色もよく、外見的には肺がんの手術をしたという重病感は全く感じられませんでした。これが開胸手術だと、しばらくは傷を抑えて動くような状態だといいます。

胸腔鏡下手術創(肺葉切除)
傷跡が小さい

胸腔鏡下手術(肺葉切除)

開胸手術創(肺葉切除)
大きな傷跡が見える

開胸手術(肺葉切除)
傷を小さくすることに拘泥して危険を侵すことのほうが問題だ
このように、手術による体へのダメージが少なく、そのため回復も早いのが胸腔鏡下手術の大きなメリットです。福岡大学では、今年間120例ぐらい肺がんの手術をしていますが、その3分の1以上は胸腔鏡下手術で行っているそうです。それだけ早期がんが増えているのです。
ただし、胸腔鏡下手術といっても、確立した方式があるわけではないのです。岩崎さんたちは、胸腔鏡を挿入して映し出されたモニター画面を見ながら手術を行っています。しかし、10~15センチの切開を入れて、別の穴から入れた胸腔鏡を補助的に使いながら手術を行う胸腔鏡補助下の肺葉切除術もあります。この場合、7割方は肉眼で見て手術を行うので、肋骨の間も開胸器で押し広げます。それでも、開胸手術よりは傷も小さく、痛みも軽減すると言われています。
「こうした違いも、患者さんは理解して選択をしてほしい」と岩崎さん。ただし、どちらがいいというのではないのです。「傷の大きさは、医師の技術が高まればやがて小さくなっていくものです。それよりも、傷を小さくすることに拘泥して危険を侵すことのほうがはるかに問題です」と岩崎さんは指摘しています。
胸腔鏡下手術の症例数が多い病院を選ぶほうが賢明
実は、この安全性こそ、岩崎さんが胸腔鏡下手術で最も重視し、また教育や啓蒙に努めてきた点なのです。胸腔鏡下手術には多くの利点がありますが、欠点はリスクです。開胸手術ならば、万が一出血しても即座に手で圧迫止血をして処置ができますが、胸腔鏡ではこうした対処はできないのです。
そこで、岩崎さんはトレーニングのための人体模型や安全教育のための材料も開発しています。今では、日本中でこれが研修に使われているそうです。
ちなみに、腹腔鏡下手術の場合は、消化器外科学会が専門医の技術認定を行っていますが、胸腔鏡の場合は呼吸器外科の専門医認定の際に胸腔鏡のセミナーを2回受けるといった条件が入っているだけで、胸腔鏡の専門医の認定は行っていないそうです。「呼吸器外科の専門医であれば、胸腔鏡をできるだけの技量があるという判断です」と岩崎さん。
患者さんがより安全な胸腔鏡下手術を受けるためには、「やはり、肺がん手術や胸腔鏡下手術の経験が豊富で症例数も多い病院を選ぶほうが安心でしょう」と話しています。


同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


