危険性と効果をきちんと把握して、検査と治療を受けよう これだけは知っておきたい肺がんの基礎知識
分子標的薬の登場で大きく変わった薬物療法
現在行われている肺がんの化学療法は、90年代に確立されたものである。シスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダ)などのプラチナ系抗がん剤と、第3世代抗がん剤と呼ばれるイリノテカン(商品名トポテシン)、ビノレルビン(商品名ナベルビン)、ゲムシタビン(商品名ジェムザール)、パクリタキセル(商品名タキソール)、ドセタキセル(商品名タキソテール)などを組み合わせる多剤併用療法である。
「それ以前の抗がん剤に比べ、この頃から副作用の比較的軽い抗がん剤が出てきたわけです。それに、副作用を和らげる治療も進歩したことで、薬をたくさん使えるようになりましたし、回数も増やせるようになりました。それによって、がんを長く抑え込めるようになったのです。最近のトピックとしては、従来の抗がん剤に比べて副作用が軽減した新薬アリムタ(一般名ペメトレキセド)が登場し、治療の選択肢がさらに広がりました」
分子標的薬による肺がん治療は、02年のイレッサ(一般名ゲフィチニブ)の登場で始まった。
イレッサが使われ始めた当初、その副作用が社会問題化したが、適切な患者さんに使用された場合には、優れた治療成績を残しているという。
「イレッサはEGFR遺伝子に特定の変化がある人に用いた場合には、8割前後の人に効果を発揮することがわかっています。一般的な抗がん剤は、2剤併用でも奏効率は3~4割です。副作用とのバランスから考えても、イレッサのほうが圧倒的に有利なのです。EGFR陽性で、間質性肺炎のリスクが低い人なら、イレッサが第1選択薬でいいのではないかと言われています」
臨床の現場でも、イレッサを第1選択薬として使用するケースが増えてきているという。
分子標的薬についてはイレッサに続いて、イレッサと同じ分子を標的とするタルセバ(一般名エルロチニブ)が07年に認可され、すでに臨床の現場で使われている。
今後も、新しい分子を標的にした分子標的薬がたくさん登場してくると期待されている。
将来の肺がん治療の有望株はワクチン療法
将来の肺がん治療法として、現在有望視されているのがワクチン(免疫)療法だ。このワクチン療法とはどのような治療なのか、簡単に説明しておこう。
細胞の表面には、アミノ酸がつながったペプチド(化合物の総称)がある。がん細胞の表面にも、がん細胞独特のペプチドがあって、これががん細胞の目印になっている。
ワクチン療法は、がん細胞のペプチドを目印にして攻撃するように、体の免疫を活性化させる。そして、自分の免疫力でがんを攻撃させるという作用の治療法だ。
「治療用ワクチンについては肝臓がんやすい臓がんですでに研究が進んでいますが、現在、肺がんでも臨床試験が行われていて、国立がん研究センター東病院もこの試験に参加しています。結論が出るのはまだ先ですが、有望な治療法であると思います」
ただ、この治療は、「かたまりとして見えているがんを治すという方向には向かわないでしょう」と吉田さん。術後治療のように、「画像検査でも見えないほどの小さながんを攻撃するときに、効果を発揮する治療法ではないでしょうか」(吉田さん)という。
「この研究がうまく進めば、がんの発病予防にも役立ちます。定期的にワクチンを投与することで、発病する前の微小がんをたたけるからです。このような使い方で、がんを完全に予防できないとしても、発病を遅らせることができれば、それだけでもワクチン療法を使う意味はあります」
この肺がんワクチン療法の実用化については、6~7年後とみられている。
よい治療を受けるための病院選びのポイント
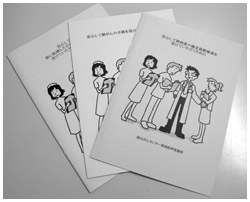
検診などで肺がんの疑いと診断されたあと、1番患者さんを悩ますのが検査と治療を受ける病院選びだろう。
この肺がん治療の病院選びについては、(1)肺がんの患者さんが多い病院(2)肺がんの豊富な治療経験を持つ病院――の2点が大きなポイントだという。
吉田さんに、病院選びの具体的なポイントをうかがった。
「手術を受けるのであれば、少なくとも週に1例程度は手術を行っている病院がよいでしょう。手術の技術というのは、身につけるためにも、それを維持するためにも、常に手術を行っている必要があります。また、手術を行う医師の経験数だけでなく、手術後の管理も、手術数が多い病院のほうが手慣れているので、手術後の大変な時期を乗り越えやすいと考えられます」
検査も治療も、危険が伴うことを忘れない
肺がんの診断と治療について、ここまでひと通り解説してきたが、検査を受けるにしても、治療を受けるにしても、程度の差こそあれ、効果とともに危険が伴うことを忘れてはいけない。
「80歳を超える高齢者で、合併症をお持ちの方は、検査や治療を受けることによって、死亡する危険性が明らかに高まります」
現在、肺がんの発病のピークは70代といわれるが、合併症などで危険性が高い70~80代の患者さんは、検査や治療を避けて、症状が現れてから、症状を取り除く治療を受けるという選択肢も考えられる。高齢の患者さんは、検査や治療を受けたほうがよいのかどうか、それらの得失について主治医とよく相談する必要があるだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


