進行度だけではなく、がんの種類によっても治療が異なることに注意! 『肺癌診療ガイドライン』のポイントをわかりやすく解説する
小細胞がんは1期以外は化学療法が治療の基本
小細胞がんの場合は、限局型と進展型に分けて、治療方針が立てられます。限局型はがんが片側の肺と胸に限局していて、転移はあっても近くのリンパ節(N1)に限られているものです。
小細胞がんの場合、化学療法が効くので、治療の基本は化学療法です。ただし、1期、つまりリンパ節転移のない限局型の場合は、とくにがんの大きさが3センチ以下(1A期)の場合、手術と化学療法を併用したほうが、5年生存率が高いことがわかっています。そのため、1期の場合は、まず手術でがんを摘出したのちに、再発予防を目的とした補助化学療法を行うのが標準的です。小細胞がんで手術が勧められているのは基本的にこの段階だけです。
限局型でも、1期以外の場合、たとえば片肺に限ったがんでも近くのリンパ節に転移があるような時には、化学療法と放射線療法の同時併用が行われます。放射線を同時に併用すると、化学療法単独に比べて3年生存率が5パーセントほど上がることが報告されています。
最近の報告では、限局型に化学療法と放射線療法の同時併用により、5年生存率が25パーセントであったとされています。
化学療法は、小細胞がんではシスプラチン(商品名ブリプラチンもしくはランダ)とエトポシド(商品名ラステットもしくはべプシド)の併用が標準です。吉村さんによると、最近は「シスプラチンとエトポシドよりシスプラチンとイリノテカン(商品名カンプトなど)のほうが生存率が高いという報告もありますが、イリノテカンは下痢などの副作用があるのでコントロールがちょっと難しいところはあるのです。
また、シスプラチンには腎毒性があるので、薬剤を尿中に排泄するためにかなりの量の輸液を投与する必要があり、腎臓が悪い人、あるいは、心臓の機能が弱っている人はシスプラチンの代わりにカルボプラチン(商品名パラプラチン)を併用します」
小細胞がんでも1A期なら5年生存率は40%に
こうした治療で、小細胞がんの治療成績は向上してきました。「昔は小細胞がんとわかった時点であきらめざるを得ないような状態だったのですが、今では5年生存率が1A期ならば40パーセントに達することもあります。シスプラチンが出て、治療成績が非常によくなりました」と吉村さんは語っています。
さらに、最近日本でも肺がん治療に認可されたアムルビシン(商品名カルセド)とイリノテカンがさらに治療成績を向上させるのではないかと期待されています。ただ、化学療法は副作用が強いので、体力が必要。一般に75歳を超えると難しくなるのも���実です。
一方、がんが肺の外にまで広がり、胸水が溜まったり、他の臓器に転移を起こしたのが進展型です。この場合は、全身的な効果が期待できる化学療法が行われます。
今のところ、シスプラチンとエトポシド、またはイリノテカンの2剤併用療法が標準的です。進展型では、長期生存例は稀で、生存期間中央値(治療開始後、50パーセントの患者さんが生存できる期間)は10~12カ月程度です。
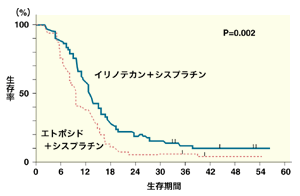
吉村さんによると「最近、アムルビシン単独でも併用療法に匹敵する延命効果があることが報告されている」といいます。シスプラチンとの併用に関しても、現在臨床試験が行われているところです。
こうしたことから、体力の低下した人や高齢者には、アムルビシンの単独療法もよいとされています。小細胞がんの治療は、新規抗がん剤の登場で、さらなる向上が期待されているのです。もっとも「小細胞がんは、進行が非常に早いので、1期で見つかる人は稀。放射線を併用できる限局型の段階で見つかれば、かなりいいほうです。この段階の5年生存率は約20~25パーセントですが、それでもかつてに比べれば画期的な数字なのです」と吉村さんは語っています。
なお、小細胞がんは治療で肉眼的にがんが消えた場合には、予防的全脳照射を行います。肺がんは脳に転移しやすいので、あらかじめ脳に放射線を照射し、がんの芽を摘んでおくのです。ただ、全脳照射をすると4~6割の人に物忘れなどの精神症状が出るので、車の運転などには注意が必要です。
非小細胞がんは術後に化学療法を行えば5年生存率がアップ
非小細胞がんの場合は、手術による摘出が治療の基本です。一般的には肺葉切除が行われます。
1A期(がんが3センチ以下で肺に限局していてリンパ節転移もない)は、吉村さんによると「手術だけで、5年生存率は8割」。手術をすれば8割の人が治るのです。この場合は、化学療法や放射線療法はかえって害になるだけなので、行われません。
1B期(がんの大きさが3センチを越え、リンパ節転移がない)と2期([1]がんが片肺に限局しており、かつ、リンパ節転移は近くのリンパ節に限られているもの、あるいは、[2]がんが肺を越えて隣接する胸壁や横隔膜などに及んでいるがリンパ節転移のないもの)も手術が行われますが、その後で術後補助化学療法が行われます。これが、前回2003年版と今回の改訂版の大きな違いです。吉村さんによると「2004年までは術後補助化学療法はやっても意味がないと言われていました。ところが、新しい抗がん剤による術後補助化学療法の効果が米国臨床腫瘍学会で発表され、一気に化学療法を行う方向に変わったのです」といいます。
この年、1B期の4年生存率は化学療法を術後に行うと59パーセントから71パーセントに向上すること、また1B期と2期を対象にした別の試験では5年生存率が54パーセントから69パーセントと15パーセントも上がることが報告されました。こうした結果が次々と報告され、手術後化学療法を行うことが標準治療になったのです。
使われる抗がん剤は、シスプラチンにイリノテカンやビノレルビン(商品名ナベルビン)、パクリタキセル(商品名タキソール)、ドセタキセル(商品名タキソテール)、ゲムシタビン(商品名ジェムザール)などの新規抗がん剤を組み合わせた2剤併用療法です。吉村さんによると「通常は、術後3週間ほどたって化学療法を開始する」そうです。いくつかの投与法がありますが、基本的には1日目にシスプラチンと新規抗がん剤のパクリタキセルあるいはドセタキセル投与(ビノレルビン、ゲムシタビンは1日目と7日目にも投与)し、これを1コースとして、3週毎に2~3回繰り返します。1B期の場合は、飲み薬のUFT(一般名テガフールウラシル)を使うこともあります。
手術による合併症は「肺炎や膿胸、縫った気管支が広がってしまうなどいろいろな合併症がありますが、肺葉切除ではほとんど0。日本の場合大病院では100人手術をしても手術で命を落とす人は1人あるかどうかというところでしょう」と吉村さんは話しています。安全性はかなり高いといえます。
| 原発腫瘤の大きさ | Tis上皮内がん | T1 ~3cm以内 | T2 3cm~ | T3 | T4 Nは関係なし | Tは関係なし | Tは関係なし Nは関係なし | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠隔転移所属リンパ節 | ||||||||
| MO 遠隔転移なし | N0所属 リンパ節転移なし | 病期0 | 病期1A | 病期1B | 病期2B | 病期3B | 病期4 | |
| N1 | 病期2A | 病期2B | 病期3A | |||||
| N2 | 病期3A | 病期3A | 病期3A | |||||
| N3 | 病期3B | |||||||
| M1 遠隔転移あり | 病期4 | |||||||
上図の補足説明
T-原発腫瘍
T1 肺組織または臓側胸膜に囲まれており、気管支鏡的にがん浸潤が葉気管支より中枢に及ばないもの(即ち主気管支に及んでいない)
T2 腫瘍の大きさまたは進展度が以下のいずれかであるもの
・最大径が3センチをこえるもの
・主気管支に浸潤が及ぶが、腫瘍の中枢側が気管分岐部より2センチ以上離れているもの
・臓側胸膜に浸潤のあるもの
・肺門に及ぶ無気肺あるいは閉塞性肺炎があるが一側肺全体に及ばないもの
T3 大きさと無関係に隣接臓器、即ち胸壁、横隔膜、縦隔胸膜、壁側心膜のいずれかに直接浸潤する腫瘍:または腫瘍が気管分岐部から2センチ未満に及ぶが、気管分岐部に浸潤のないもの:または無気肺あるいは閉塞性が一側肺全体に及ぶもの
T4 大きさと無関係に縦隔、心臓、大血管、気管、食道、椎体、気管分岐部に浸潤の及ぶ腫瘍:同一肺葉内に存在する腫瘍結節:悪性胸水を伴う腫瘍
N-所属リンパ節
N1 同側気管支周囲および/または同側肺門リンパ節および肺内リンパ節転移で、原発腫瘍の直接浸潤を含む
N2 同側縦隔リンパ節転移および/または気管分岐部リンパ節転移
N3 対側縦隔、対側肺門、同側または対側斜角筋前、または鎖骨上窩リンパ節転移
肺の切除と肺活量
肺は右側が3つ、左側が2つの肺葉から構成されています。肺がんの摘出手術では、基本的にこの葉単位で肺を切除することになります。
この場合、肺活量が60パーセントまで低下しても肺気腫など肺の病気がなければ普通の生活を送れるそうです。ただし、片肺を切除するなど肺活量が40~60パーセントになると、「平地を歩くのは大丈夫ですが、走ったり、階段を一気に登ったりすると息が切れます」と吉村さん。それでも、片肺をとってゴルフをしている人もいるそうです。肺活量が30~40パーセントになるとじっと座っていれば良いのですが、歩いたり体を動かすと息切れするようになり、30パーセント以下になると寝たきりになるといいます。
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


