ASCO2006・肺がんの術後化学療法、ガイドライン変更の必要なし 新しい治療法のリスクとベネフィットを正しく知り、悔いのない選択を
説明・同意の義務を改めて浮き彫り

もうひとつのトピックは、シスプラチンベースの補助化学療法についてのメタアナリシス。ヨーロッパを中心としたグループが、約4500例の臨床試験の結果を病期別に分析したもの。それによると、観察期間の中央値は5.1年で、全体の生存率でも無投与のグループに比べてハザード比は0.89と低い値を示しており、統計学的に有意差があった。5年生存率にみる術後化学療法の上乗せ効果は5.3パーセントと報告している。
病期別でみると、1A期はハザード比が1.41と高い値で、1A期に関しては補助化学療法の効果は期待できないというのが研究グループの分析。2期、3期についてはハザード比0.83であり、約15パーセントの患者が補助化学療法によって死亡のリスクを減少できるとしている。ただし、1B期についてはあえて結論を明言しておらず、さらなるエビデンスの確立が必要、としている。
また、薬についてはシスプラチンがキードラッグであり、シスプラチン+ビノレルビン(商品名ナベルビン)がもっともエビデンスベースの高い治療であるとしている。
第3のトピックは、今や化学療法は何でもかんでもやる時代ではない、オーダーメード治療の時代ということだ。DNAの修復に関与するERCC-1というタンパクがあまり発現していない患者にシスプラチン併用化学療法を行うと、生存率が向上することが明らかになった。この発表は、ERCC-1を調べれば、シスプラチンが効かない患者を最初から除外して患者を選ぶことができるという話として注目された。
全体のまとめとして、坪井さんは次のように話している。
「肺がん治療のガイドラインでは、術後化学療法を行うことを明記していますが、今年のASCOの発表をみるかぎり、はっきりと有意差が出ないような発表はあったものの、今のところ、ガイドラインを変更するまでには至っていません。ただし、少なくとも実際の医療現場では、1B期から3期の患者さんとその家族には、術後化学療法のリスク(副作用)とベネフィット(期待される効果)をしっかりと伝えなければならないことを、あらためて痛感しました。抗がん剤というのは基本的には毒ですから、その治療にはリスクが付きまといます。化学療法をやるかやらないかは、ぜひとも患者さん自身に決めていただきたい。その際、患者さんに正しく情報が伝わらないと、患者さんは誤った判断をされる可能性があります。そんなことにならないよう、患者さんに対して、具体的にリスク・ベネフィットをどう伝えていくかといったコミュニケーションスキルを、われわれ医者はますます勉強しないといけないと痛感しました」
| 有害事象 | グレード3 | グレード4 |
|---|---|---|
| 好中球減少 | 11% | 24% |
| 血小板減少 | 6% | 0% |
| 悪心・嘔吐 | 6% | 0% |
| 感染 | 6% | 0% |
| 高脂血症 | 15% | 1% |
| 筋肉痛・関節痛 | 6% | 0% |
| 倦怠感 | 3% | 1% |
| 感覚器系神経障害 | 5% | 0% |
化学療法の安全性については、評価はわからなかった
[術後化学療法で恩恵を受ける可能性]
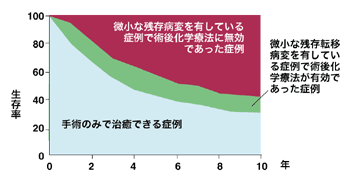
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


