これだけは知っておきたい肺がんの基礎知識 自分のがんはどんながんなのか、まずはそこを把握することが重要
周囲のリンパ節をとるリンパ節郭清は必要か
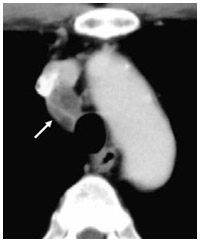
肺がんは、主に空気の通り道のまわりにあるリンパ節(縦隔リンパ節など)に最も転移しやすいことがわかっています。そこで、肺がんの手術では、そのリンパ節を周囲の脂肪組織と一緒に、ひとかたまりに取るのが一般的です(リンパ節郭清)。
リンパ節郭清を行うと、体内のリンパ液の流れが滞り、手足が急激にひどくむくむリンパ浮腫が起こることがあります。リンパ浮腫は、主に乳がんや子宮がんの患者さんで問題になっており、患者さんの術後のQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)をひどく損なうものと考えられるようになりました。
そこで、乳がんや子宮がんでは、転移が最初に起こるリンパ節だけを特定して郭清し、組織検査を行う検査方法が一般的になりつつあります(センチネルリンパ節生検)。転移が確認されたときだけ広汎なリンパ節郭清を行うことで、リンパ節転移のない人が無用なリンパ節郭清を受けずにすみ、リンパ浮腫に苦しむ患者さんが減りました。
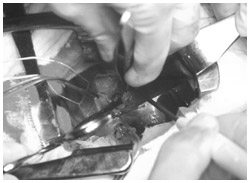
そんな経緯から、肺がんの患者さんにも、「リンパ節郭清は必要ですか」、「センチネルリンパ節生検はしないのですか」などと質問されることがあります。しかし、肺がんの場合、センチネルリンパ節生検は行わず、手術のときに縦隔リンパ節を郭清するのが今も一般的です。
理由は、第1に肺がんの手術でリンパ節郭清を行っても、リンパ浮腫が問題になることはほとんどないこと。第2に、リンパ節転移の程度が病期に大きく関わっており、病期を正確に診断するためにはリンパ節を取って顕微鏡で転移の有無を調べることが重要であること、です。また、リンパ節に広がったがんを郭清によって取り切ることで、がんが完全に取り除かれ、治癒(5年生存)に至る可能性があるというメリットもあります。ですから、現状ではリンパ節郭清を行ったほうがいいだろうと思います。
肺がんと抗がん剤の悩ましい現状
今���、肺がん治療の現場でも、さまざまな抗がん剤が使われています。ただ、肺がんに対して決定版と呼べるような抗がん剤はなく、治療成績も決して高いとは言えないのが、残念ながら現状だと思います。
たとえば、1B期の腺がんの患者さんが手術後にUFTという飲み薬を術後2年間飲み続けたら、飲まなかったケースに比べて5年生存率が1割ほど増えたという日本の報告があります。また、1B期以上の患者さんに対して、シスプラチンなどプラチナ系の抗がん剤を中心に、複数の抗がん剤を点滴したところ、治療を受けなかった患者さんより5年生存率がやはり1割ほど上回ったという海外の報告もあります。
少しでも効果があるなら使いたいところですが、抗がん剤は正常な細胞も傷つけるため、全身状態を悪くしたり、さまざまな副作用を引き起こしたりするむずかしい薬です。とくに、プラチナ系の抗がん剤は副作用が強く、亡くなる方もおいでです。つまり、肺がん治療における抗がん剤の現状をドライにまとめると、「10人中9人には効果がないうえ、死ぬこともある薬」ということになるのです。
それでも、今日ではプラチナ系の薬と、90年代に使われ始めた副作用がより弱い抗がん剤を2剤併用し、副作用を和らげる薬も使うことで、副作用をずいぶん減らせるようになりました。組み合わせもさまざまあり、出やすい副作用のパターンが違うので、患者さんの症状にあわせて使い分けられます。
抗がん剤の使い方についても、いろいろ議論があります。たとえば、2004年、世界最大の腫瘍学会であるASCO (米国臨床腫瘍学会)では、肺がんの1B期以上では術後抗がん剤療法が効果的という報告がありました。他方、抗がん剤(+放射線)療法のあとに手術を行う方法も世界中で試されており、ある程度以上に進行した肺がんをどのように治療するべきか、まだよく分かっていないところがたぶんにあります。
がんを選別して攻撃する分子標的薬が次々開発されるなど、抗がん剤研究は着々と進んでいます。それでも、「これだ!」という薬がなかなか現れない現状では、副作用とのバランスを見ながら抗がん剤を使わなければなりません。そのため、状況によっては抗がん剤治療をやめるという選択もあることを忘れないでほしいと思います。
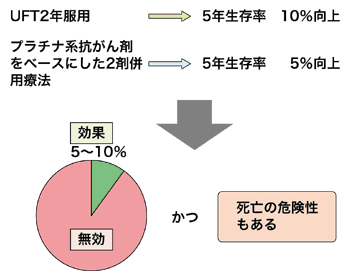
[非小細胞肺がんの術後5年生存率]
| 1A期 | 8割 | (85%、309人) |
| 1B期 | 6~7割 | (72%、163人) |
| 2A期 | 5~6割 | (48%、37人) |
| 2B期 | 4~5割 | (48%、103人) |
| 3A期 | 2割程度 | (32%、151人) |
再発後などについて医師・家族と話し合う
それに関連して、大事なことをもうひとつ。治療後のこと、とくに、再発してしまった場合のことなどを、早い時期から家族や医師と話し合っておくことを、私はおすすめしたいと思います。あえて言わせていただけば、治癒のむずかしい肺がんの患者さんは、診断を受けた最初から対症療法を活用し、QOLの維持を考えていただきたいのです。
副作用をともなう抗がん剤をどこでやめ、痛みやつらい症状を和らげることを主体とする緩和ケアに移行するか。それを考えるのも、QOL維持のためには必要です。主治医と相談し、慎重に決めてください。
緩和ケアは今日たいへん進んでいて、痛みや呼吸の苦しさはもちろん、身体症状はかなり改善できます。そのための技術を医療機関で教われば、身体症状を和らげながら、自宅で過ごすことも可能です。
逆に言えば、そうした症状を我慢するのは、美徳でも何でもありません。不必要なストレスを体に与えるだけと割り切り、積極的にケアを求めていただきたいと思います。
常に言われることですが、ご自分(や家族)の治療の主役は、ご自分(やご家族)です。どんな可能性があるのか、それにはどんな利点と欠点がつきまとうのか。できるだけの情報を集め、医師と相談のうえ、ベストな治療計画を立てていただきたいと思っています。
(構成/半沢裕子)
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


