息苦しさをやわらげる「呼吸リハビリ」 ちょっとしたコツをマスターするだけで呼吸がうんと楽になる
リラクゼーションだけでも呼吸が楽になる
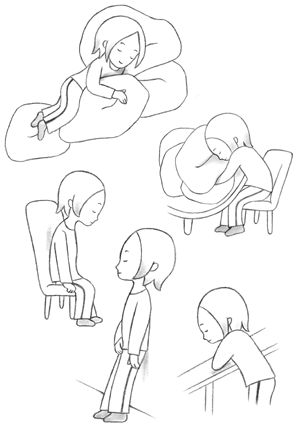
リラックスすると、体の力が抜ける
Aさんは週1回、合計6回通院。呼吸状態をチェックし、提案されたプログラムをマスターした。外来でのトレーニングの時間は20~30分間。同行した家族も一緒に呼吸法を学んだ。
「1から5のプログラムは簡単にマスターできます。これらを行うことで息切れは少なくなり、息切れ感をコントロールできます。6の運動療法は、体力を維持するために重要です。また、痰が出しにくいときには排痰練習をします。アカペラ(フジ・レスピロニクス(株)販売、米国DHD社製)などの排痰器具を用いると痰を出しやすくなります」と岩城さん。
なお、息切れが起きたときに最初に行うのは、1のプログラム、リラクゼーションである。息切れが起きたら、右の図のように壁や机などのもたれかかるような楽な姿勢をとる。そして、口すぼめ呼吸や腹式呼吸を行う。
「このリラクゼーションをマスターするだけで、呼吸が楽になります。息切れによるパニック状態を防ぐことができます」と岩城さん。 同病院緩和ケア病棟に入院中の患者にも呼吸リハビリテーションを必要とする人がいる。岩城さんらは、入院患者のベッドサイドで、その患者の呼吸状態に応じた呼吸リハビリテーションに取り組んでいる。
「呼吸リハビリテーションは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの慢性の呼吸器病への有効性は確立されています。しかし、肺がんなどのがんによる呼吸困難感や息切れに対して呼吸リハビリテーションがどの程度有効かについて、まだきちんとした報告はありません。ただ、これまでの現場での取り組みから言えば、肺がんなどによる息切れにも呼吸リハビリテーションはかなり有効だと感じています。息切れがあったら呼吸リハビリテーションに取り組んで、呼吸を少しでも楽にしてほしいと思います」(吉沢さん)
同病院では今年4月、リハビリテーション室に新たに2人の呼吸療法認定士を迎え入れて、呼吸リハビリテーションを強化する。
「呼吸リハビリテーシ���ンによって、肺がんなどのがんによる呼吸困難感や息切れを少しでも楽にさせてあげたいと思います。地域の中核病院の1つとして、大学病院の呼吸器科などと連携して、呼吸リハビリテーションの普及に努力していきます」と吉沢さんは語る。
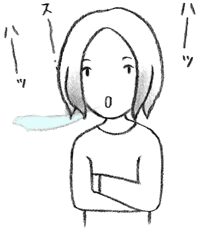
◎息をゆっくり吸い込み、速く強く息を「ハーッ」と吐き出す
◎2~3回くり返し咳をして痰を出す

食間に1日あたりコップ8~9杯のぬるい水を飲み、痰を出しやすくする

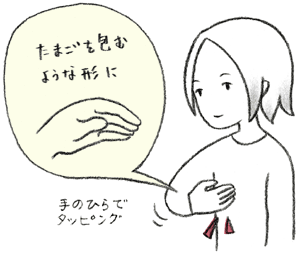
◎市販のバイブレーターか手で行う
◎バイブレーターはタオルを体に当てて使う
◎振動は1カ所1分以内
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


