進行別 がん標準治療 がんのタイプ、進行状況によって異なる治療法に注意!
進展型および再発治療
日本の標準治療が世界的な標準治療になる日も
進展型は、すでに全身にがんが転移している状態です。したがって、治療は全身的効果を期待して抗がん剤による化学療法が基本になります。
「世界的には、限局型と同様にブリプラチンもしくはランダ(シスプラチン)とベプシドもしくはラステット(エトポシド)の組み合わせが、現在の標準治療です。しかし、日本で行われた臨床試験(JCOG=日本臨床腫瘍グループ)で、ベプシドもしくはラステットより、ブリプラチンもしくはランダとカンプトもしくはトポテシン(一般名塩酸イリノテカン)を組み合わせたほうが、明らかに生存期間が長いこと、つまり効果が高いことが明らかにされている」そうです。
この試験では、生存期間中央値(中央の人が生存する期間)が、ブリプラチン(もしくはランダ)とベプシド(もしくはラステット)の組み合わせでは9.4カ月であったのに対し、カンプト(もしくはトポテシン)との併用ならば、12.8カ月と3カ月以上延長することが示されたのです。(下図参照)
この成績が2002年に世界的に著名な医学雑誌に発表され、日本ではほぼブリプラチン(もしくはランダ)とカンプト(もしくはトポテシン)の組み合わせが標準治療となっています。
現在、アメリカでもこの結果を検証する追試験が行われており、この結果が認められれば、ブリプラチン(もしくはランダ)とカンプト(もしくはトポテシン)の2剤併用が、世界的な標準治療になる可能性も高いのです。
こうした治療で、肉眼的にがんが消えた場合も、予防的全脳照射を行うことがあります。
十分な効果がない場合には、カルセド(一般名アムルビシン)という抗がん剤が使われます。「30パーセント前後の人に効果があり、有意にがんを縮小させることが認められています。そのため、二次治療薬(二番目に使う治療薬)としてよさそうと考えられている」そうです。これも、肺がん治療の朗報です。
治療した場合とそうでない場合の治療成績]
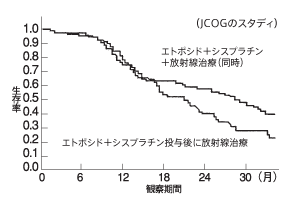
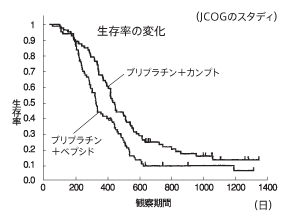
再発するまでの期間により治療の考え方が変わる
再発した場合、治療が厳しくなるのは、どのがんでも同じです。小細胞肺がんの場合もこれは同様です。しかし、一般的には治療後6カ月以内の再発か、6カ月を過ぎてからの再発かで、治療の考え方は変わってきます。6カ月以内の再発の場合は、「治療薬を変更するのが基本です。カルセドを含めて小細胞がんに効果があるとされている抗がん剤は他にもいくつかあります。これを試すことになる」そうです。
具体的には、エンドキサン(一般名シクロフォスファミド)、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、オンコビン(一般名ビンクリスチン)の3剤併用療法、あるいはブリプラチン(もしくはランダ)とベプシド(もしくはラステット)の併用で再発したのならば、ブリプラチン(もしくはランダ)とカンプト(もしくはトポテシン)に切り換えることもできます。
ただし、「これでどれだけ生存期間が伸びるかは、まだ確かめられていない」のだそうです。がん治療は、どれだけがんが縮小するかより、どれだけ命を延ばせるかが一番重要であることはいうまでもありません。この点については、科学的にはまだ解明されていないのです。
6カ月以上たってから再発した場合には、「抗がん剤に対する感受性を保持しての再発の可能性もある」。つまり、一度効いた抗がん剤がまた効くかもしれないので、以前効果のあった抗がん剤をもう一度使ってみるだけの価値があるそうです。それで効果がなければ、6カ月以内に再発した場合と同じように、別の抗がん剤を試してみることになります。
ただし、「小細胞がんでも、実際にはその中に非小細胞がんが混じっているケースがあります。化学療法で小細胞がんが死んで残った非小細胞がんが中心になって再発していることもありますから、再発時には*生検を受けて、どの細胞が残っているか確認してから治療を始めることを勧めたい」と佐々木さんは語っています。
*生検=体の組織を針か小切開によって少量採取し、細胞の性質などを調べる検査
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


