進行別 がん標準治療 がんのタイプ、進行状況によって異なる治療法に注意!
非小細胞肺がんの標準治療
非小細胞がんは、進展度によって1期から4期にまで分けられています。この場合、治療の基本は、手術です。
1期、2期、3期
手術できるかどうかの分かれ目は3a期
1期(がんが肺内にとどまっていて、リンパ節などに転移がない)と2期(がんが発生した肺と同じ側の肺門部のリンパ節に転移しているが、他臓器には転移していない)は、手術の適応となります。
「3b期(がんが縦隔に広がったり、胸水がたまる、あるいは反対側の首のリンパ節にまで転移している状態)になると、手術の適応はほとんどなくなりますが、3a期(胸膜までがんは広がっているが、転移は原発巣と同じ側の肺門部のリンパ節まで、あるいは縦隔リンパ節までにとどまっているもの)が、手術できるかどうかの境目です。まだ、専門家の一致した見解はないのですが、外科では手術適応の範囲と考える傾向があります」と佐々木さんは語っています。
つまり、状態や部位によって3a期でも手術が行われる場合と、3b期と同じ治療が行われる場合があるわけです。 実際には、非小細胞肺がんの人の6~7割はすでに手術不能の段階で発見されています。したがって、手術適応になる人はそう多くはないのが実情です。
手術できない3期のがん
手術できない3期も放射線と抗がん剤の同時併用療法
手術適応とならない3期の非小細胞肺がんでは、限局型の小細胞肺がんと同様に、放射線と抗がん剤による化学療法の同時併用療法が行われます。
「欧米では、80年代には放射線治療がスタンダードだったのですが、化学療法と比較しても生存期間に差はなかったのです。ところが、放射線単独で治療した場合と、放射線と化学療法を併用した場合で比較した結果、併用群のほうが生存率が高いことがわかり、今では局所進展型の非小細胞肺がんには放射線化学療法が標準治療になっている」そうです。
また、同時併用のほうが効果が高いことが明らかにされています。使う抗がん剤は、プラチナを含む抗がん剤(ブリプラチンかパラプラチン)と新規抗がん剤のうちのひとつを組み合わせた2剤併用療法です。
新規抗がん剤とは、この10年ほどの間に開発された抗がん剤のことで、カンプト(もしくはトポテシン、一般名塩酸イリノテカン)、ナベルビン(一般名ビノレルビン)、タキソール(一般名パクリタキセル)、タキソテール(一般名ドセタキセル)、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)があります。このうちの1剤とプラチナ製剤を組み合わせ、同時に放射線を照射するわけです。
ただし、ジェムザールとカンプトは放射線と併���できないので、放射線化学療法から除かれます。海外の比較試験ではどの組み合わせでも奏効率、生存率に大きな差はないそうです。

非小細胞肺がんの標準治療は、パラプラチン+タキソール

進行非小細胞肺がんに対する二次治療として
標準治療になっているタキソテール
命に関わる間質性肺炎に注意
また、放射線と化学療法を併用する場合には、間質性肺炎の発生に注意が必要と、佐々木さんは指摘しています。間質性肺炎は、通常の肺炎とは異なり肺胞をしきる壁に炎症が起きて、呼吸機能が低下する病気です。ステロイド剤などが治療に使われますが、ひどい場合は命に関わることもあります。
「タキソールやタキソテール、ジェムザールでも間質性肺炎は起こりますが、カンプト(もしくはトポテシン)のほうが頻度は高いのです。そのため、放射線化学療法を行う場合には、ブリプラチン(もしくはランダ)とカンプト(もしくはトポテシン)という組み合わせはあまり使わない」そうです。
稀ですが、放射線化学療法が非常によく効いて、中には手術にもちこめるようになる人もいます。この場合は、手術に備えて途中から放射線の照射量を低下させます。放射線照射によって肺が繊維化し、手術が難しくなるのを防ぐための処置です。
放射線治療ができない3期のがんと4期の治療
延命期間は2~3カ月。化学療法を受けない選択も
3期でも、すでに胸水が溜まっていたり、片側の肺に半分以上がんが広がっていると放射線治療を行うことは難しくなります。間質性肺炎を起こす危険が高くなるからです。
こうした放射線化学療法を行えない3期のがんは、4期(遠くの臓器などに転移したもの)と同じ治療が行われます。すなわち、化学療法が中心です。これに、必要であれば症状の緩和などを目的に、転移した部位に局所的に放射線を照射することもあります。
非小細胞がんは、小細胞がんに比べると抗がん剤などの効きが良くないとされています。しかし、1995年イギリスの著名な医学雑誌に、抗がん剤の有効性が発表されました。3期、4期の非小細胞肺がんを対象に行われた臨床試験を分析した結果、ブリプラチン(もしくはランダ)を含む化学療法を行った群は、積極的な治療をしないで緩和医療を行った群よりも、生存期間が伸びるというのです。この報告では、生存期間の中央値(中央の人が生存する期間)は、6~8週間、1年生存率は10パーセント上昇すると報告されています。
この結果から「非小細胞がんにも、抗がん剤が有効である」ことが、科学的に認められたのです。佐々木さんによると「一部には呼吸困難などの症状緩和作用もある」そうです。「そういう意味では、全身状態のよい3期、4期の患者さんには化学療法は症状緩和という意味も含めてお勧めできる治療です。ただ、それでも延命期間は2~3カ月です。副作用を考えて化学療法を受けないという選択もありうるとは思います」と佐々木さん。このあたりになると、患者さんの考え方や価値観によって、選択はかなり変わってくるのです。
外来で治療できるパラプラチンの利用を
ここで使われる抗がん剤は、4期の放射線化学療法と同じで、プラチナ製剤と新規抗がん剤のうちの1種類を併用する2剤併用療法です。放射線照射の併用がないので、この場合はプラチナ製剤とジェムザールの組み合わせも可能です。一方、プラチナ製剤として、ブリプラチン(もしくはランダ=シスプラチン)を選ぶのか、パラプラチン(カルボプラチン)を選ぶのかという問題があります。
これについて佐々木さんは、「ブリプラチンのほうが腫瘍縮小効果が高いので、日本ではこちらを使う傾向があります。しかし、全体の生存率はパラプラチンでもほとんど変わらないのです。QOL(生活の質)を低下させずに患者さんが自宅で生活できるという意味で、外来で治療ができるパラプラチンのほうがいいのではないでしょうか」と語っています。ブリプラチン(もしくはランダ)は、大量の補液が必要であり、しかも吐き気や嘔吐、脱毛、白血球減少などの副作用が少なからずあるので、入院治療が基本になります。4期の放射線化学療法で、毎日放射線を照射する場合は入院治療になるので、ブリプラチン(もしくはランダ)と新規抗がん剤の2剤併用でも入院という点に関しては同じです。
しかし、化学療法のみを行う場合は、全体の生存率がほとんど変わらないのであれば、ブリプラチン(もしくはランダ)を投与して何カ月か入院して過ごすよりも、副作用の少ないパラプラチンの組み合わせで自宅から通院したほうがいいのではないかというのです。残念ながら、治癒の可能性が低い状態であるからこそ、貴重な時間を自宅で過ごせる治療が選択されるべきではないかというのです。
「肺がんは、外来治療への転換が一番遅れている。実際に、世界ではパラプラチンとタキソールの組み合わせが、外来治療での標準になっている」そうです。
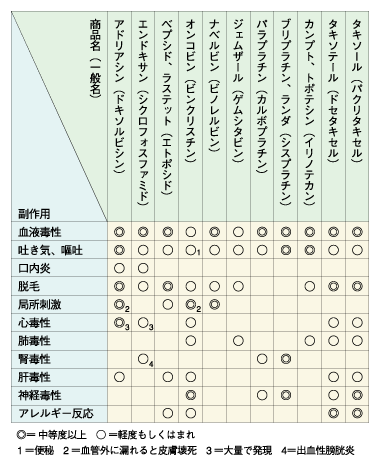
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


