進行別 がん標準治療 がんのタイプ、進行状況によって異なる治療法に注意!
再発時の治療
二次治療として効果が認められているタキソテール
非小細胞がんでは、現在二次治療まで標準的な治療法が確立されています。すなわち、先のような化学療法で効果がない場合、あるいは再発した場合には、二次治療が行われます。
現在、二次治療としての効果が認められているのが、タキソテール(ドセタキセル)です。プラチナ製剤を使ったあとに再発した場合、タキソテールを使うと生存期間の延長とQOLの改善が認められているそうです。
こうした臨床試験などの結果から、現在「化学療法は一次治療を行って、患者さんが納得すれば二次治療まで行うのが基本になっている」といいます。
新しい希望だが、標準治療とは言えない
一方、最近登場して注目されているものに、分子標的治療薬、イレッサ(一般名ゲフィチニブ)があります。これは、上皮細胞成長因子の受容体(EGFR)に作用して、がん細胞に増殖指令が出るのを阻止すると言われていますが、本当の働きはまだ解明されていません。しかし、世界的な臨床試験で、日本人の場合、再発した非小細胞がんでも27パーセントに有効(がんが50パーセント以上縮小する確率)と報告されて、大きな注目を集めました。
しかもこの薬は、1日1回服用する飲み薬で、吐き気など従来の抗がん剤に多い副作用は少ないことも報告されました。この結果を受けて、日本では2002年7月に世界に先駆けて認可されたのです。ところが、その後予想以上に大勢の患者さんに投与された結果、間質性肺炎が多発。死亡例が出て社会問題となりました。これまでのところ、4人に一人に効果があり、200人に一人が副作用で死亡すると報告されています。
これに関して佐々木さんは、「新しい希望とは言えますが、まだ標準治療とは言えません」と語っています。ただ、イレッサを使って「非常に長期にコントロールされている患者さんがいることは確か。これまでならば1カ月で亡くなる患者さんが半年、1年と生存されることが実際にある」といいます。つまり、長く効果が続き生存期間が大幅に伸びている患者さんもいるのです。しかしその反面致死的な肺障害を経験する患者さんもいて、イレッサ投与前に正確に予想できないことが臨床的には大きな問題となっています。
投与3日目に早くも現れた間質性肺炎
「従来の抗がん剤は、副作用に苦しんでも必ずしも効果があるというわけではなく、またつらい副作用に苦しんだ結果、少し効果があるという程度のものでした。ところが、イレッサの場合、効果の発現が非常に早く、効く人は服用開始後3~4日で症状が消えていく」といいます。その意味で、���れ味が極めて鋭い薬といえます。
しかし、逆に副作用の発現も極めて急激です。現在では、間質性肺炎の危険が周知され、その発見、治療に注意が注がれています。にもかかわらず、投与3日目の午後から間質性肺炎の兆候が現れ、ただちに治療を開始したにもかかわらず救命できなかったケースもあると言います。つまり、効果も副作用も非常に鋭いのです。
「臨床試験は、一次治療の効果がなくなった人が対象でしたが、イレッサを最初から使う臨床試験も行う必要があると思います。また、副作用も喫煙や併用薬など外的要因と遺伝的な体質の差異など内的要因を探っていくべきです」と佐々木さんは語っています。イレッサに関しては、まだまだ科学的な評価は十分定まっていないのが現状です。
しかし、佐々木さんの患者さんにも、脳転移で発見された非小細胞肺がんが、イレッサの投与で消失、その状態が1年以上続いている人がいるといいます。増加する患者さんのためにも、こうした分子標的治療薬を、何とか上手に育てていってほしいものです。
がん細胞の縮小効果と延命
これまで、抗がん剤の評価ではどのくらいの人で腫瘍が縮小するかが、最も重要視されてきました。そして、がんが縮小すれば、延命期間も伸びるはずと考えられてきたのです。ところが、最近10年でこうした考え方は大きく変化してきたと、佐々木さんは語っています。
つまり、腫瘍縮小効果に応じて延命期間は伸びないし、逆に腫瘍縮小効果は低くても、延命期間が伸びる抗がん剤もあることがわかってきたのです。たとえば、非小細胞がんの化学療法に使われるブリプラチン(もしくはランダ=シスプラチン)とパラプラチン(カルボプラチン)もそうです。腫瘍の縮小効果はブリプラチン(もしくはランダ)のほうが10パーセントほど高いのに、全体的な延命期間はどちらを使っても大差ないのです。二次治療に使われるタキソテール(ドセタキセル)も、奏効率(がんが50パーセント以上縮小する率)はわずか10パーセントです。にもかかわらず、タキソテールを使うと延命期間が伸びることが報告されているのです。
その解釈として、佐々木さんは「抗がん剤の併用で寿命が伸びる、あるいはがんの増殖を抑制する効果があってがんが大きくならない(不変)状態が長く続くということなのかも。もし抗がん剤による副作用に大きな問題がなければ、病気が進行するまでは、たとえ著しい縮小がなくても治療を継続する考え方も必要です。わが国の肺がん治療医の多くは、1~2回の投与で50パーセント以上の腫瘍の縮小がなければ治療を終了してしまうからです。」と語っています。
パフォーマンス・ステータス(下表参照)
化学療法を行うためには、ある程度の体力も必要です。そこで、化学療法が行えるかどうかは、患者の全身状態、すなわちパフォーマンス・ステータスによって決まります。基本的に、イレッサを含めて化学療法が行えるのは、グレード2までの患者さんです。
ブリプラチン(もしくはランダ)は、強い抗がん剤なのでグレード1まで、また放射線化学療法を行えるのも、グレード1までの患者さんです。実際には、3期~4期でグレード0の状態にある人はむしろ少ないので、放射線化学療法を行える人は限られることになります。
パフォーマンス・ステータスが3、4の人は基本的にベストサポーティブケア、つまり緩和医療の対象になります。しかし、今後はパフォーマンス・ステータスが悪い人でも、症状の緩和効果を含めて効果をみていくことが必要と、佐々木さんは語っています。
| 程度 (グレード) | 全身状態(パフォーマンス・ステータス) |
|---|---|
| 0 | がんと診断されても、無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる |
| 1 | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽労働(軽い家事や事務など)はできる |
| 2 | 歩行や身のまわりのことはできるが、ときに少し周囲の人々の手助けが必要なこともある。軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している |
| 3 | 身のまわりのことはある程度できるが、しばしば周囲の人々の手助けが必要で、日中の50%以上は就床している |
| 4 | 身のまわりのこともできず、常に周囲の人々の介助が必要で、終日就床している |
PDQを調べよう
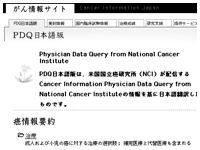
http://cancerinfo.tri-kobe.org/database/pdq/index.html
PDQとは、米国国立がん研究所(NCI)が発信している大規模ながん情報のホームページ。Cancer Information Physician Data Queryの略称。アメリカが国の威信をかけて開発した高度ながん専門情報データベースで、世界中から最新の臨床試験結果を集めて作成され、高い信頼性を得ている。その日本語版のホームページも、今年5月、京都大学探索医療センター探索医療検証部の福島雅典教授が中心となって作られ、治療、スクリーニング(検診)と診断、予防、遺伝子学、支持療法等の信頼される情報が無料で公開されている(「がん情報サイト」)。
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


