肺がん患者に有用な薬。しかし、副作用のない夢の薬ではない イレッサの真実
安易な投与が副作用を引き起こした
イレッサ発売前のセールスポイントはその効果の高さだけでなく、副作用の少なさにもあった。ところが現実には04年12月時点で588名もの肺がん患者がこの治療薬を利用したことで間質性肺炎を患い、かけがえのない命を落としている。
アストラゼネカが03年6月から03年12月までに日本国内614カ所の医療機関での3322例の症例を対象に実施した特別調査によると、間質性肺炎の罹患率は5.8パーセント。内2.3パーセントが死亡している。
間質性肺炎というのは、肺を形成している肺胞のすきまに炎症が起こる病気で、短期間で症状が進行する。とくにイレッサが関係している場合には、症状が急速に進行するため、治療は困難をきわめるといわれている。それにしてもこの治療薬の利用がこの病気の発病にどう関係しているのだろうか。肺障害との関係からイレッサの動物実験も手がけている東京女子医大呼吸器内科教授の永井厚志さんは、イレッサは病気の原因ではなく、この病気を促進する作用があるという。
「間質性肺炎になる患者さんのほとんどは、実はイレッサを利用する前から、症状はごく軽微ながらもこの病気を患っているか、その前段階である肺線維症を起こしています。肺がんは肺線維症にしばしば合併します。イレッサには肺胞の上皮細胞の働きを弱めて、肺胞内部の繊維芽細胞の働きを強める結果となることが考えられます。その結果、ごく軽微だった症状が一気に増悪していきます」
現在では症状のステージの度合い、喫煙歴、肺の既往症など、間質性肺炎が起こりやすい条件がある程度は明らかになっている。しかし、イレッサが承認された直後は、そうした発病のバックボーンが周知されていなかった。国立がん研究センター東病院の吉田さんは、そのためにイレッサが安易に投与されたことが、死亡数の増大につながった可能性もあるという。また、これは当然といえば当然のことだが、イレッサを利用する患者の多くが、末期段階にまでがんが進行しており、そのために体力が極端に衰弱していたであろうことも見逃せないだろう。
もっとも、それらとは別に多くの死亡者が多発した原因として、アストラゼネカあるいは国による、いわば人災としての側面が指摘されているのも事実だ。
海外で報告された副作用例が日本で本当に検証されたのかどうか、医療現場の副作用報告への対応に問題はなかったか、製品に付随する添付書が8回も改訂されているのはなぜか――これらの疑問はいまなお残っている。
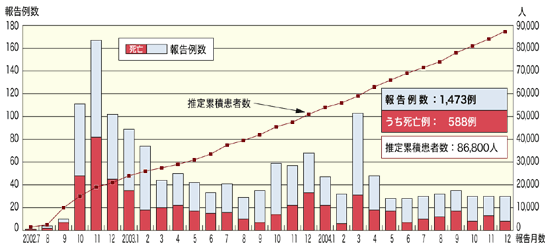
セカンドラインの治療に不可欠な治療薬
このようにイレッサを取り巻く問題は相次ぐ訴訟によって、社会的な側面でより広がり始めている。そのなかで肺がん治療の現場では、この治療薬をどう捉えているのだろうか。
肺がん治療のなかで手術が適用されない非小細胞がんの治療は抗がん剤治療が基本となり、ランダ(もしくはブリプラチン一般名シスプラチン)、パラプラチン(一般名カルボプラチン)などのプラチナ製剤に90年代に開発されたナベルビン(一般名ビノレルビン)、カンプト(もしくはトポテシン、一般名イリノテカン)などの抗がん剤を加えた2剤併用療法がファーストラインの治療として行われている。このファーストラインの治療で効果が現れなくなった場合にはセカンドラインとしてタキソテール(一般名ドセタキセル)という抗がん剤が単独投与されることが多い。
イレッサはこのタキソテールに代わってセカンドラインの治療薬として、あるいはタキソテールが効かなくなった場合のサードラインの治療薬として用いられている。
こうした治療の中で日々、イレッサに接している医師たちは、この治療薬をどう見ているのだろうか。
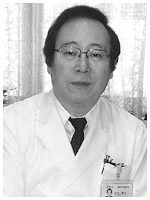
イレッサの動物実験を手がける
東京女子医大呼吸器内科教授の
永井厚志さん
取材を進める中で何人もの医師に話を聞いたが、いずれの場合にも共通していたのが「イレッサは不可欠の治療薬」という認識だ。前述の東京女子医大病院呼吸器内科教授の永井さんはさらにイレッサの効用の高さを語る。
「私のところでは手術が適用されないステージが3b以上の腺がん患者さんを対象にセカンドラインの治療薬としてイレッサを用いています。女性、非喫煙者で体調がよく肺に線維症の異常が見られないことなど、適用範囲を厳密に絞り込んでいるからでしょう。これまでの数10人の症例では、治験で示された奏効率をはるかに上回る成果が上がっています。そうしたケースでは腫瘍が縮小するとともに、胸水が取れ、背中の痛みもなくなるなど症状が画期的に改善する例も少なくない。私個人としては、この治療薬の切れ味を生かすためにファーストラインの治療薬としても使いたいくらいです」
ちなみに副作用はこれまでの症例で重篤な副作用が現れたケースは末期がん患者に用いた1例に過ぎないという。その場合も本人が副作用の危険を承知したうえで、どうしても使いたいと訴えがあったことから、永井さんはイレッサの使用に同意したという。
同じように国立がん研究センター東病院でも、イレッサを利用する場合には患者を絞り込んだうえでCTを用いて胸部の異常をチェックしている。その結果、重篤な副作用はほぼ完全に抑えられているという。
適用範囲を的確に絞り込むことで、イレッサの優れた利点を最大限に引き出すこともできるわけだ。当然ながら、それはすべての医療現場で行われなければならないことでもある。
客観的な視点を持ち、情報に振り回されない
もっとも私たちがイレッサによって提起された問題を風化させてはならないのも事実だろう。先の吉田さんはこの問題を総括するようにこう語る。
「イレッサは発売前から夢の新薬といわれ、じっさい治療を始めるとそのことを裏づけるような劇的な著効例も現れた。そうしてつくられた幻影に患者も医師も振り回されてしまったということでしょう。たかだか2、300人を対象にした治験では、薬の作用のすべてを確かめるすべがないことを忘れてしまっていたのです。そうした安易な利用が行われたところに落とし穴が待っていたということではないでしょうか。イレッサはすばらしい治療薬です。しかし、副作用のない夢の新薬ではありえないことを医師も患者も忘れてしまっていたのです」
客観的な視点を持つことによって、初めて私たちは薬剤によるベネフィットを高め、リスクを抑えることができるということだろう。
3月10日から3回にわたって催された検討会では目新しい動きは見られなかった。「ISEL試験」の再検証とともに、日本肺癌学会による「ゲフィチニブ使用に関するガイドライン」の一部見直しが行われ、より広い範囲へ周知されるよう厚生労働省に情報提供活動の推進が迫られた程度だ。
ただ、その後厚生労働省では新薬の承認審議期間に安全性試験を実施するなど、薬剤の承認システムの改正の準備も進められているという。
多くの死を無駄にしないために、そしてより多くの患者に充実した生をもたらすために、問題の検証を求めていくとともに新たな薬剤利用の環境づくりに期待したい。
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


