渡辺亨チームが医療サポートする:肺がん編
通院治療にはカルボプラチンとタキソールの組み合わせがベスト
山本信之さんのお話
*1 転移の診断
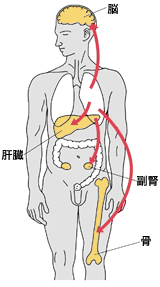
肺がんで転移しやすい部位は、肺の中の他の部分、肝臓、副腎、脳、骨などです。ですから、転移を調べるにはこれらの場所を全部検査しなければなりません。骨の検査には骨シンチグラフィという方法が、脳の検査にはMRI検査を行います。最近保険診療に採用されたPET(ポジトロン・エミッション・トモグラフィー、陽電子放出断層撮影)検査も脳以外の遠隔転移や、縦隔リンパ節(胸の中央部の気管支周囲のリンパ節のこと)転移を早い時期に診断することができます。しかし、早い時期に診断したからといって、その後の抗がん剤治療がよく効くというわけではないので、PET検査は、それほど役に立つ検査ではありません。
*2 抗がん剤の有効性
手術できない肺がんに対して、抗がん剤治療だけを行った場合、平均延命期間は約10カ月です。肺がんが完全に消えてしまうという完全寛解に至るのは100~1000人に1人の割合です。
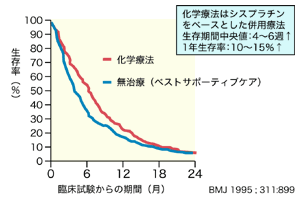
*3 多剤併用
肺がんの抗がん剤治療では、抗がん剤を1種類より2種類組み合わせたほうがより有効であることがわかっています。また、2剤より3剤のほうががんを小さくする効果はあるのですが、そうすると副作用も強くなるので、延命効果を考えると2剤のほうがいいという考え方が一般的です。現在は、シスプラチンとかカルボプラチンなど、××プラチンという名前の「白金系」の抗がん剤と、それ以外の抗がん剤を組み合わせた2剤併用の処方が、肺がんに対する標準的化学療法となっています。
*4 新世代の抗がん剤
1990年代に、肺がんに有効といわれる新世代の抗がん剤が次々登場しています。タキソール、タキソテール(一般名ドセタキセル)、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)、カンプト(一般名塩酸イリノテカン)、ナベルビン(一般名ビノレルビン)などの薬剤です。そして、これらの薬剤と、白金系の抗がん剤を組み合わせた新世代の治療法のほうが、従来のビンデシンを使った治療法より副作用が少なくて、有効性が高いというエビデンス(根拠)が出てきました。
では、新世代のうちではどの組み合わせがベストかということになりますが、これについてはまだ明らかな違いがわかっていません。病院によって、どの薬剤を使い慣れているか、患者さんがどういう副作用が許容できるかということによって、選択されることになります。
ただし、外来通院で抗がん剤治療を受けるということになると、シスプラチンよりカルボプラチンとの組み合わせのほうがベターと考えられます。カルボプラチンはシスプラチンより点滴時間がはるかに短くすみますし吐き気などの患者さんの自覚的な副作用も少ないので、通院に向いています。日本でよく行われているカルボプラチンとの組み合わせはタキソールです。アメリカなどではカルボプラチンとジェムザールの組み合わせも行われています。
4期・3b期非小細胞肺がん
| 白金系抗がん剤の併用が中心 | |
| シスプラチン(商品名プリプラチン、ランダ) | +塩酸イリノテカン(商品名カンプト、トポテシン) ゲムシタビン(商品名ジェムザール) ビノレルビン(商品名ナベルビン) ドセタキセル(商品名タキソテール) パクリタキセル(商品名タキソテール) |
| カルボプラチン(商品名パラプラチン) | +パクリタキセル |
| 白金系抗がん剤が使用不能な場合 | |
| 塩酸イリノテカン、ビノレルビン、ゲムシタビン、ドセタキセル、パクリタキセル | |
*5 抗がん剤の副作用
新世代の抗がん剤では、カンプトは下痢、タキソールやタキソテールでは脱毛、ナベルビンでは血管炎、ジェムザールでは発疹などの副作用が目立ちます。また、好中球減少は必ず出現しますし、腎機能障害や貧血、吐き気、下痢、などの副作用を伴なうこともあります。1000人に1人くらいの割合で強い副作用のため死亡することもあるといわれています。
| 商品名(一般名) | 副作用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血液 毒性 | 吐き気、 嘔吐 | 口内炎 | 脱毛 | 局所 刺激 | 心毒性 | 肺毒性 | 腎毒性 | 肝毒性 | 神経 毒性 | アレルギー 反応 | |
| ナベルビン (ビノレルビン) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| ジェムザール (ゲムシタビン) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| パラプラチン (カルボプラチン) | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| プリプラチン、ランダ (シスプラチン) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| カンプト、トポテシン (イリノテカン) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| タキソテール (ドセタキセル) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| タキソール (パクリタキセル) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
*6 G-CSF
G-CSFは細菌感染から体を守る好中球を増加させる機能のある薬で、わが国では保険がききます。抗がん剤により白血球数が1000以下、好中球数が500以下になると、感染が起こりやすくなるので、この薬を使う場合があります。または白血球数が2000以下、好中球数が1000以下で、高熱が出ている場合は、抗生物質と併用します。一般的には白血球が5000以上に戻るまで使うようにしています。
G-CSFのように抗がん剤の副作用を抑える治療を「支持療法」と呼びます。G-CSF、抗生物質、吐き気止め薬、血小板の輸血など、いろいろな方法がありますが、これらを最適に使用することができるのが腫瘍内科医なのです。
*7 腫瘍マーカーの意味
腫瘍マーカーとは、がん患者の血液中に検出される、がん細胞が産生する物質です。肺がんの種類によって高くなる腫瘍マーカーの種類が異なり、腺がんでは特にCEAというマーカーが高くなります。抗がん剤でがんが小さくなれば腫瘍マーカーが減少する傾向があることも事実ですが、信頼性はあまり高くなく、これだけで効果を判定することはできません。抗がん剤の効果を判定する上で、優先すべきはCTやレントゲンなどの画像です。腫瘍マーカーはその補助的な診断に利用します。また、肺がんがなくても、糖尿病、喫煙などで、CEA値が高値を示す場合もあります。
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


