「ジェムザール+パラプラチン」は進行肺がんに対するベストの選択 編集長インタビュー:肺がん治療の世界的権威、ロナルド・B・ナターレ博士に聞く
手先を使う職業人は避ける

――副作用の現れ方の違いは、薬の作用メカニズムと関係するわけですね?
ナターレ おそらくそうです。まず、タキソールやタキソテールなどタキサン系の薬は、がん細胞の細胞分裂に関与する*微小管に作用します。一方ジェムザールはDNAの合成そのものに作用する薬です。
――すると、個人によってより適応した化学療法を選択することが可能なのでしょうか?
ナターレ それがじつはできないのです。どの患者さんにどの薬がリスクが多いとか少ないとかわかればいいのですが、今のところわかりません。ただし、タキソールなどは神経毒性が現れやすいので、たとえば音楽家やデザイナーなど、手先を使うような職業の人は避けるようにします。
――アメリカでも分子標的薬イレッサが承認されましたが、日本ではすでに副作用による死亡事故などが多発して話題になっています。3種類の併用療法とイレッサの効果は比較されていますか?
ナターレ まだイレッサとこれら三つの化学療法を純粋に比較した試験はありません。ただし、私の経験に基づいて予測すれば、これら三つの化学療法に比べてイレッサの奏効率は低いだろうと思います。おそらくイレッサの役割は、化学療法に置き換えたり、同時に使うというものではなく、その前後に用いることによって貢献するものでしょう。化学療法のほうはすでに実績があるわけですから、現在はまず化学療法を行い、そのサイクルの中にイレッサを取り入れるという方法が試みられるようになっています。
*微小管=細胞内に存在するミクロの中空の細管。細胞の形態維持や変形、染色体の移動、細胞分裂などに関与する
高齢者でも受けるメリットは?
――お話をお聞きしていると、ジェムザール+パラプラチンが進行肺がん治療のベストの選択ということになりますね?
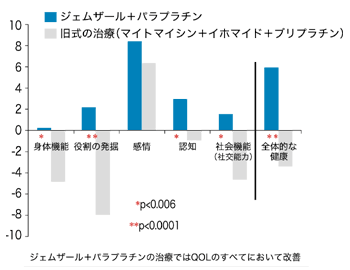
ナターレ 現在はそういえます。化学療法ではしばしば副作用がひどいために治療を中断しなければならないことがありますが、この組み合わせで治療を打ち切るケースはわずか1パーセントほどです。
――高齢者であっても化学療法は受けるべきですか?
ナターレ すでに高齢の患者さんを対象とした臨床試験もいくつか行われており、若い人と同様の奏効率や症状の緩和、QOLが得られるというデータが出されました。スウェーデンで行われた試験では、70歳以上の患者さんが40パーセントも入っていて、ここでもジェムザール+パラプラチンが生存率を大きく改善することが証明されています。お年寄りもぜひ化学療法を受けていただくべきです。
――ではこのすぐれた治療法をもっと広く普及させる必要がありますね?
ナターレ おっしゃる通りです。まずドクターへの啓発をやっていかなければいけません。医師がぜひ知っておくべきことは、脱毛の副作用がきわめて少ないということです。これはがんの患者さんの尊厳を守る上で、とても重要なことです。治療法を選択する場合、効果の面で同等であれば、脱毛などの患者さんのQOLに大きく影響する要素も考慮した上で、選択する必要があります。患者さんに情報を提供するのも医師の役割ですから、医師がよく知っていて患者さんにちゃんと伝えてほしいと思います。
代替医療との併用には注意
――化学療法を受ける場合、患者さんが心がけるべき点は?
ナターレ 私は患者さんに六つほど注意点をお話します。
まず化学療法を受けた当日と翌日はできるだけ飲み物をとって水分を補給すること。二つめは吐き気を抑えるため、食事はできるだけ小分けにして回数を多くすること。三つめとして、とくにアメリカ人の食事は栄養が偏りがちなので、マルチビタミンのサプリメントを摂ることを奨めています。ただし、ビタミンの摂りすぎはよくありません。
四つめはつとめて体を動かそうとすることで、とくに歩くことを勧めています。五つめは患者さんによっていろいろな宗教や思想を持っているので、注意しながら伝えているのですが、できるだけ精神面を大切にしようということ。
最後に代替医療のお話をします。アメリカでは最近、民間療法や伝統医学を利用する人がとても多くなっていますが、なかには化学療法と併用すると非常に危険な相互作用を起こす場合もあります。
私のセンターでも、患者さんが漢方薬を飲んだために、腎不全や肝不全に陥った例がありました。患者さんが代替療法を利用する場合は、前もって必ず医師と相談するようにお話しています。
患者に対してチームでサービス
――まわりから患者さんをどのようにサポートすればいいのか、アドバイスを?
ナターレ 私たちのセンターでは、心理療法士、ソーシャルワーカー、栄養士、理学療法士、疼痛管理士などが、患者さんへのサービスチームを組んでいます。チームでイブニングディスカッションを開催し、患者さんやご家族が参加してどのようにがん治療に対処するかとか、がんに打ち勝った体験談を話し合う機会を設けているのです。こうした活動の狙いは、患者さんが孤立しないようにすることと、一方で自立を忘れないようにすることでしょう。それががん闘病でたいせつなことだと思います。
アメリカでは昨年『Cancer care』という雑誌が誕生していますが、この雑誌のコンセプトは、患者さんやご家族がいかにがんに対処するかを考え合うというものです。この『がんサポート』も同じようなコンセプトをもつ雑誌だと思いますが、こうした雑誌に盛り込まれた情報も、患者さんのサポートのために非常に重要な役割を持っていると思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策


