イレッサは、効果と副作用の面から見ると長期に渡って治療継続が期待できる EGFR遺伝子変異陽性肺がんはまず分子標的薬で治療する
EGFRの信号を抑えがんの増殖を抑制
イレッサなどのEGFR-TKIは、どのようにして効果を発揮するのだろうか。
EGFRというのは、がん細胞の細胞膜を貫通する状態で存在している。そして、細胞の外側にある受容体に増殖因子が結合すると、EGFRは活性化し、細胞内に向けて「増殖せよ」の信号を送り始める。この信号が、がん細胞の核にまで伝えられ、がん細胞は増殖する。
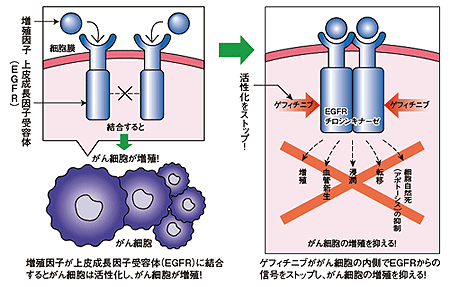
イレッサなどのEGFR-TKIは、細胞内でEGFRに結合し、信号が伝達されるのを抑え込む働きをする。それによって、がんの増殖を抑制するのである(図4)。
「EGFR遺伝子変異陽性の肺がんは、欧米では肺がんの患者さんの10%程度しかいません。ところが、アジア人には多いことが知られていて、日本人では30~50%の患者さんが陽性です」
陽性ならば、きわめて有効な治療の選択肢が増えることになる。アジア人であること以外に、非喫煙者、女性、腺がんの患者さんにも、EGFR遺伝子変異陽性の人が多いことが知られている。
宮城県立がんセンターのデータでは、非喫煙者、女性、腺がんの条件がそろうと、EGFR遺伝子変異陽性の人の割合は約50%。中には60%と報告している施設もあるという。
EGFR遺伝子変異検査が陽性なら1次治療はイレッサ
EGFR遺伝子変異検査の結果、陽性とわかった患者さんにとって、最もよく効く治療薬は、EGFR-TKIである。そのため、イレッサは日本肺癌学会肺癌診療ガイドライン2012年版で1次治療薬として推奨されている。
ところが、現実には、1次治療でイレッサが使われていないケースもあるようだ。
「最もよく効く薬を後にとっておこう、という考え方があるのです。しかし、このような考えに基づいた治療には、少なからずリスクも生じます。それは、すべての患者さんが、2次治療を行えるわけではないからです」
欧米では、抗がん療法を始めた患者さんの約30%が、2次治療に進むことができない、というデータが報告されている。日本でも、臨床試験などを除く通常治療においては、約20%の患者さんが、1次治療だけで治療が終了してしまっているのだ。
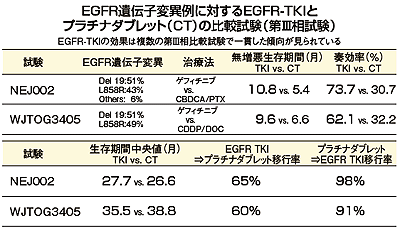
Inoue A et al;Ann Oncol. 2012 Sep 11. [Epub ahead of print] Mitsudomi T et al;
Lancet Oncology:11 (2),121-8 (2010) Mitsudomi T; ASCO 2012, 7521
「つまり、イレッサなどのEGFR-TKIを後に回してしまうと、最もよく効く薬を使えないまま、治療を終える患者さんが出てくることになります。これは大きな問題だと思います」(図5)
イレッサによる治療を開始しても、それがいつまでも効くわけではなく、平均すると1年ほどで耐性(*)ができ効かなくなってくる。そうなった場合には、抗がん薬による治療への切り替えが行われる。
このような順番で治療することにより、キードラッグであるEGFR-TKIを必ず使用でき、全身状態がよい状態で次の抗がん薬に移れ、生存期間を延ばすのに役立つと考えらえている。
*耐性=投与を繰り返しているうちに、薬の効果が弱まり、最終的にほとんど効かなくなる現象
イレッサによる治療は仕事しながら行える
イレッサは経口薬である。通常、1日1回、1錠を内服する。点滴で投与する薬のように、投与するのに時間を取られることはない。
間質性肺炎など危険性の高い副作用が、投与後早い時期に起こりやすいため、宮城県立がんセンターでは、最初の2週間は入院で治療が行われている。
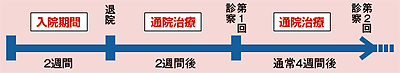
それで問題がなければ通院治療となる。最初は入院と同じレベルで管理・観察を十分に行うため、2週間分の薬が処方される。その後、問題がなければ4週間分の薬が処方されることになる。経過が順調なら、4週に1回通院するだけでいいのだ(図6)。
「治療を受ける患者さんにとっては、便利な薬だと思います。そうしたこともあって、仕事を続けながら治療に取り組んでいる患者さんも少なくありません」
こうした利便性のよさも、イレッサが広く使用される理由の1つである。
副作用の皮膚障害は乗り越えられる
イレッサの副作用で、最も頻度が高いのは皮膚障害である。程度は個人差があり、中にはかなりひどくなる人もいる。
「イレッサが登場した当初は、皮膚障害がひどくなり、これ以上治療を続けられない、という状態になるケースもありました。しかし、最近は、きちんとステロイド軟膏を使用したり、炎症を抑える目的で抗生剤を使ったりすることで、皮膚障害は十分にコントロールできる副作用になっています。皮膚障害で、イレッサの服用を中止することになるケースは、最近ではまずありませんね」
皮膚障害が重い場合には、皮膚科と連携して副作用の治療に当たることも勧められている。
間質性肺炎は息切れに注意
頻度は高くないが、生命の危険があるため、細心の注意を払わなければならない副作用が、間質性肺炎である。イレッサによる間質性肺炎の発症率はさまざまな報告があるが、多く見積もって約6%。通常の抗がん療法でも、約2%の頻度で起きることがわかっている。
とくにイレッサによる治療を受ける場合には、間質性肺炎が起こる可能性を、常に考えておく必要がある。
「大切なのは、間質性肺炎が発症したときに、なるべく早く治療を開始することです。治療が遅れると、わずか1週間ほどで命を落としてしまうこともあります」
早く発見するためには、現れている症状を見逃さないことが大切だ。肺炎だから咳が出て発熱があるのだろう、と思っている人が多い。もちろん、そういうこともあるが、必しもそうだとは限らない。
「咳は出る場合も、出ない場合もあります。発熱だけという人もいますね。熱と咳が出ればわかりやすいと思いますが、風邪だろうと考えてしまって、発見が遅れることがあります」
鼻水も出たら風邪の可能性が高くなるが、熱と咳なら、まず間質性肺炎を疑ってみる必要がある。
「もう1つ、ポイントとなるのが息切れです。いつもは息切れしないようなことで、息切れが起こります。たとえば、トイレに行ってきただけなのに息切れがする、などといった症状です。間質性肺炎が発症している場合、息切れは必発と考えていいでしょう」
イレッサを服用していてこんな症状があった場合には、すぐに主治医に連絡する必要がある(図7)。
| 急性肺障害・間質性肺炎について | |
| ● | 服用中、急性肺障害・間質性肺炎が疑われる症状 息切れ、呼吸がしにくい、咳および発熱等 →直ちに医療機関へ |
| ● | 急性肺障害・間質性肺炎を起こしやすい人 服用前に肺の間質部分に炎症があったり、肺が線維化している状態、全身の状態が悪い場合、たばこを吸っていた人や他の抗がん剤治療をした経験がある人 |
| ● | 急性肺障害・間質性肺炎が起きた場合に危険なケース 服用前に肺の間質部分に炎症があったり、肺が線維化している状態、全身の状態が悪い場合 |
| とくに注意しなくてはならない症状 | |
| ●呼吸がしにくい、またはかぜの様な症状がつづく●下痢がひどくて止まらない●のどが渇く、体がだるい、尿量が減っている●中毒性表皮壊死融解症(ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう)、皮膚粘膜眼症候群(ひふねんまくがんしょうこうぐん)●全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ(水疱)、高熱(38℃以上)、まぶたや目の充血、唇や陰部のただれ、関節の痛み、のどの痛み、皮膚の広い範囲が赤くなる●肝機能障害、肝炎、黄疸、肝不全(はき気がする、羽ばたくような手のふるえ)●血尿、血尿をともなう膀胱炎●食欲がない、はき気がする、胃・おなかの激しい痛み、背中の痛みなど●血が混ざった便、便が黒くなる、空腹時にみぞおちが痛い、血をはくなど | |
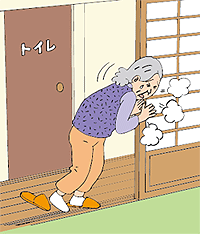
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


