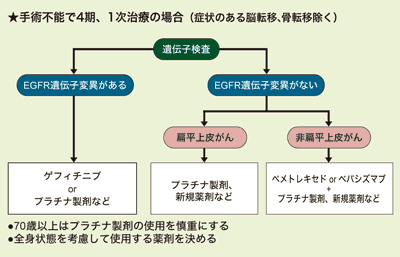個々の患者さんに応じた「より大きな効果、より少ない副作用」の薬物療法を選ぶ案内役に 速報!肺がん新診療ガイドラインの変更ポイントはここ
アルゴリズムで評価基準となる6項目
手術不能な進行非小細胞肺がんに対する薬物療法のアルゴリズムでは、坪井さんによれば、次の6つが重要なポイントになるようです。
1 骨や脳への転移、胸水など遠隔転移に伴う症状の有無
2 EGFR遺伝子変異の有無
3 全身状態(パフォーマンス・ステータス)が良好か(治療を受けるための体力の程度)
4 年齢
5 がんの組織型(扁平上皮がんか、非扁平上皮がんか)
6 キードラックの1つであるシスプラチンの治療に耐えられるか(腎毒性や吐き気などの副作用に対する忍容性)
以上を踏まえて、手術不能の4期非小細胞肺がんの抗がん剤による初回治療のアルゴリズムは、次のようになります。
まず、転移による症状のある脳転移、骨転移に対しては、放射線治療などの局所療法で症状緩和を目指します。次いで、EGFR遺伝子変異の検査結果に基づいて、変異があった場合はイレッサ、あるいは標準治療としてきたプラチナ併用療法のいずれかを患者の選択によって行います。変異がなかった場合は、プラチナ併用療法を行うのが基本です。プラチナ併用療法を行う際には、その対象により扁平上皮がんと非扁平上皮がん(腺がん・大細胞がん)に分け、後者ではアバスチン、あるいはアリムタをキードラッグにしてプラチナ製剤、新規抗がん剤との併用療法を考慮します。
「つい数年前まで、肺がんは小細胞がんか、非小細胞肺がんに大別して治療方針を立てていました。しかし、もっと細かい分類が必要になりつつあります。分子標的薬などの新しい治療薬をはじめ、抗がん剤の一部において、薬剤の治療効果を予測する因子が次々と明らかになっているからです。
すなわち、EGFR遺伝子変異の有無、がんの組織型などの因子です。腺がんの一部の患者さんでは、ALK遺伝子(*)の異常があることが明らかになり、この異常を阻害する抗がん剤が注目を集めています。肺がんの治療は、薬剤開発のレベルも含め、確実に個別化治療、いわゆるテーラーメイド治療の方向にあります」
*ALK遺伝子=キナーゼ(たんぱく質リン酸化酵素)を作らせる遺伝子の一種。ALKがEML4という遺伝子と融合する染色体異常によって肺がんが発生する
集団検診は推奨グレードBに復活
03年版、05年版では、「肺がんの診断」の章で触れられていた集団検診が、別立ての章で取り上げられています。集団検診の推奨グレードは05年度版では「C」でしたが、今回は従来と評価の方法を変えて、「B」に戻ることになりました。
症状のない人を対象に行われる住民検診や職場検診に代表される集団検診は、早期がんの発見率を上げることにつながっています。
「しかし、いくら早期がんの発見が多くなっても、死亡率の低下に寄与しなければ、真の効果とはいえないのではないかという考え方があります。実際に、それを示すエビデンスはありません。ガイドラインの推奨度は、主に大規模比較臨床試験、あるいはそれをもとにしたメタアナリシス(*)の結果を総合的に評価して決めています。
集団検診は、比較試験で良好な結果が示されていないために、前回の改訂で推奨グレードCと評価されましたが、今回は集団検診の評価方法として比較試験がなじまないという観点から、日本で行われた大規模なコホート研究(*)の結果を重視して、推奨グレードBとしました。国も集団検診を推進することで、がんで亡くなる人を減らそうと意欲的です。そういった社会的なニーズを反映させた再評価でもあります。ほかのガイドラインとは評価方法が異なることから、別立ての章で扱うことにしたのです」
*メタアナリシス=複数の臨床試験結果を統合解析すること
*コホート研究=複数の集団を比較観察し、疾病の発生と原因との関係を調べる疫学研究
TNM分類の改訂に伴う問題が浮上
がんの治療法を決める1つの重要な指標は、がんがどこまで広がっているかを1~4期で表す病期です。その国際的な分類法であるTNM分類法が一部変更され、2010年1月から運用が始まっています。
TNMのTとは腫瘍という英語の頭文字で、大きさや個数、局所浸潤具合を指します。Nはリンパ節のことで、原発巣の周囲のリンパ節への転移個数や範囲を表します。Mとは離れた臓器への転移=遠隔転移のことで、この3つを総合して病期を表すのが国際的なルールとなっています。
新しいTNM分類では、主に次のような点が変わりました。
T因子は、T1がT1a(腫瘍の大きさ2センチ以下)とT1b(同2~3センチ以下)、T2がT2a(同3~5センチ以下)とT2b(同5~7センチ以下)に細分化され、7センチを超える腫瘍はT2からT3に変更されました。
また、肺内の結節は、同一肺葉内ならT4からT3、同じ側のほかの肺葉ならM1からT4、反体側の肺ならM1からM1aにそれぞれ変更。胸膜播種、悪性胸水、心嚢水(*)はT4からM1a、遠隔転移はM1からM1bになりました。これに伴い、病期分類もこれまでの1B期、2B期の一部が2A期に、3B期の一部が3A期に移動したのです(下表を参照)。
この変更は国際的な統一基準に基づいて世界各国の治療成績などを照合できるようにするためですが、ガイドライン改訂にも影響が及んでいるとのことです。T因子やM因子の変更に応じて、病期も今まで1期だったものが2期になったりすることがあります。その場合、推奨される治療法も変わってくるはずです。そのために、さまざまな問題点が浮上してきました。
「たとえば、05年版のガイドラインでは、病期が1B期ではUFT(一般名テガフール・ウラシル)の術後補助化学療法が推奨されています。新分類で1B期になる患者さん全てに、UFT治療は同じ効果を期待できるのでしょうか。一部の患者さんではデータがなくて、医師も善し悪しを判断できない場合があります。そのような問題点をどう整理してガイドラインに反映させるか、まだ道半ばです」
第3版のガイドラインでは、そのような問題点を指摘しつつ、ウェブ上で順次情報公開し、新しいエビデンスの発表に対応してタイムリーに内容変更を行っていくことが予定されています。
「患者さんも、新分類でご自身の病期が変われば、5年生存率がどうなるのか、これまで推奨されていた治療法を続けてもいいのか、といった不安を感じられるでしょう。TNM分類変更によって混乱している患者さんは、主治医とよく話し合って、ご自身の病期や選べる治療法について、確認を取ったほうがいいですね」
坪井さんは、こうアドバイスしてくれました。
*胸膜播種・悪性胸水・心嚢水=胸膜播種は、肺を包む胸膜を超えて無数のがん細胞が胸腔内に散らばった状態。悪性胸水は胸膜内に水がたまり、肺を圧迫すること。心嚢水は心臓を包む心嚢内に水がたまること
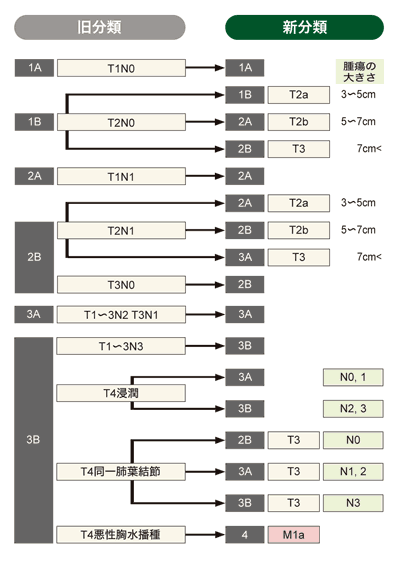
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン