アバスチンの併用で奏効率が高まり、病状の悪化を防ぎ、生存期間も延長した 切除不能な進行・再発非小細胞肺がんの最新薬物療法
日本の臨床試験でも好結果が出ている
日本でも第2相臨床試験が行われている(JO19907試験)。アメリカで行われた試験と同様、CP群とCP+アバスチン群とを比較している。無増悪生存期間で、アバスチンを加えることによる上乗せ効果がはっきり現れた。
それを示しているのが図3のグラフである。CP群に比べ、CP+アバスチン群でがんの進行または死亡のリスクが39パーセント減少している。さらに、治療開始1年後もがんが進行せず無増悪生存期間を維持している患者さんの割合はCP+アバスチン群で19.1パーセントであり、5人に1人であるということも大きな特徴といえる。
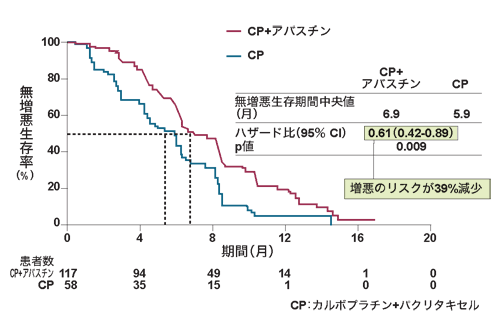
| CP + アバスチン (n=117) | CP (n=58) | |
|---|---|---|
| 完全奏効 (CR),n(%) | 1 (0.9) | 0 (0) |
| 部分奏効 (PR),n(%) | 70 (59.8) | 18 (31.0) |
| 安定(SD),n(%) | 39 (33.3) | 23 (39.7) |
| 進行(PD),n(%) | 5 (4.3) | 14 (24.1) |
| 評価不能 (NE),n(%) | 2 (1.7) | 3 (5.2) |
| 奏効率 (ORR),n(%) | 71 (60.7) | 18 (31.0)* |
また、奏効率(CR+PR)でも非常にはっきりとしたデータが出た。表に示したように、CP群の奏効率が31.0パーセントなのに対し、CP+アバスチン群の奏効率は60.7パーセントと2倍になっているのだ。
「これまで非小細胞肺がんの化学療法を行うときには、患者さんに、抗がん剤の治療をしても、がんの断面積が50パーセント以上小さくなるのは、だいたい3分の1の人なんですよ、というお話をしてきました。ところが、このデータに基づけば、小さくなる人が半分以上いますと言えるわけです。がんが小さくなれば、症状が楽になることもあります。そういう点で、とても意味のある数字だと思います」
もう1つ、里内さんが注目しているのは、治療しているにも関わらず、がんが進行してしまう(PD)患者さんの割合だ。CP群では24.1パーセントの患者さんが進行するが、CP+アバスチン群では、それが4.3パーセントに抑えられている。
「治療していて感じるのですが、患者さんにとって最も辛いのは、抗がん剤治療を行っているのに、がんが進行してしまうケースです。それが大幅に減少しているのは、臨床の現場では大きな意味があると思います」
日本で行われた臨床試験の結果からも、多くのことが読み取れるようだ。
使える人を絞り込むことで安全性が高まってきた
分子標的薬の治療では、その薬がよく効く人を選択して治療するということが行われる。たとえば、イレッサやタルセバでは、上皮増殖因子受容体(EGFR)に特定の遺伝子変異がある人に限って使用することで、従来の2剤併用療法と比べても高い治療効果が得られることが報告されている。
つまり、がん細胞の受容体に直接働きかける薬なので、がんのタイプによって、よく効いたり、効かなかったりするというわけだ。
アバスチンは、こういった薬とは効き方が異なっている。
「がんそのものに作用する薬ではなく、がんが出す血管新生の因子に作用する薬です。がん自体には働きかけず、環境に働きかけるわけです。だから、こんなタイプのがんによく効くということはありません」
では、アバスチンは誰に使ってもよいのかというと、そういうわけではない。血管新生因子に作用するため、出血に関係する副作用の危険があるのだ。中でも特に危険なのが喀血である。出血の量などによっては窒息死につながることもあるという。
「アバスチンは、こういう人によく効くということで患者さんを選択するのではなく、こういう人は危険だから除外しましょうということで、選択が行われてきました」
図4は、これまで行われてきた臨床試験で、どのように患者さんを絞り込んでいったか、それによって喀血のリスクがどのように低下してきたかを示している。
「危ないと思われる人を除外する方法で患者さんを絞り込むことにより、アバスチンを使うことに対するリスクは、どんどん下がってきたと言えます」
対象となる患者さんをきちんと選択することが、アバスチンを安全に使用するためのポイントになっている。
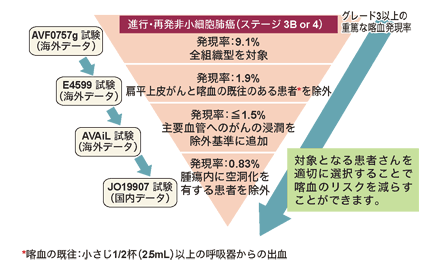
併用療法終了後はアバスチン単独で
アバスチンは、プラチナ製剤を含む2剤併用療法と組み合わせて使用される。日本の治療現場では、もともとCP療法が広く行われていたため、臨床試験と同様のCP+アバスチン療法が多くなりそうだ。
プラチナ製剤を含む2剤併用療法は、3~6サイクル行うのが基本で、最大6サイクルとされている。アバスチンを加えた場合も同様と考えてよい。
投与間隔は3週間おきで、1週目、4週目、7週目という間隔で、3剤を投与する。
そして、最大6サイクルの治療が終了した後は、アバスチンだけの投与に切り替える。そして、この維持療法を、がんが進行を始めるまで続けることが推奨されている(図5)。
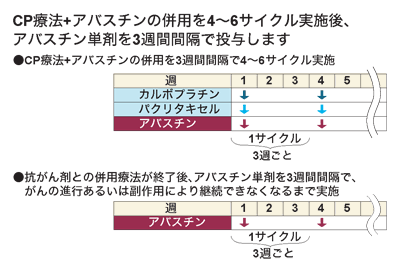
詳しくは担当の医師に確認してください。
「がんが進行するまで使うというのは、分子標的薬の普通の使い方ですね。アバスチンの臨床試験ではすべて、そのような維持療法が行われていました。動物を使った基礎研究では、アバスチンを投与すると腫瘍血管が退縮してがんが小さくなりますが、アバスチンの投与をやめると、わずかな期間で元に戻ってしまうことが示されています。薬を使っているときだけしか効いていない、と言ってもいいでしょう。だから、効いているうちは使い続けましょう、という戦略なのです」
これはよく効いている人にとっては、治療期間が長くなることを意味する。しかし、アバスチンだけなら投与時間が短くてすむし、日常生活に影響する副作用もほとんどない。
「アバスチン、カルボプラチン、パクリタキセルの点滴だと、投与時間は5時間くらいかかります。アバスチンは、初回は急性反応が起こるかもしれないため、90分かけて投与します。しかし、それで問題がなければ2回目は60分、それで問題がなければ、3回目からは30分で投与していいことになっています。アバスチンだけの維持療法なら、3週間おきに30分の点滴ですから、患者さんのQOLに影響するようなことはあまりないでしょう」
里内さんが治療した患者さんの中にも、がんの進行がうまく抑えられ、アバスチンの投与を9カ月、国内臨床試験の他施設で20数カ月続けている人がいるということだった。
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


