新たな分子標的薬の登場で、劇的な効果がみられる人も 選択肢が増えてきた!! 非小細胞肺がんの最新化学療法
アリムタは副作用が軽い印象
2剤併用療法の効果は、どの組み合わせでもほぼ同じとされているが、副作用はさまざまだ。たとえば、タキソールやタキソテールのタキサン系は、神経障害が比較的出やすく、神経症状で困ることがときどきある。ジェムザールは自覚的な副作用は軽いが、肺の線維化(組織が異常増殖し、正常な働きができなくなること)には十分な注意が必要になる。イリノテカン(一般名)も線維化に気を付けなければならない。
「アリムタは他の抗がん剤に比べて、副作用が軽い印象があります。効果の点ではあまり変わっていないと思いますが、副作用の面からすると、アリムタが少しいいように思います。アリムタとタキソテールを比較した臨床試験も行われていますが、効果は同等で、副作用はアリムタのほうが軽かったというデータが出ています」
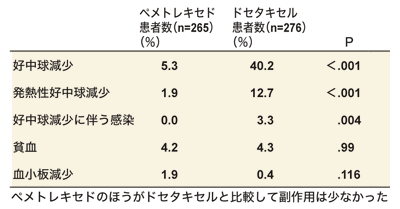
がんの種類による抗がん剤の使い分けも行われるようになってきた。非小細胞肺がんの中には、「扁平上皮がん」「腺がん」「大細胞がん」などの種類があるが、従来はどれに対しても同じように治療が行われてきた。しかし、最近になって、「扁平上皮がん」と「非扁平上皮がん」に分けて治療する動きが現れているという。
「とくにアリムタは非扁平上皮がんに効きやすく、ジェムザールは扁平上皮がんに効きやすいとされています」
EGFR陽性ならイレッサは8割に効く
再発・転移肺がんに対しては、イレッサ(一般名ゲフィチニブ)やタルセバ(一般名エルロチニブ)といった分子標的薬も使われている。EGFR(上皮成長因子受容体)という遺伝子が、変異している肺がん患者さんに効果を発揮する。
「分子標的治療と標準治療を比較した臨床試験がありますが、腺がんの場合、東洋人で遺伝子変異がある場合には、分子標的治療のほうが成績が優れていることが明らかになっています。これからは、まず��伝子変異があるかどうかを調べ、あることがわかったら、分子標的治療をメインにするということになっていくでしょう」
ただ、EGFR変異陽性でも、標準治療から始めるべきか、あるいは分子標的治療から始めるべきかについては、はっきりした結論が出ていない。分子標的治療でもずっと効いているわけではないので、どのような順番で使うのが合理的なのか、明確になっていないのである。
「一般的には、標準的な化学療法をまず行い、それが効かなくなったときに、第2次治療として分子標的薬を使うケースが多いと思います。ただ、高齢の患者さんや全身状態の悪い患者さんには、他の抗がん剤を使いにくいので、EGFR変異陽性なら、患者さんによく説明したうえで、分子標的薬を最初に使うようにしています」
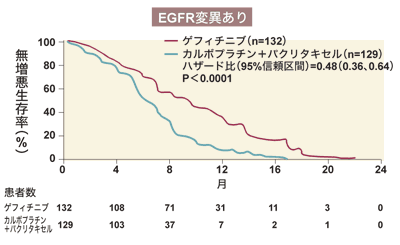
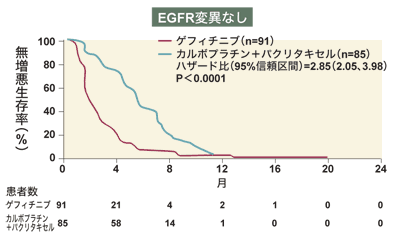
また、最近では脳といった中枢神経に転移した人にはとくにイレッサが効きやすいといった印象もあるという。
「現場の医師の間では脳に転移している人にイレッサが効きやすいといった印象を持っていましたが、最近の文献で中枢の転移病巣にはEGFR変異が多いというデータがあります」と久場さん。
現在、EGFR変異陽性の患者さんを対象にした場合、イレッサはその約8割に効果を示すことがわかっている。したがって、非小細胞肺がんの治療では、EGFR遺伝子が変異しているかどうかが、治療を進めていく上で非常に重要な情報になるのだ。


タルセバはイレッサよりも副作用が強く出る印象
タルセバは、イレッサと同じ物質を標的とする分子標的薬だが、使い方は少し異なっている。イレッサはEGFR変異陽性の場合に使われるが、タルセバは陰性の人にも効くことがあるので、陽性であるかどうかに関わらず使われているのだ。
「これまでは、すでに標準治療の化学療法を何種類か行い、イレッサも使ったような患者さんにタルセバが使われることが多かったと思います。これまでの経験ですが、イレッサよりも副作用が強く現れるという印象を持っています。口内炎が強く出ますし、発疹もイレッサよりタルセバのほうが強いですね。これは、規定の投与量が多いためではないかといわれています」
分子標的薬と一般的な抗がん剤との併用に関しては、欧米で臨床試験が行われ、イレッサに関しては否定されている。併用しても効果が増強しなかったのだ。ただ、アバスチン(一般名ベバシズマブ)と抗がん剤の併用に関しては、いい結果が出ている。
「日本ではまだアバスチンが肺がんの治療薬として認可されたばかりですが、かなり期待されています。今後はアバスチンと化学療法剤の併用療法が行われるようになるでしょう」
ただ、アバスチンは副作用として出血傾向が強まるので、気道近くに顔を出しているような扁平上皮がんには使えないという。喀血を招く危険性があるので禁忌となっているのだ。
「非小細胞肺がんの化学療法は、まだ十分とはいえませんが、分子標的薬が登場したこともあり、10年前と比べれば、ずいぶん進歩しました。かつては化学療法を行うことで患者さんやご家族に喜んでもらえることは少なかったのですが、最近はそういったケースが増えてきました」
これからも新しい分子標的薬が登場してくることなどで、非小細胞肺がんの治療は進歩していくことになるだろう。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


