日本からは、全身状態が悪くなった肺がん患者さんに朗報も 抗がん剤の効果と副作用で明らかになった人種差・民族差の大きさ
全身状態が不良でも1次治療でイレッサが有効
イレッサについては、日本の研究グループから有益な発表があった。
化学療法の適応ではないとされる全身状態不良の非小細胞肺がんでも、EGFR遺伝子変異を持っている場合、ファーストライン治療としてイレッサを用いると高い効果を示すことが明らかとなったのだ。
発表したのは、北東日本ゲフィチニブ研究グループに参加する埼玉医科大学教授の小林国彦さん。
日本肺癌学会の肺癌診療ガイドラインでは、全身状態不良の非小細胞肺がんの場合、化学療法の適応はないとされ、緩和医療が選択されることが多く、予後も3~4カ月ほどでしかない。ところが、そのような患者でも、イレッサの投与によって1年以上の生存期間の延長が認められたというのだから驚異的といえる。
試験の対象となったのは、EGFR遺伝子変異を有し、根治的放射線治療や手術の適応がない、抗がん剤治療歴がない、20~75歳未満(年齢の中央値は72歳)で全身状態不良、白血球数・血小板が少ないため抗がん剤治療の適応にならない、肝腎機能が保たれている、緩和医療での予後予測が4カ月以下と推察される患者さん29名で、イレッサ1日当たり25ミリグラムを連日投与した。
その結果、奏効率は62パーセント、1年生存率は73パーセントだった。また、全生存期間の中央値は17.8カ月であり、無増悪生存期間の中央値は9.3カ月。全身状態改善率も79パーセントで、全身状態が臨床的に意義のある改善(グレード3~4から1~2へ)をした人は66パーセントにのぼった。
「EGFRの遺伝子変異を調べる検査は保険適応になっているので、だれでも受けることができます。日本ではEGFR遺伝子に変異のある人は3~4割いるとみられていますが、今後、全身状態不良の非小細胞肺がんでもEGFR遺伝子変異が陽性の場合、イレッサの投与が勧められることになるでしょう」
なお、研究グループでは今後、やはりEGFRを阻害する分子標的薬タルセバ(一般名エルロチニブ)でも、全身状態不良の患者さんに対する効果の評価や、EGFR遺伝子変異があってイレッサの投与を受けても奏効に至らず変化がみられなかった患者さんに対し、タルセバの効果を確かめたい、としている。
| 患者数 | 奏効率 | 95%信頼区間 | |
|---|---|---|---|
| 完全奏効 | 1 | 3 | ー |
| 部分奏効 | 18 | 62 | ー |
| 安定 | 7 | 24 | ー |
| 進行 | 2 | 7 | ー |
| 1 | 3 | ー | |
| 全奏効 | 19 | 66 | 51ー80 |
| 病勢コントロール率 | 26 | 90 | 80ー99 |
吐き気・嘔吐を抑える新薬にも注目!
「患者さんはどうしても新しい抗がん剤のほうに目がいきますが、副作用を抑える薬も着実に進歩しています」と酒井さん。
その言葉の通り、今年のASCOでは「シスプラチンに新規制吐剤のNK1受容体拮抗薬・エメンド(一般名アプレピタント)を併用すると、シスプラチンの吐き気・嘔吐の頻度が穏和なパラプラチン(一般名カルボプラチン)と同レベルまで軽減できることがメタアナリシス(複数の研究結果の解析)で証明された」という発表があった。
シスプラチンは肺がん治療でよく使われる薬だが、吐き気・嘔吐の副作用が強いことで知られる。そこで、こうした副作用を軽減することを目的に開発されたのがカルボプラチンだ。シスプラチンとカルボプラチンとの比較では、ややシスプラチンの効果が高いとされる。しかし、吐き気・嘔吐の副作用が強いことを理由に、シスプラチンをやめてカルボプラチンを用いることが多いのが現実だ。
制吐剤で吐き気・嘔吐が抑えられ、シスプラチンの効果を得ることができるなら、これほどの朗報はない。
米国ではすでに承認されていて、NCCN(全米の主要ながんセンターのネットワーク)のガイドラインでは、「催吐性が高度または中等度の化学療法」への使用が推奨されている。
ところが、日本では未承認。すでに2年前に開発治験が終わり、承認申請が出されているが、審査が遅れていて承認の目処が立っていない。このため、やむなく海外から個人輸入している人も少なくないようだ。
「日本における一刻も早い承認が待たれます」と酒井さんも強い期待を述べている。
なお、新規制吐剤にはもう1つ、パロノセトロン(5HT-3受容体拮抗薬)という薬がある。こちらは半減期が長いのが特徴。このため、急性の吐き気・嘔吐だけでなく、抗がん剤投与の24時間以降に出現する遅延性の吐き気・嘔吐にも有効といわれている。この薬も、日本で開発治験が終わり、最近承認申請が出されたところである。
抗がん剤の投与による吐き気・嘔吐は、約80パーセントの人に現れるといわれ、ひどい場合は治療が困難になることもある。新規抗がん剤の開発とともに、こうした副作用を抑える薬にも期待したい。
脳転移予防のための全脳照射は少線量に
限局型小細胞肺がんの完全奏効(CR)例に対する予防的全脳照射(脳転移予防のための脳への放射線療法)についての発表も注目された。
2007年のASCOでは部分奏効(PR)以上の症例に対する予防的全脳照射の有効性が明らかにされ、世界の標準治療となった。
今年のASCOでは、照射する線量が多いほうがいいか、少ないほうがいいかを比較した試験の結果が発表され、CR例に対して25グレイと36グレイとで比べたところ、線量の少ない25グレイを照射したほうが、36グレイの照射より生存期間が有意に延長されることがわかった。
理由についてはいろいろな説があるが、放射線の量が多いとかえって免疫力を低下させ、がんの増殖が活発になるのではないかという指摘がある。また、線量が多いほうが、脳への転移よりむしろ、原発巣である肺での再発を増やすことも明らかとなったが、その理由は不明である。
いずれにしろ、36グレイでなく25グレイに軍配が上ったのだから、今後、日本でも、予防的全脳照射は25グレイで行われるようになるのではないか、と酒井さんは語っている。
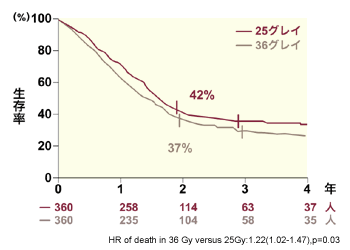
[原発巣である肺での再発率]
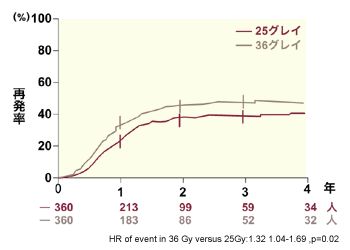
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


