がんのタイプによって薬を選べる時代が近づいた 変わる非小細胞肺がんの最新化学療法
術後補助療法に上乗せ効果
03年以降、臨床試験の結果が相次いで発表され、その有効性が明らかになってきたのが術後の化学療法(補助療法)だ。日本でも標準治療として推奨されるようになってきた。
がんが原発巣にとどまり3センチ未満で、リンパ節などへの転移がない1a期なら、基本的には術後の化学療法は行われない。3センチを越えていて、手術では完全切除されたがリンパ節転移があった場合に、術後の化学療法が強く勧められる。
久保田さんによれば、術後の化学療法でよく推奨されるのは、シスプラチン+ナベルビン(一般名ビノレルビン)の2剤併用療法という。シスプラチン+ジェムザール(一般名ゲムシタビン)なども、劣らないぐらいの効果があるともいわれているが、1番エビデンス(科学的根拠)があるのはシスプラチン+ナベルビンだという。
04年に報告された試験では、術後病期1b期と2期を対象に、シスプラチン+ナベルビンの化学療法を行った群と手術単独群を比較したところ、5年生存率で15パーセントの上乗せ効果があった。また、完全切除された1b期から3a期までを対象にした別の試験でも、やはり5年生存率で10数パーセントの上乗せ効果が示されている。
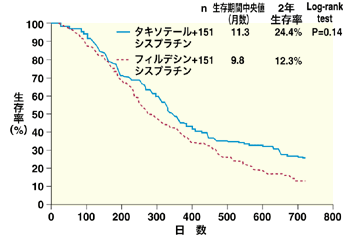
最新の研究では、シスプラチン+タキソテールの2剤併用療法が注目されている。
「シスプラチン+タキソテールは、4期の患者さんを含めて、現在、標準治療の1つとなっているシスプラチン+ナベルビンよりも、有意に生存期間が良好というデータがメタアナリスで示され、術後補助化学療法にシスプラチン+タキソテールを用いた臨床試験が行われています。日本で行われたシスプラチン+タキソテールの2剤併用療法とシスプラチン+フィルデシン(一般名ビンデシン)の比較試験でも前者のほうが投与回数が多いにもかかわらず、貧血や白血球減少症の発現の割合は少なく、生存期間の延長が確かめられています」
| 投与サイクル | DC(n=151) | VdsC(n=151) | ||
|---|---|---|---|---|
| 患者数 | % | 患者数 | % | |
| 1 | 115 | 100 | 151 | 100 |
| 2 | 132 | 87 | 115 | 76 |
| 3 | 84 | 56 | 53 | 35 |
| 4 | 41 | 27 | 17 | 11 |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 投与サイクル数* | ||||
| 中央値 | 3 | 2 | ||
| 範囲 | 1-9 | 1-5 | ||
| DC:タキソテール+シスプラチン VdsC:フィルデシン+シスプラチン *P=.01. | ||||
[タキソテール+シスプラチン併用療法の副作用(血液毒性)]
| 毒性(病期) | DC(n=151) | VdsC(n=151) | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | % | 患者数 | % | ||
| 貧血 | <.01 | ||||
| 3期 | 15 | 10 | 34 | 23 | |
| 4期 | 0 | 0 | |||
| 血小板減少症 | |||||
| 3期 | 1 | 1 | 0 | 0 | <.01 |
| 4期 | 0 | 0 | |||
| 白血球減少症 | |||||
| 3期 | 66 | 46 | 92 | 68 | |
| 4期 | 3 | 10 | |||
| 好中球減少症 | |||||
| 3期 | 59 | 74 | 41 | 77 | |
| 4期 | 53 | 76 | |||
| DC:タキソテール+シスプラチン VdsC:フィルデシン+シスプラチン | |||||
分子標的薬も次々と
分子標的薬の開発も相次いでいる。
02年に承認されたイレッサ(一般名ゲフィチニブ)もその1つ。がん細胞の表面にあるEGFR(上皮成長因子受容体)に作用し、がんの増殖を抑える薬だ。肺障害など副作用の問題はあるものの、女性や腺がん、非喫煙者、EGFRの遺伝子配列に異常がある人(日本人など東洋人に多い)に効きやすいといわれる。
欧米では、血管新生阻害剤のアバスチン(一般名ベバシズマブ)が、プラチナ製剤ベースの化学療法と併用するファーストラインの治療薬として承認されている。
アメリカで行われた比較試験によると、パラプラチン(一般名カルボプラチン)+タキソール(一般名パクリタキセル)にアバスチンを加えると、有意に予後良好であるとの結果が出た。しかし、一方で毒性も強く、治療関連死亡が対象群では0.5パーセントなのに、アバスチンと併用した群では3.6パーセントだった。
また、ヨーロッパでは、シスプラチン+ジェムザールにアバスチンを併用した試験が行われ、無増悪生存期間は対象群より良好だった。ただし、全生存期間ではそれほどの差はなかったという。
日本では、アバスチンは大腸がんに対しては承認されているが、肺がんへの適応に関しては治験が行われている最中。
「アバスチンは喀血や感染などの毒性も強く、70歳以上の高齢者だと毒性はさらに増えるようで、より安全に使われるようなコントロールが大事。承認されても、実際に使えるのは進行性非小細胞肺がん患者の2~3割程度と思われます」
昨年10月に承認された新しい薬剤にタルセバ(一般名エルロチニブ)がある。イレッサと同様、EGFRに作用する薬で、イレッサが250ミリ錠の1規格しかないのに対して、25ミリ錠、100ミリ錠、150ミリ錠の3規格があり、量の調節が可能であることも特徴の1つとなっている。
「タルセバとイレッサは効き方がどう違うか、まだあまりはっきりしていません。タルセバとイレッサを直接比較した試験も行われていません。ただ、肺毒性はイレッサと同じぐらいありそうだし、皮膚毒性などは、今の開始用量ではタルセバのほうが強いようです。毒性に応じて減量が可能なのがタルセバの特徴でもありますが……」
また、イレッサよりタルセバのほうが価格が高いため、経済的な理由で服用をためらうケースもあるという。
「イレッサにしろタルセバにしろ、肺毒性が命取りになる可能性があるので、もともと肺線維症のような病気を持っておられる方には使いづらい。効果が期待できる方に対するセカンドライン以降の薬と考えられると思います」


肺がんの分子標的薬。イレッサ(左)とタルセバ
タイプによって薬を選ぶ時代に
分子標的薬ではないが、アリムタ(一般名ペメトレキセド)という新しいタイプの抗がん剤もある。アリムタは葉酸(水溶性ビタミンの一種)と分子構造がよく似ている葉酸代謝拮抗剤。がん細胞は増殖のため葉酸を必要とするが、アリムタは葉酸の代わりに作用してがん細胞の増殖を阻害する。
日本では、悪性中皮腫の治療薬として承認されているが、肺がんにはまだ認められていない。昨年9月、アリムタとシスプラチンを併用する治療法は、ジェムザールとシスプラチンの併用療法と比べて、副作用が少なくて同等の効果が得られたとの報告があり、患者にとって有益な治療法と評価されている。
「腺がんと大細胞がんでみると、シスプラチン+アリムタのほうが生存期間が延びるという結果でしたが、扁平上皮がんでは逆でした。ですから、腺がんなど、扁平上皮がん以外のタイプにはかなりの期待が持てる可能性があります」
イレッサのように、女性とか非喫煙者により効果が大きいという薬もある。すると今後の方向性としては、がんのタイプによって薬剤の選択が変わってくることも十分考えられるだろう。
また、骨転移に対しては、ゾメタ(一般名ゾレドロン)という骨吸収抑制剤があり、日本でも承認されている。抗がん剤というより、破骨細胞による骨の破壊を防ぐ働きをする。
「いわゆる”痛み止め”とは違うので、1~2回やって痛みが取れないからやめたというのでは、あまり薬の効果を引き出すことにはなりません。骨転移のある場合に症状を出にくくする予防薬ととらえてほしい」
と久保田さんはアドバイスしている。
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


