間質性肺疾患の合併に気をつければ、間質性肺炎は防げる 肺がんの分子標的薬はサードラインで使うのが標準的
肺がんの分子標的薬には遺伝子異常とのかかわりが
では、イレッサとタルセバの違いは、どんなところにあるのでしょうか。
イレッサとタルセバが効くシステム(「機序」といいます)はだいたい同じと考えられていますが、イレッサはとくにある種の遺伝子変異のある細胞に効くのではないかと考えられています。ちなみに、イレッサがほかのがんに効かないのも、ほかのがんにはこの遺伝子変異がないためではないか、と推測されています。
タルセバも同様に、この遺伝子変異のある細胞に効きますが、タルセバは遺伝子変異のない細胞にも効くようで、この薬がすい臓がんに効くのは、そのあたりの機序とかかわりがあるのではないか、と考えられています。
というように、薬の成り立ちや薬が効く機序にも違いがあると思われますが、薬の効き方や、それにともなって使い方にも多少違いがあると、私は考えています。
たとえば、海外には、タルセバとタルセバのプラセボ(偽薬)、イレッサとイレッサのプラセボを使った2つの第3相試験(最も厳密に行われた比較試験)があります。イレッサの試験では、有意差は出ていないものの、プラセボと比べるとイレッサのほうが少し成績が上です。有意差が出なかったのは、イレッサは効く人にはよく効くが、効かない人には全然効かないという特徴が影響しているかも知れません。
一方、これらの試験の結果からは病状安定、つまり、がんの大きさが変わらない期間を長くする効果は、少しタルセバのほうが高いようです。したがって、がんを小さくする効果があまりないと感じられても、タルセバのほうは「明らかに悪くなった」というデータが出てこない限り、使い続けたほうがいいだろうと思います。
もちろん、副作用との兼ね合いでもありますし、ここは医師によっても意見の分かれるところだろうと思いますが。
副作用が強く出るのは、つらいものです。が、イレッサは飲む量を決める試験のとき、2週間投与して2週間休むというスケジュールで行ったところ、休んでいる間に悪くなるケースが確認されました。そのため、今���は毎日飲み続けるようになっています。
タルセバは今のところ、最大耐用量(体を壊さずに飲めるギリギリの量)を飲まなければならず、そのために皮疹などの副作用も強めに出る気がしますが、その一方、250ミリグラム剤1つしかないイレッサに比べると、25、100、150ミリグラムと錠剤に3サイズがあり、微調整が可能です。
何とか患者さんにあう薬を選び、明らかに悪くなるまでは、がんばって続けていただければと思います。
新しい分子標的薬が出てくる可能性も
イレッサ、タルセバ以外に、肺がんの分子標的薬として今、注目されているのは、大腸がんの治療薬として開発されたアバスチン(一般名ベバシズマブ)です。
アメリカでは肺がん治療薬としてすでに承認されていて、日本でもつい最近、肺がんに対する治験の症例集積が終わりました。すぐとは行きませんが、次に承認されるのはこれではないかと思います。
アメリカのデータでは、「非小細胞肺がん」に対して行われている2剤併用の抗がん剤治療に比べ、アバスチンを上乗せすると、平均2カ月の延命効果があるとの報告がなされています。
ただ、副作用もありますし、「扁平上皮がん」だと喀血する可能性があるなど、同じ「非小細胞肺がん」のなかでも、少し適応が限られるようです。
また、がんが新しく血管をつくるのを阻害する分子標的薬で、腎がんなどに効果があるといわれているスーテント(一般名スニチニブ)が、肺がんにも効いたという報告も海外で出てきています。
さらに、がんの増殖遺伝子の受容体(IGF-1R)にくっついて、がんが増殖できないようにする抗体や、イレッサが効かなくなる原因となる増殖因子c-MET(シーメット)にスイッチが入らないようにする薬など、他にも分子標的薬の開発は次々と進められています。
今後も新しい薬が開発されてくることと思いますが、まずは患者さんが今ある治療を、副作用に注意しつつ上手に使い、少しでもいい状態を長く保てるよう、願ってやみません。
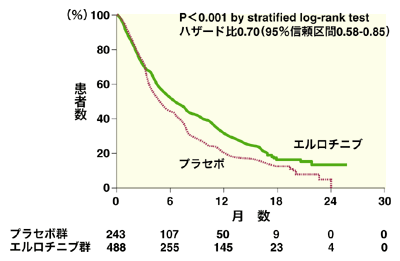
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


