科学的視点を持ち、それに基づいて治療することが患者の利益につながる 肺がんの分子標的薬の現在
イレッサをどう使うか
抗がん剤の臨床試験は、さまざまな患者さんを集めて、色々な状況下での効果が繰り返し確かめられる。そうしたなかから、効果が期待できるであろう患者さんの特徴が徐々に明らかとなり、抗がん剤の使い方もはっきりと見えてくる。イレッサでも、世界各国で幾つかの臨床試験が行われ、詳しいことが分かってきた。それらの臨床試験を、滝口さんが丁寧にまとめて下さった(表1)。日本で使える非小細胞肺がんの分子標的薬は、今のところイレッサだけだが、間もなくタルセバ(一般名エルロチニブ)も保険承認される見通しなので、それらの試験結果が列挙されている。
イレッサに関してのみ、要点をかいつまんで説明したい。これらの試験は、ファーストラインとセカンドラインに分けられる。ファーストラインとは、化学療法をまだ行っていない患者さんを対象とするもので、セカンドラインとは、既に化学療法を行った患者さんを対象にするものである。つまり、イレッサを最初の“一の手”として使った場合がファーストライン、次の“二の手”として使った場合がセカンドラインと称される。
試験の成績は、患者さんの生存期間に延長がもたらされるか否かで評価された。まず、ファーストラインだが、現在の標準的化学療法にイレッサを併用して、進行がん患者さんの経過をみたところ、全体としては併用効果がまったく認められなかった。すなわち、標準的化学療法のみのグループと比較しても、生存期間に差がなかったのである。これでは、イレッサを患者さんに投与する意味がなく、標準的化学療法だけで良いことになる。
| 試験名 | 薬剤 | 患者数 | 対象者 | 国 | 試験期間 | 主な結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL-1 | イレッサ | 210 | 化学療法治療歴あり | 日本、米国、欧州 | 2000-2001 | 250mgと500mgで効果は同等。副作用は250mgのほうが少ない。18-19%の奏効率。37-40%の症状緩和率 |
| IDEAL-2 | イレッサ | 221 | 化学療法治療歴あり | 米国 | 2000-2001 | 250mgと500mgで効果は同等。副作用は250mgのほうが少ない。9-12%の奏効率。35-43%の症状緩和率 |
| INTACT-1 | イレッサ | 1093 | 進行非小細胞肺がん/治療歴なし | 主に欧州 | 2000-2001 | 標準化学療法(シスプラチン+ゲムシタビン)に併用した場合、生命予後に対するイレッサの上乗せ効果なし |
| INTACT-2 | イレッサ | 1037 | 進行非小細胞肺がん/治療歴なし | 主に米国 | 2000-2001 | 標準化学療法(カルボプラチン+パクリタキセル)に併用した場合、生命予後に対するイレッサの上乗せ効果なし |
| SWOG0023 | イレッサ | 620 (無効中止) | 局所進行非小細胞肺がん/治療歴なし | 米国 | 化学放射線治療後にイレッサを使うことによる予後改善なし | |
| ISEL | イレッサ | 1692 | 化学療法治療歴あり | アジア(日本を含まない)、 欧州 | 2000-2001 | 2次治療としてイレッサを使うことによる生命予後改善なし。東洋人に限った場合、および非喫煙者に限った場合は改善の可能性? |
| V15-32 | イレッサ | 489 | 化学療法治療歴あり | 日本 | 2003-2006 | 既治療例に対する標準化学療法(ドセタキセル)と比べ、イレッサの生命予後に対する効果が劣っていないとは示されなかった |
| TRIBUTE | タルセバ | 1059 | 進行非小細胞肺がん/治療歴なし | 米国 | 2001-2002 | 標準化学療法(カルボプラチン+パクリタキセル)に併用した場合、生命予後に対するタルセバの上乗せ効果なし。非喫煙者に限った場合は効果がある可能性? |
| BR.21 | タルセバ | 731 | 化学療法治療歴あり | 北米、南米、アジア | 2001-2003 | 2次治療としてタルセバを使うことによる生命予後改善あり |
| TALENT | タルセバ | 1172 | 進行非小細胞肺がん/治療歴なし | 欧州 | 2001-2002 | 標準化学療法(シスプラチン+ゲムシタビン)に併用した場合、生命予後に対するタルセバの上乗せ効果なし |
セカンドラインとしての意義
| イレッサ N=235 | プラシーボ N=107 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢(中央値) | 61歳 | 61歳 | |
| 男性 | 60% | 60% | |
| PS* 0-1 | 72% | 72% | |
| 非喫煙者 | 41% | 41% | |
| 2次治療 | 54% | 65% | |
| 組織型 | 腺がん | 64% | 64% |
| 診断から無作為化 までの期間 | <6カ月 | 25% | 32% |
| 6-12カ月 | 40% | 38% | |
| 前化学療法における 最良総合効果 | CR/PR | 21% | 21% |
| SD | 35% | 32% | |
| PD/NE | 44% | 48% | |
では、セカンドラインではどのような成績が得られたのだろうか。既に化学療法を行った患者さんに対して、イレッサ単独での治療が付け加えられ、その後の経過が調べられた。結果として、全体的には生存期間の明らかな延長は証明されず、残念な結果であった。
しかし、非喫煙者や東洋人だけのデータに限って解析すると、そこには生存期間を延長させる可能性(図3・4参照)が示唆された。
こうした臨床試験の結果から、今のところイレッサは、標準的化学療法の後に再発した患者さんに対する治療選択のひとつとして位置づけられ、特に腺がんで非喫煙者であれば、延命効果が期待できると考えられている。ちなみに、以上のことは、日本肺癌学会の一番新しい『診療ガイドライン』(2005年度版)にも詳しく記載されている。重要な記述があるので、一部を原文のまま抜粋する。
●分子標的薬剤の推奨度としては、『非小細胞癌に投与を推奨するだけの根拠は明確でない(グレードC)』と記載されている。
●エビデンスとしては、『ゲフィチニブ(イレッサ)の奏効には喫煙歴、性別、組織型等が影響することが報告されている』、『化学療法と(分子標的薬)の同時併用療法では、化学療法単独に比較してその意義を示すことができなかった』、『一般診療で、化学療法との同時併用は行うべきでない』などと記されている。
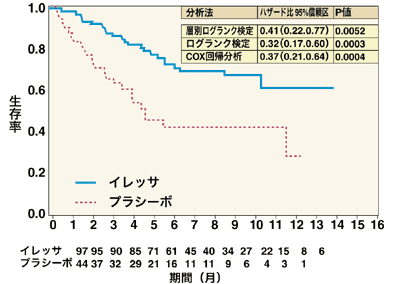
科学的視点を持つことが大切
以上を踏まえて、滝口さんに、今後の肺がん治療における分子標的薬の意義を、どのようにお考えなのかと質問した。
「これから先、最先端の研究から、色々な分子標的薬が開発されてくるでしょう。そのことに、大きな期待を寄せています。がんと戦う手段が豊富に揃って、それをエビデンスに基づいて使いこなせば、患者さんには大きな利益となるでしょうから」。
さらに、滝口さんはイレッサについて次のように語った。
「作用のメカニズムなどを更に詳しく研究すること。そして、効果が期待できる患者さんの特徴を、遺伝子レベルで明らかにすることなどが大切です。イレッサで治療していると、時には短期で劇的な改善を示す患者さんと出会います。大変に優れた薬剤ですが、万人にその効果が現れる訳ではありません。誰に効くのか、なぜ効くのか、どう使えば良いのか。われわれは辛抱強く、その研究を続けていかなければなりません。患者さんのためですから。」
科学に対する真摯なまでの姿勢と、治療に対する情熱が、滝口さんの中には確かに共存していた。こうした多くの医師や研究者に支えられ、がんの薬物療法は進歩を続けているのだと実感できた。
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


