腹腔内投与による毒性の問題を乗り越え、標準治療となるか 見直される卵巣がんの腹腔内化学療法
理想的な腹腔内化学療法の条件は?
ただし、1つの薬剤だけではサンドイッチ作戦はなかなかうまくいかないようです。
分子量が大きく、水に溶けにくい薬は腹腔内に長くとどまり、腹腔内における薬剤濃度も高い割合を示します。これに対し、分子量が小さく、水に溶けやすい薬は滞在時間が短く、腹腔内における薬剤濃度も低くなってしまいます。
腹腔の外には間質があり、ここには毛細血管が張りめぐらされています。毛細血管の血管内皮にはナノレベル(1ナノメートルは10億分の1メートル)の微小の穴があいていて、分子量の小さな物質と水分は容易に通過しやすいものの、大きな物質は通りにくい仕組みになっています。このため、分子量の大きい物質は腹腔内から血管への移行が容易ではなく、このため腹腔内に長くとどまることになります。
また、腹腔内は少量の水が循環しているので、水に溶けやすい薬だと早く水に溶けて血管に移行して、腹腔内での効果も短くなってしまいます。
では、個々の抗がん剤にはどんな違いがあるかとみてみると、ブリプラチン、パラプラチンといったプラチナ製剤(*)は分子量が比較的小さく、いずれも水に溶けやすい。一方、タキソールは分子量が大きく、水に溶けにくい薬です。
そこで藤原さんは語ります。
「理想的な腹腔内化学療法の条件としては、腹腔内には長時間留まる高分子で水に溶けにくい薬を用いるのが1番いい。ほかの臓器には行かず、腹腔内に長く留まるなら、全身への副作用も少なくて済みます。ところが、パラプラチンに代表されるプラチナ製剤を凌駕する薬は今のところないのが現実です。プラチナ製剤は低分子量で比較的水に溶けやすく、本来は理想的な腹腔内化学療法製剤とはいえません。それでも、プラチナ製剤は血流を通して腫瘍中心部に速やかに移行できる特性があります。そこで、プラチナ製剤を用いた腹腔内化学療法は全身投与の1ルートと考えられ、サンドイッチ作戦にふさわしいといえます」
*プラチナ製剤=白金系の抗がん剤。DNAに直接作用しその複製を阻害したり、アポト-シス(細胞死)を起こす
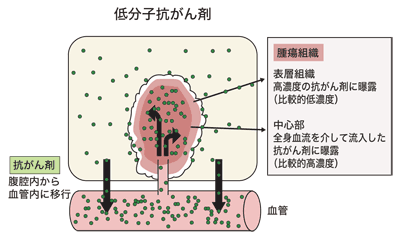
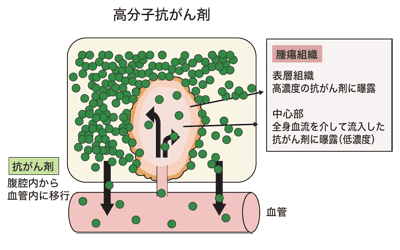
なぜ腹腔内投与が認められなかったのか
かなり早い時期から、腹腔内化学療法の有用性を主張してきたのが藤原さんです。しかし、米国で行われたいくつかの臨床試験で高頻度の毒性が出たことが問題となって、いまだに広く受け入れられるまでにはなっていません。
これに対して藤原さんは、「毒性が問題になったのは不適切な試験デザインが原因の1つ」と語ります。
藤原さんによれば、腹腔内化学療法の毒性で1番怖いのはカテーテルのトラブル。ポートをに針を刺して抗がん剤を注入するときに不潔になると感染症を引き起こし、最悪の場合、腹膜炎を起こすこともあります。
薬剤毒性は静脈投与と同じで、消化器症状、神経毒性、好中球減少などがみられますが、腹腔内投与による腹痛などのほかにとくに目立つものはないといいます。
それでも、様々な理由で世界の卵巣がん治療の流れからは取り残され、「存在意義が危うくなった時もある」と藤原さんが語るほど。ところがそんなとき、状況を一変させる出来事がありました。
06年1月、世界的に権威のある医学雑誌「ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディスン」に米国で行われた第3相試験の結果が発表されました。
3期の卵巣がん患者に、当時の標準治療であるタキソール+ブリプラチンの静脈投与と、タキソール静注投与+ブリプラチン腹腔内投与とを比較したところ、後者は生存期間をほぼ1.5年延長しました。ただ、副作用がきつくQOL(生活の質)が低下したものの、治療1年後では差異はなかったといいます。
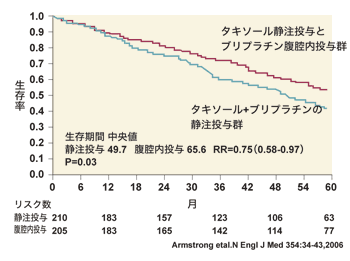
腹腔内投与を検証する臨床試験が各国で開始
この結果を受けて、米国のNCI(国立がん研究所)は腹腔内化学療法を推奨する「クリニカルアナウンスメント(臨床提言)」を発表。NCIのこうした発表は異例です。
「ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディスン」に載った試験結果の通りなら、腹腔内投与は標準治療になり得る、というので、現在、日本、カナダ、米国、ヨーロッパなどで、副作用が軽くより有効な腹腔内化学療法を検討するための大規模な臨床試験が開始されます。
日本では、「iPocc試験」という名称で行われます。2期以上の患者を対象に、50~60施設が参加して行われる予定で、標準治療であるタキソール+パラプラチンの新規投与法として、パラプラチンの腹腔内投与+タキソール静脈のウィークリー投与(毎週1回投与)の有用性を検証する試験です。
タキソールの毎週投与とセットで
実は、タキソールのウィークリー投与については最近、大きなニュースがありました。
09年11月、日本発の臨床試験の結果が英国の医学雑誌「ランセット」に掲載されました。
この試験は、日本で抗がん剤治療を行っている主な医療機関が参加する「婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構(JGOG)」が、約630人の患者を対象に実施した「JGOG3016試験」。
現在、卵巣がんのファーストライン(初回治療)としては、タキソール+パラプラチンを3週間に1回静脈投与するのが標準的な治療となっています。これと、新しい方法としてタキソールを毎週1回投与(パラプラチンの投与法は標準治療と同じで、タキソールの1回の投与量を減らす)する療法とを比較したのです。
結果は08年のASCO(米国臨床腫瘍学会)で発表され、無増悪生存期間が約11カ月もの延長を示したことから、高い評価を受けました。
このときは全生存期間についてのデータが得られていなかったのですが、その後、全生存期間も従来の65パーセントから72パーセントに向上したことが明らかとなり、「ランセット」に発表されました。
「この試験結果は、おそらくここ数年の中でのチャンピオンデータです。米国ではこの結果に注目して、日本と同じような結果が得られるかどうかの臨床試験が始まります。それだけ世界中に大きな影響を与えているといってよいでしょう」
藤原さんはこう語りますが、今後日本でも、ウィークリー投与が標準治療になる可能性があります。
生存期間を著しく延長させたウィークリー投与にプラスして、藤原さんによれば「理論的には卵巣がんに対して最適な投与方法と考えられている」腹腔内化学療法を併用すれば、さらに大きな上乗せ効果が期待できるのではないでしょうか。日米欧で行われる臨床試験の結果が注目されます。
同じカテゴリーの最新記事
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線
- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず
- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが
- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた
- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状
- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待


